「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
旧車の売買と鑑定市場

プリウスのリセールバリューは高い?高く売れるプリウスとは
近年、国産車のほとんどの車種にハイブリッドモデルがラインナップされています。ハイブリッド車の元祖は1997年に初代が発売されたトヨタ自動車のプリウスです。プリウスはハイブリッド専用車として開発され、世界を驚かせました。初代登場から25年が経った2022年には5代目が発表され世界中で注目されています。人気が衰えることのないプリウスですが、リセールバリューはどのようになっているのでしょうか。この記事ではプリウスのリセールバリュー事情について解説いたします。 プリウス人気のモデル 2022年現在、新車で購入できる現行型のプリウスは4代目のZVW50/51/55型です。2015年12月に発売されたモデルであり、中古市場にも多く流通しています。 モデル別にリセールバリューの良し悪しはあるのでしょうか。2022年11月現在での販売価格を調査してみました。 初代モデル(1997年12月~2003年8月) 流通台数は1台で価格は110万円でした。意外な高額プライスに驚きを隠せません。プレミア価格になっていますね。もし、初代プリウスをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ旧車王で鑑定させてください。 2代目モデル(2003年9月~2012年1月) 流通台数は約150台で価格は9万円~129万円でした。上位の約20%には50万円以上のプライスタグがついています。中には走行距離17万km、2009年式のモデルが約60万円になっているものもありました。過走行でも、人気グレードであったり、オプションが評価されて高額査定になるケースもあるようですね。 3代目モデル(2009年5月~2015年11月) 流通台数は約4,500台で価格は19万円~359万円でした。3代目モデルが2022年11月現在、最も流通台数の多いモデルです。この年式になってくると7、8割は販売価格が100万円以上と高額。型落ちでも人気の高さをうかがえました。 4代目モデル(2015年12月~) 流通台数は約4,150台で価格は98万円~438万円でした。よほどのことがない限り、販売価格は200万円以上です。新車価格はエントリーグレードが259万7,000円のため、23%オフぐらいの価格感ですね。 プリウスの人気グレードは? プリウスの年式ごとの販売価格を見てきましたが、どのグレードが人気なのでしょうか。ここからはプリウスの中でも高い人気を誇っているグレードを紹介します。 標準グレード「S」 最も人気のグレードは標準グレードの「S」です。上級ファブリック素材が採用されているシートが大きな特徴といえるでしょう。エントリーグレードと比較すると高級感があり、乗り心地の良さを感じられます。 特に「S ツーリングセレクション」は高い人気を誇ります。エアロパーツや大型のホイールが装着されており、スポーティーな印象を与えるエクステリアとなっています。合成皮革でシートヒーターが搭載されているシートも人気の理由の一つです。 最上級グレード「Aプレミアムツーリングセレクション」 「新車では高くて手が出しづらいけど、中古なら購入できる」という理由から、中古市場では最上級グレードの人気が高くなっています。プリウスの場合は「Aプレミアムツーリングセレクション」が最上級グレードです。 特徴は上級グレード「A」にスポーティーなパーツを装着したものになっています。やはりクルマ選びで重視されるポイントは見た目なのでしょう。かっこよさから人気が高く、リセールバリューも高い傾向にあります。 プリウスの人気カラーは? クルマのボディカラーは、リセールバリューに大きく影響を与えます。ここからはプリウスの人気のカラーについて見ていきましょう。 ホワイトパールクリスタルシャイン 人気第一位はホワイトパールクリスタルシャインです。エントリーグレードの「E」を除く全グレードに有償オプションとして設定されるカラーとなっています。白系は定番色となっており、流行に左右されないため人気の高さは安定します。 アティチュードブラックマイカ 次に人気のカラーはアティチュードブラックマイカです。黒は高級感を与える色として人気があり、特に男性に支持されています。白系同様にトレンドに左右されることがない定番色ということも強みの一つです。 シルバーメタリック 3番目に人気のカラーはシルバーメタリックです。こちらも定番色ですが、白や黒と比較するとやや地味な印象になりますが、汚れや傷が目立ちにくいというメリットがあります。そのため「迷ったらシルバーメタリックを選ぶ」という方も多く、人気が高いようです。 まとめ 1997年の登場以来高い人気を誇るプリウスは、定番のグレード、カラーが人気であることがわかりました。また、中古市場ではスポーツグレード「ツーリングセレクション」の人気が高く、査定価格も期待できるようです。過走行の個体でも人気グレード・カラーであり、状態が良ければ高額査定に期待できるでしょう。 旧車王は、プリウスの買取実績も豊富で、適切に価値を鑑定することができます。プリウスの売却をご検討の際は、旧車王にご相談ください。 ※2022年11月25時点「価格.com(https://kakaku.com/)」のデータ トヨタ プリウス高価買取・査定相場

自動車譲渡証明書とは?記入の仕方や作成時の注意点についても解説
中古車の購入や買取時に必要となる自動車譲渡証明書とは、どのような書類でしょうか。業者の担当者に説明されたがよくわからないまま記入や捺印をした人も多いと聞きます。今回Fは、自動車譲渡証明書とは何か、書き方や注意点について解説します。初めて中古車を購入する方や、個人間での名義変更を検討中の方は参考にしてください。 自動車譲渡証明書とは 自動車譲渡証明書とは、中古車の売買時や個人間での名義変更(移転登録)に必要な書類です。一般的に馴染みのない書類のため、書類の入手や記入方法がわからない方も多いでしょう。自動車譲渡証明書は、新旧の所有者間で車を譲渡した証明として移転登録に必須の書類です。様式が定められており、規定通りに記入や捺印をする必要があります。 自動車譲渡証明書の書き方 自動車譲渡証明書の書き方は、ルールに基づいて記入方法が定められています。間違った記入をすると訂正が必要となるため、記載例を参考にして正しく記入しなければなりません。記載例については国土交通省のサイトでダウンロードするか、中古車販売店から取得するようにしましょう。 1.国土交通省のサイトからひな形をダウンロード 自動車譲渡証明書は、国土交通省のサイトからひな型をダウンロードすることが可能です。F印刷時に拡大や縮小などは行わずにA4サイズで印刷すれば問題ありません。また、中古車販売店などの業者を利用する場合は用意してくれることが多いので、そちらを利用するようにしましょう。 2.必要事項を記入する 自動車譲渡証明書は、大きく分けて車両と譲渡譲受人の情報欄に分かれています。それぞれに必要事項を記入して譲渡人の捺印が必要です。各項目の詳細は下記を参照ください。 【車両情報欄】車名、型式、車台番号、原動機の型式を記載します。いずれも車検証に記載されている内容を転記しましょう。※車名は車検証記載の通りメーカー名の記入だけで問題ありません 【譲渡譲受人情報欄】・譲渡年月日........2段目に譲渡の事実があった日付を記入(1段目は譲渡人欄のため斜線)・譲渡譲受人の個人情報........1段目に譲渡人、2段目に譲受人のそれぞれの氏名と住所を記入※実印の押印が必要な書類のため、印鑑登録証明書記載の氏名住所を転記する・譲渡印........譲渡人の実印を押印(譲受人の押印は不要) 記入に関してはボールペンの使用が望ましく、文字を消すことのできるフリクションインキの使用は認められていません。 自動車譲渡証明書の誤字・脱字への対応方法 自動車譲渡証明書の誤字・脱字については、譲渡人の実印による訂正印が必要になることがあります。多くの場合はあらかじめ捨印を押しておくことで対応が可能です。しかし、捨印には法的効力はなく、軽微な記入ミスにしか対応してもらえません。車両情報欄など、重要箇所の誤字や脱字については訂正印が必要となるため注意が必要です。 ※捨印とは、軽微な誤りに備えてあらかじめ訂正印として文章の余白部分に押印するものです。 委任状が必要な場合もある 譲渡人と譲受人がそろって移転登録手続きに出向く以外では、自動車譲渡証明書と委任状はセットとして必要です。また、多くの場合は中古車販売店や行政書士などの代行業者に依頼するため、こちらも同様に委任状が必要となります。委任状も様式が定められているため国土交通省のサイトからダウンロードするか、中古車販売店や代行業者が用意したものを使いましょう。 未成年の場合は同意書も必要 車の売買や譲渡について未成年者が関わる場合は、親権者の同意書が必要です。親権者同意欄には親権者の実印を押す項目があり、印鑑登録証明書及び未成年者との関係性を証明するための戸籍謄本も必要となります。また、委任状の様式も定められているため、こちらも国土交通省のサイトからダウンロードするか、中古車販売店や代行業者が用意したものを使いましょう。 譲渡証明書以外の必要書類 中古車の名義変更(移転登録)で譲渡証明書以外に必要となる書類は、車検証や申請書などです。詳細は下記を参照ください。 ・車検証・申請書........運輸支局の窓口か国土交通省のサイトからダウンロードして入手・手数料納付書(検査登録印紙)........運輸支局で入手と印紙の購入が可能・譲渡人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)・譲渡人の実印(譲渡人が手続きする場合)・譲受人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)・譲受人の実印(譲受人が手続きする場合)・委任状(手続きする人によって記入方法が異なる)・ナンバープレート 記入の仕方や手続き方法などについては、国土交通省のホームページをご覧ください。

S15シルビアと86/BRZで買うならどっち?FRスポーツカーを比較
日産S15シルビアとトヨタ86(ZN6)/スバルBRZ(ZC6)は、扱いやすいコンパクトなボディと素直な旋回特性を持つFRという共通した特性をもっています。どちらも既に新車として販売されておらず、購入するなら中古車となりますが、購入後に後悔しないためにはそれぞれの特徴を理解し予算をしっかりと見定めなければなりません。今回はそんなS15シルビアと86/BRZの魅力と、中古車市場について紹介します。 日産S15シルビア【1999年~2002年】 日産シルビアは、誰でも手軽にスポーツドライビングが楽しめるスポーツクーペとして誕生しました。5代目であるS13シルビアでは、軟派なデートカーから硬派な走り屋ご用達車両としての地位を確立し、日本の走りや文化を象徴するモデルとなっていきます。 まずは、シリーズの最終モデルであるS15シルビアについて、その概要と中古車相場について紹介します。 ターボ仕様S15シルビアスペックR S15シルビアのグレードは、NAのスペックSとターボ仕様であるスペックRの2グレードです。2Lターボエンジンを搭載する仕様のスペックRは、6速MTで最高出力250psを発揮し、シリーズ最高の性能を誇ります。また、4速ATでも225psとなっており、スポーツカーとしては十分な性能を持っています。 2022年11月の中古車相場は、6速MT仕様で160万円から800万円前後。走行距離が少なく、修復歴の無い程度が良い車両は価格が高くなっていますが、20万kmを超える個体は200万円前後でも十分に入手可能で、ATターボ仕様は230万円から300万円で推移しています。 S15シルビアスペックS S15シルビアのスペックSは、2LのNAエンジンを搭載するグレードです。最高出力は165psですが、1230kgの軽量なボディと相まって十分な動力性能をもっています。エンジン出力は控え目ながら、トルクフルなエンジン特性で誰でも扱いやすいグレードです。 中古車相場は5速マニュアルで140万円から430万円、ATで80万円から300万円程度です。ターボ仕様のスペックRと比べるとやはり手を出しやすい価格で、ATなら修復歴なし、10万km以下の個体が200万円以下で購入できます。 トヨタ86(ZN6)/スバルBRZ(ZC6)【2012年~2021年】 トヨタ86とスバルBRZは、トヨタとスバルが共同開発したことで大きな話題となりました。比較的新しい車ではあるものの、中古車としては入手しやすい価格です。入手しやすい理由と、旧型となっても魅力的な初代トヨタ86とスバルBRZを紹介します。 新型の発売により初代86の中古車が増加 トヨタ86/スバルBRZの中古車が比較的安い理由は、2021年10月に2代目が発売されたことです。エンジンが2.4Lとなったことで、パフォーマンスが大幅に向上。新型に乗り換えたユーザーも多く、2022年11月現在、初代トヨタ86/スバルBRZは多くの台数が中古車市場に流通しています。 2011年11月現在で大手中古車情報サイトに掲載されている台数は、86が約1,500台、BRZは約450台。中古車価格は6速MTが100万円から500万円で、ATは80万円から300万円です。「スポーツカー=MT車」というある種の固定概念が崩れつつある世相を反映し、AT比率が高めないことも特徴といえます。 新しい車両が多く維持がしやすい トヨタ86/スバルBRZは2021年まで新車が発売されており、トラブルが少ない車種といわれています。 エンジン出力は200psとターボのS15シルビアに比べると控え目で、手荒に扱われた車両も少なく、程度の良い車両が多くなっています。また、補修部品は生産終了から約10年は提供されており、末永く付き合えるクルマです。 唯一無二の2L水平対向エンジンとFRの組み合わせ トヨタ86/8スバルBRZは、いずれも2Lの水平対向エンジン FA20型を搭載しています。 全高の低い水平対向エンジンならではの「超低重心パッケージ」で、軽快で優れたハンドリング性能を持っており、誰でも運転の楽しさを味わうことができる1台です。 FRレイアウトと水平対向エンジンの組み合わせは、世界中どこを見渡しても86とBRZしかありません。この唯一無二の組み合わせが、初代トヨタ86/スバルBRZの魅力が色褪せない理由です。 中古車で買うならS15シルビアとトヨタ86/スバルBRZどちらを選ぶべきか FRのスポーツクーペとして、魅力的なS15シルビアとトヨタ86/スバルBRZですが、発売された年式やキャラクターによって、大きな違いがあります。 ここからは、中古車として購入を検討した場合、どんな違いがあるのかについて紹介していきましょう。 アメリカの25年ルールのあおりを受けてS15シルビアの中古車相場も上昇 R32スカイラインGT-Rや80スープラ、RX-7など、80年代後半から90年代に発売された国産スポーツクーペは、異常ともいえる高騰を見せています。その主な要因として挙げられるのが、アメリカの25年ルールです。アメリカでは右ハンドル車の販売が認められていませんが、発売から25年経ったクルマは、クラシックカーとして例外的な販売、使用が可能です。 2022年現在、1999年に発売されたS15シルビアは、まだ直接25年ルールの影響を受けてはいません。しかし、S13やS14の高騰を受ける形で、S15シルビアの中古車相場も上昇傾向にあります。 トヨタ86とスバルBRZに比べ、ターボエンジンを搭載するS15シルビアの方が動力性能という点では格上です。しかし、仮に300万円で程度の良いS15シルビアを手に入れても、経年劣化に起因する整備費用を覚悟しなければなりません。 もちろん、最新の車種にはないスタイリングやユーザーの好みでカスタムする余地が残っているなど、S15シルビアにしかない魅力があります。時間を掛けて程度の良い個体を探し、購入後もしっかりとメンテナンスするのであれば、購入後に後悔することはないでしょう。 トヨタ86/スバルBRZなら車両代+100万円で十分にカスタム可能 初代トヨタ86とスバルBRZは年式が新しく、経年劣化による故障の心配は低く安心して維持、保有できます。もちろん、絶対的な動力性能ではS15シルビアに敵いませんが、逆にいえばチューニングによって求める性能にカスタムすることが可能です。 例を挙げると、マフラーやエアクリーナー、ECUを交換すると、実際の最高出力以上の気持ち良さが比較的安価で手に入ります。そして、S15シルビアのターボモデル並みの馬力を手に入れたい場合は、チューニングメーカー各車から市販されているボルトオンターボキットやスーパーチャージャーがおすすめです。 選ぶキットや求める出力により費用は異なりますが、もっとも手軽な物であれば、50~60万円程度で230~250psを狙えます。さらに、サスペンションや駆動系に手を加えれば、クルマ全体をリフレッシュできるでしょう。トータル100万円程度のカスタム費用を見ておけば、S15シルビアにも引けを取らない1台を仕上げることも不可能ではありません。 まとめ 電動化や自動運転など、世間の潮流は環境性能と安全性を重視しており、運転の楽しさを求めたスポーツカーはやや影の薄い存在となっています。中にはスポーツ性能を重視した車種も販売されていますが、超高額高性能なスーパーカーばかりです。S15シルビアやトヨタ86/スバルBRZのように、手軽な新車として購入できる国産FRスポーツカーは多くありません。 S15シルビアは、程度の良い個体が少なく修理やメンテナンスの費用が掛かるものの、走り屋文化を象徴する雰囲気とカスタムが楽しめます。対して、トヨタ86とスバルBRZは、動力性能で劣るものの、購入と整備費用を抑え、その費用をカスタムに回せば同等の性能を手に入れることも可能です。 往年の雰囲気と動力性能を重視してS15シルビアを選ぶか、維持保有のしやすさを重視してトヨタ86やスバルBRZを選ぶか。どちらもスポーツカーの楽しさと雰囲気を十分味わえる魅力的なモデルなため、予算とメンテナンス環境を勘案し選びましょう。

外車の中古車購入は正しい知識がないと難しい!デメリットを理解しよう
「憧れの外車が欲しくても新車では高くてなかなか手が出せない……。でも中古車だと手の届きやすい価格になっており検討できそう」このような方も多いのではないでしょうか。しかし外車の中古車は国産車と比較して故障などのトラブルが多いというイメージがつきまといます。実際のところどうなのでしょうか。この記事では中古車購入のデメリットについて解説します。 外車の中古車でよくあるトラブル3選 ここからは外車の中古車を購入する際によくあるトラブル事例を3つ紹介します。 故障した際の修理費が高額になる まず、修理費が国産車と比較し高くなります。ほとんどの国産車は多くの修理・整備工場に入庫可能ですが、外車になると限られてしまいます。特に格安を売りにした整備工場の多くは外車の取り扱いをしていないことがあります。 なぜこのようなことが起こるのでしょうか。それは外車を扱うためには国産車とは別の専門知識が必要であったり、部品の調達コストがかさむなどの問題点があるからです。 一般的な1時間当たりの整備工賃(レバレート)は下記の通りです。国産車:7,000~10,000円外車:10,000~15,000円 外車を購入する場合は、故障した際にそれなりの修理費がかかることを覚悟しておきましょう。 ハイオクガソリン限定車が多く燃料代が高い 国産車では、スポーツカーや高級車など一部の車種を除けばレギュラーガソリンを入れられるクルマがほとんどです。しかし外車はガソリン車の場合、ほとんどがハイオク限定車です。ヤリスやフィットクラスのコンパクトカーでもハイオク限定車となっています。 また、低年式の外車は燃費が悪いものも多く存在します。2010年以前の欧州製コンパクトハッチバックを例にすると、リッター10km程度しか走らないこともざらにあります。当時の同クラスの国産車の場合、15~20kmぐらい走るものが多いです。 燃費を気にされる方は、外車の中古車購入は控えたほうがいいかもしれません。 リセールバリューが悪い メルセデス・ベンツやフェラーリ、ポルシェなど一部の外車はリセールバリューが高く、新車価格を上回ることもあります。そのため、外車はリセールバリューが良いと思っていませんか。実は一部の車種を除いて国産車よりリセールバリューが悪い傾向にあります。一般的な目安として同価格帯の国産車より2~3割程度安くなる場合が多いです。 なぜ外車はリセールバリューが低くなるのでしょうか。原因の一つとしてあげられるのは、前述した整備費用や燃費などの維持費の高さです。購入価格を抑えても数年間所有した場合、国産車よりトータルコストが高くなってしまうかもしれません。 外車の購入には、維持費やリセールバリューを気にしない強い意志と経済力が必要になるでしょう。 中古の外車を購入する際に気を付けるポイント では、中古の外車を購入する際、どのようなことに気を付けたら良いのでしょうか。ポイントを解説します。 外車専門店で購入する 中古車販売店には外車を専門に扱っているところもあります。さらには特定のメーカー専門店や名車専門店なども存在します。専門店は一般店よりも特定メーカーや車種に関する知識を有するスタッフが在籍しており、安心して任せることが可能です。 一方、一般店より販売価格が高額になる点がデメリットです。しかし目利きのスタッフが仕入れたクルマを、しっかりと整備して納車していただけるというメリットもあります。 長い目で見た際に、専門店で購入するメリットを感じられるでしょう。 ▼輸入車専門店ガレージカレント▼アメリカンヴィンテージカー専門店ガレージカレント U.S. アフターサービスを確認する 外車購入の際は、アフターサービスをしっかりと確認しましょう。修理費や整備費が国産車と比較すると高くなりますが、店舗によっては充実した保証サービスを提供しているところもあります。保証内容と保証期間は明確にすることが重要です。充実したアフターサービスを受けられるなら、リスクを軽減できるでしょう。 コスト重視の方は国産車購入をオススメ 外車を所有することは、特別感や充実感を得られる代わりに、高額なランニングコストを支払わなければなりません。一見、安いと思える中古外車も3年後、5年後には「国産車を選んでおけば良かった……」と後悔する可能性があります。強い思い入れがなく低コストでクルマを維持したい方には国産車購入をオススメします。 また、国産車は中古市場でも人気が高くなっています。10年落ちの国産車でもナビやコーナーセンサーなど標準装備されている車種が多く、不便に感じることは少ないでしょう。昔は10年落ち、10万kmオーバーのクルマは価値がなくなると言われてきましたが最近のクルマは充分元気に動きます。実用性重視の方には国産中古車の購入は間違いない選択であると言えます。 まとめ 販売価格の安い外車中古車は、正しい知識がないと購入後に後悔してしまうかもしれません。外車中古車の購入を検討する際は維持費の高さやリセールバリューの低さを覚悟しておきましょう。外車は国産車とは違う魅力があります。デメリットを理解し納得できた場合には、楽しい外車ライフがあなたを待っているでしょう。

S204 STIバージョンはなぜ高価買取が可能なのか?!突出した人気の理由に迫る
スバルのスポーツ部門を担うSTIが制作した600台限定の特別仕様車であるS204は、シリーズの中でも特に高い人気を誇っています。ベースモデルであるGDB型インプレッサと比較してもその差は歴然です。なぜこれほどまでにS204が人気なのか、歴史を紐解きながらその理由に迫ります。 Sシリーズはメーカーが作ったチューニングカー Sシリーズは、STIが送り出すコンプリートカーの最上位シリーズです。スバルのモータースポーツ部門として開発をおこなうSTIによって、レースで培ったノウハウをもとに特別仕様車として製造されています。 エンジンチューニングだけにとどまらず、新開発の足回りやブレーキ、専用デザインされた内外装と、細部にいたるまでSTIのこだわりがみられる特別なシリーズです。 Sシリーズの歴史 Sシリーズは、今でも名車として名高いインプレッサ22B STI バージョンの成功を受けて開発されました。 初代Sシリーズとしてリリースされたのは、GC8をベースとして開発されたS201。専用にチューニングされたエンジンは300psを発生、エアロバンパーや大型ウイングを装備するなど、まさにメーカーが作ったチューニングカーといった迫力のある仕様でした。 また、Sシリーズには2系統あり、インプレッサをベースとする20系とレガシィをベースにする40系にわかれます。Sシリーズ第2弾として登場したのは、レガシィベースのS401でした。 その後、モデルチェンジの節目ごとに発売されたSシリーズは、現在までに10モデルをリリースしました。内訳は、インプレッサベース6モデルとレガシィベース、WRXベースがそれぞれ2モデルです。 2代目インプレッサGDB型Sシリーズは3モデル 2代目インプレッサとなるGDB型をベースとしたSシリーズは、マイナーチェンジごとに製作され、合計3モデルがリリースされました。 インプレッサベースとして発表された6モデルのSシリーズ内、同型で複数のモデルがあるのはGDB型のみです。S202〜204の3モデルがGDB型インプレッサベースのSシリーズとして製作されました。 2000年に登場したGDB型インプレッサは2度のマイナーチェンジをおこなっていて、ヘッドライトの形状から、それぞれ「丸目」「涙目」「鷹目」という愛称がファンによってつけられました。 GDB型として製作された3台のSシリーズは、S202が「丸目」、S203が「涙目」、そしてS204が「鷹目」に対応しています。 S204の人気が高い3つの理由 GDB型インプレッサは中古車としてそれほど人気が高いわけではありません。しかし、S204に関しては多くのファンから熱い支持を得ています。販売台数600台限定と希少性が高いように感じますが、Sシリーズの多くのモデルは台数を限定して販売されています。 たとえば、S204の直前にリリースされたS203は555台限定でした。こうした背景から、流通量の少なさは「S204特有の人気の高さ」につながっていないと考えられるでしょう。 S204がなぜこれだけの支持を集めているのか、3つの観点から迫ります。 WRC参戦モデルとして最後のSシリーズだった スバルの“世界ラリー選手権”(WRC)参戦の歴史を締めくくるモデルだという点は、S204の人気に大きく影響しているでしょう。2005年に発表されたS204のベースであるGDB型インプレッサは、スバルがメーカーとしてWRCに参戦する最後の年となる2008年シーズン中盤まで使用されていました。 WRCでの活躍により、インプレッサはスポーツカーとして確固たる地位を築きました。しかし、2008年シーズン後半に3代目インプレッサのGRB型ハッチバックモデルが投入されたあと、世界経済の悪化と戦績の低迷を理由に同年のシーズンを最後にワークス活動を終了してしまいます。 WRC撤退後、ワークス活動の主軸はニュルブルクリンク24時間レースに移行。のちにハッチバックのGRB型ベースのR205や、セダンであるGVBベースのS206が登場していますが、開発目標はラリーでの勝利ではなくオンロードの快適性向上でした。 インプレッサを象徴するWRCでの活躍が影を潜め、オンロードに移行してしまった結果、S204が「スバル=ラリー」というキャラクター性を色濃く残した最後のSモデルとなります。 エンジンへのこだわりと新開発のボディと足回りを徹底的に強化 S204は前身となるS203を正統進化させたモデルです。前作のS203から特にボディと足回りに力を入れていて、ボディ強化パーツとしてヤマハと共同で新開発した“パフォーマンスダンパー”が投入されます。すでに完成の域にあったエンジンに足回りを徹底的に強化したことで、S204はクルマとしての完成度を極限まで高めたモデルになりました。 トランクルームにあるリアストラット上部に装着される“パフォーマンスダンパー”は、ボディへの入力を吸収するパーツです。ストラットタワーバーのようにボディに受ける力を跳ね返すのではなく、吸収するという発想でボディへの影響を抑えて、安定性を高めます。 また、車高を15mmダウンさせスプリングレートを50%向上した専用のローダウンスプリングと、大径化により強化されたリアスタビライザー、そしてリアサスペンション取り付け部のピロボール化と応答性のよい足回りを完成させました。さらに、軽量BBS製鍛造18インチアルミホイールも用意され、S203よりも大幅に運動性能が向上しています。 すべてにおいてワンランクアップ S204は、エンジンや足回り以外にも多くの点で進歩しています。細部にこだわってワンランク上の性能と上質さを身にまとったことも、S204が高い人気を誇る理由の1つです。 性能面では、エンジンへのこだわりとともに、タービンの大型化と専用チタンスポーツマフラーによって抜けの良いレスポンスを実現。減衰力が固定式に変更されたショックアブソーバーや径が拡大されたスタビライザーなど細部にもこだわり、発生するパワーを持て余すことなく自在にコントロールできる高い操縦性を発揮します。 内装面では、全体をグレーに統一し、随所に本革を使用するなどインテリア全体の質感を向上させました。ドライカーボンを使用したレカロ製シートは、基本的な設計は変わらないものの、本革とアルカンターラのコンビシートに変更されています。加えてサイドサポート部に本革を使用し、乗降性とともに高級感も向上しました。こだわり抜いたシートは1脚75万6000円と前作S203のシートよりも20万円も高額になっています。 また、ステアリングのグリップ部分には、フェラーリにも使われている最高級の本革を採用。フロアカーペットは高級感があり遮音性に優れた高い毛足の長いものに変更されています。 S204は、欧州高級スポーツカーをターゲットに開発されたS203の完成型ともいえるモデルです。 今も高値で取引されるS204 発売当時500万円近い高額な価格も話題となったS204ですが、発売から15年以上が経過した現在は、新車価格よりもさらに高い価格で取り引きされています。 買取相場からお伝えすると、旧車王では2022年10月に550万円でS204を買取しています。通常のGDB型の買取価格は100万円前後で推移しており、S203でさえ260万円ほどでの取り引きなので、いかにS204の人気が高いかお分かりいただけるのではないでしょうか。 販売価格に関しては、大手中古車販売サイトで2006年式のS204が約900万円で販売されていました。また、先述の通り販売台数が限定600台だったことから、現存する在庫数も豊富とは言えません。 価格の高騰だけではなく、在庫面からも今後さらに入手困難になることが予想されるため、S204が気になっている方はぜひ早めの入手をおすすめします。 ※価格は2022年11月執筆当時

今が買い!?996・997型ポルシェ911で注意したい“インタミ問題”とは?
996・997型のポルシェ911は、ポルシェの中では比較的手が出しやすいモデルだと言われています。そんな996・997型の購入を検討する中で、エンジンの故障である“インタミ問題”を気にする方も多いのではないでしょうか。ハードルが低いとは言え、ポルシェの中古車は決して安くありません。インタミ問題が怖くて、購入を躊躇している方も少なくないと思います。そこで今回の記事では、996・997型911の特徴とインタミ問題について詳しく紹介します。 996・997型ポルシェ911とは ポルシェ911は、世界中のスポーツカー好きから愛されていると言っても過言ではないほど人気のモデルです。プレミアムスポーツカーらしく中古でも簡単に購入できる価格ではありませんが、そんなポルシェ911の中でも比較的手を出しやすいと言われているのが996・997型の911です。 まずは、996・997型それぞれどんな特徴があるのか紹介します。 初の水冷エンジンを搭載した996型(1998~2004) 996型のもっとも大きな特徴は、水冷化されたエンジンです。 初代の901型が登場した1964年から、911には一貫して空冷式の水平対向6気筒エンジンが搭載されてきました。しかし、排気ガスや騒音の規制に対応するため、1997年に登場する996型から水冷式に変更されます。 もう一つ大きな変化と言えるのが、衝突安全のために拡大されたボディサイズです。それまで「ポルシェを着る」と表現されていたタイトな内装から一転、ボディサイズの拡大に伴って車内空間にも余裕が生まれました。 これらの変更点はコアなポルシェファンにとって歓迎できるものではありませんでしたが、水冷化でオーバーヒートの心配が軽減し、室内が広くなったことで日常の使い勝手は向上しました。その結果、あまり911に興味を示さなかった新たなファン層の獲得に繋がったのです。 現代のスポーツカーへ進化する997型 996型のあとを受け、2004年に997型がデビューします。996型では不評だった涙目型のヘッドライトを廃止し、911伝統の丸型に変更されました。しかし、骨格やエンジンの基本設計は996型を継承しており、実質的な変化はそれほど大きくありません。997型が大きな進化を遂げたのは、2008年のマイナーチェンジのときです。 まず、996型で採用されたティプトロニックSを廃止し、いわゆるツインクラッチを持つPDK(ポルシェ・ドッペル・クップルング)に変更されました。さらにNAモデルには新開発された直噴エンジンを搭載し、カレラの最高出力は325馬力から345馬力に向上しています。 最後の空冷式エンジンを搭載する993型911まで、どちらかと言えばハードで玄人向けのスポーツカーと思われてきました。しかし、996型で伝統の空冷式エンジンに別れを告げ、997型で今では当たり前のツインクラッチ式PDKを採用することで、誰でも乗れるスポーツカーへと進化したのです。 996・997型911の“インタミ問題”とは 高額な値段で取引されるポルシェの中でも、996型と997型の911は比較的手が出しやすい価格で推移しています。しかし、安いからには“それなりの理由”があるもの。その最たる理由として挙げられるのが、“インタミ問題”です。 インタミとはインターミディエイトシャフトの略で、クランクシャフトの下部に位置するエンジン内部の部品です。911に搭載されている水平対向6気筒エンジンは、左右3気筒ずつシリンダーヘッドが分かれており、インターミディエイトシャフトとチェーンを使って、クランクシャフトの回転を左右バンクにあるカムシャフトに伝えています。 エンジンの仕組み上、クランクシャフトとカムシャフトは必ず決められた位置関係になければなりません。その為、緩みがないよう、チェーンにはかなりの張力が掛っています。真の問題はインターミディエイトシャフトそのものがダメなのではなく、支えているベアリングの強度不足です。このシャフトを支えるベアリングが破損すると、最悪カムシャフトとクランクシャフトの位置がずれ、吸排気バルブとピストンがぶつかり、エンジンが壊れてしまいます。 つまり、インターミディエイトシャフトがあるからダメなのではなく、強度不足のベアリングがダメというのがインタミ問題です。 万が一壊れてしまった場合、最悪エンジン本体が壊れてしまう可能性があり、修理費は高額になります。そうなれば当然買うことを躊躇してしまいますが、実はそれほど心配する必要はありません。 中古車で996・997型ポルシェ911を探すなら年式に注意 インタミ問題が関係しているのは、2002年~2004年の996型後期と2004年から2008年までの997型前期のみです。しかも、NAのカレラだけであり、ターボやGT2、GT3は該当しません。 もちろん、997型でもっとも高年式を狙ったとしても10年以上前の中古車であるため、年式相応の故障リスクはあります。しかし、996型なら前期、997型なら後期から選べばインタミ問題を気にする必要がありません。 また、上記の問題に該当する車両は、ポルシェジャパンによるサービスキャンペーンの対象です。並行輸入車ではなく正規ディーラー車であれば、対策済みの部品に交換されているため心配はいりません。 中古車を購入する場合は、正規ディーラー車でサービスキャンペーンを実施しているか確認しましょう。万が一対策されていなくとも、購入後正規ディーラーで対応してくれます。 リスクを許容できるなら購入を検討すべし 筆者をはじめ、多くのクルマ好き、スポーツカー好きにとってポルシェ911は特別な一台です。「いつかはポルシェ!」と思っている方も少なくないと思います。 996型の中古車相場は、大手中古車販売サイトで420万円前後。997型は同じサイトで670万円前後で掲載されています。最後の空冷式である993型が1100万円前後、新しい世代の991型が1500万円前後であることを考えると、高いとは言え手が出しやすい価格です。 「最新のポルシェは最良のポルシェ」と言われるものの、どんなに古くてもその乗り味やエンジンフィールはポルシェです。もちろん年式としては古いため、輸入車の中では壊れ難いと言われるポルシェであっても消耗品の交換とこまめなメンテナンスは欠かせません。 今回紹介したインタミ問題を良く調べ、古いクルマであるという一定のリスクを許容できるのであれば、996・997型911は十分購入を検討する価値があるポルシェです。
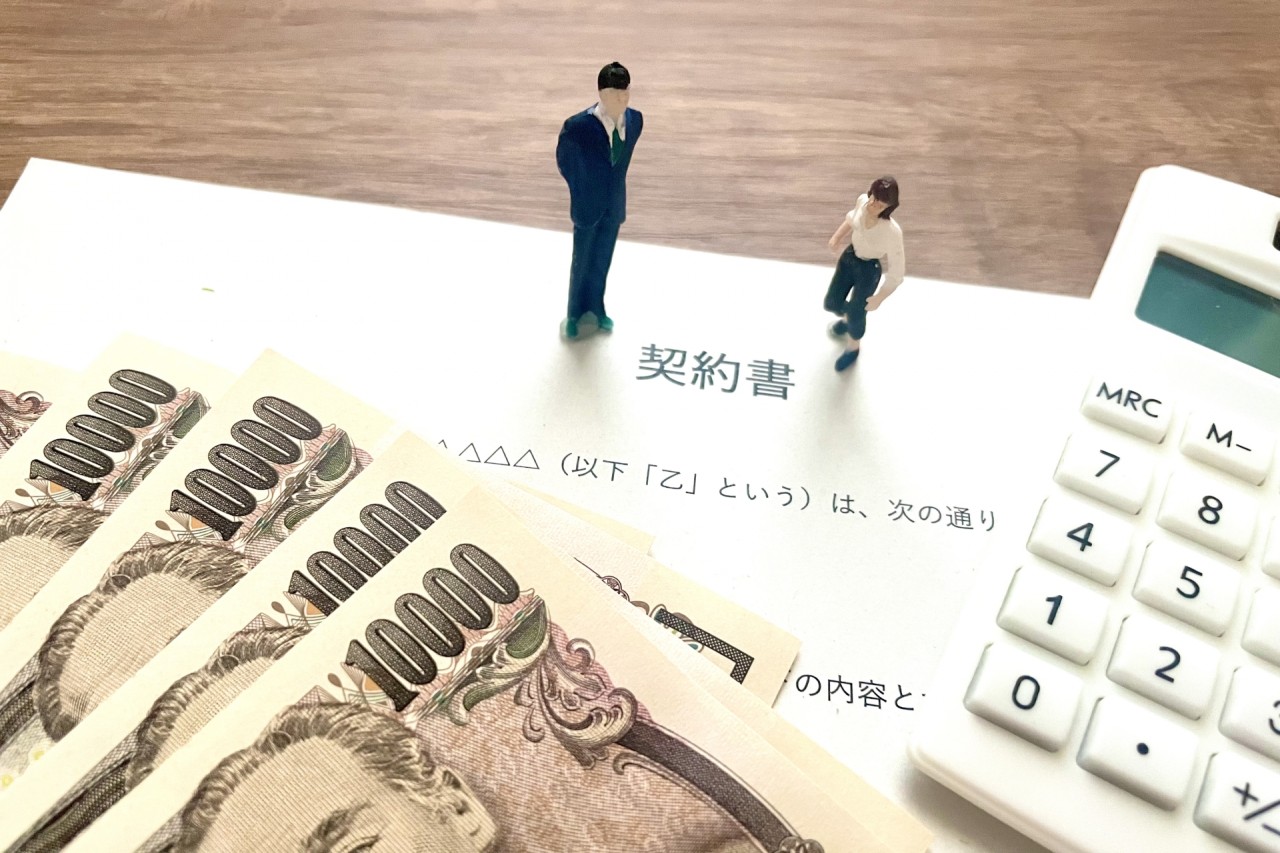
自動車の売買時に契約書が必要な理由は?必要性や記載される項目などを解説
車の売買をするときは、契約書を作成した方がよいといわれています。なぜ、売買契約書が必要なのでしょうか。今回は、車の売買で契約書が必要な理由、記載事項、注意点について解説します。売買契約書の作成を検討している方、必要性が気になっている方は参考にしてください。 自動車売買契約書とは 自動車売買契約書とは、車の売買取引に合意したことを証明する書類です。売主と買主の間で売買の条件や内容を確認し、合意した上で署名や捺印をします。車の売買契約は、取引金額が高く、名義変更に関するトラブルも発生しやすいため、必ず契約書を作成しましょう。 自動車売買契約書の必要性 自動車売買契約書が必要な理由は、トラブルを防ぐためです。 車の売買では、故障や不具合といった車両のトラブル、名義変更や納税など法的な手続きも必要です。金銭的なトラブルや法的な手続きなどで揉めないためにも、契約書を必ず交わしましょう。 自動車売買契約書で定める内容 ここからは、自動車売買契約書で定める内容について紹介します。ここで紹介している契約書記載事項は、あくまでも必要最低限の内容です。場合によっては、項目を付け足してください。 売買契約であることを示す文章 自動車の売買契約であることを示す表題や文章が必要です。 書類の表題に「自動車売買契約書」と記載し、表題の下に「売主 ◯◯◯◯(以下「甲」という。)と 、買主 ◯◯◯◯(以下「乙」という。)は、甲乙間の売買契約に関して、以下のとおり合意した。」という文章を加えます。 この表題と文章があることで、自動車の売買契約書であること、売主と買主がそれぞれ誰なのかということが明確になります。 対象となる車両 対象となる車両に関する内容は、なるべく細かく記載しましょう。 必要となる主な項目は「登録番号」、「車名」、「型式」、「年式」、「車体番号」です。 これらの情報がなければ、どの車が売買対象なのか特定するのが難しいため、必ず記載しましょう。 売買代金の額 売買代金の金額は、「金◯◯◯万円(税込)」と記載しましょう。「金」と「万円」で金額の数字を挟むことで、改ざんを防ぐことができます。また、消費税が発生する場合には「(税込)」表記もしておきましょう。 この売買金額とともに、支払期日と振込先を明記しておくことも重要です。いつまでに、どのような方法で支払いをするのか決めておかなければ、代金の支払いがされなくなってしまいます。 引き渡し条件・日程 車両の引き渡し条件は、さまざまなケースが考えられます。 例えば、「契約日に手付金◯◯万円を支払い、引き換えに車両を引き渡す」や「◯年◯月◯日に現金◯◯万円を甲に持参し、支払いと引き換えに車両を引き渡す」などです。 いずれも、日付や支払方法を明記することがポイントとなります。 所有権を移転する時期 所有権を移転する時期についても契約書に明記しましょう。 例えば、「◯年◯月◯日までに所有権を移転する」や「契約日から◯日以内に所有権の移転をする」というように、いつまでに所有権の移転を完了させるのか明記しておくと、トラブルを防止できます。 名義変更の手続きの取り決め 名義変更の手続きを誰がいつまでに行うのか明記しましょう。 また、「車両引き渡し時に取扱説明書・車検証・名義変更必要書類を交付する」というように、必要書類をどのタイミングでどの書類を渡すのかということも契約書に記載しておくことがポイントです。 さらに、「乙は、◯◯年度分の自動車税について、◯年◯月◯日以降の月割相当額を負担する」という自動車税の負担、「名義変更に要する費用は乙の負担とする」という名義変更に関する費用の負担についても契約書に明記しましょう。 危険負担に関する条項 危険負担は、車が盗難に遭ったり壊れたりした場合の責任の所在を取り決める項目です。 「本契約締結日から車両引き渡し日までに、滅失または毀損した場合は甲の負担とする」というように、どのタイミングまで甲の負担で、いつから乙の負担になるのか明記しましょう。 瑕疵担保責任に関する条項 瑕疵担保責任は、修復歴や故障などを隠して売却した場合に売主が負うべき責任です。 契約書には「引渡し時に本契約書の車両であることや装備・外観等の状態について確認を行い、甲が瑕疵担保責任を負わないことを確認する」という内容を記載しておきましょう。 瑕疵担保責任については、買取業者との取引でも発生するトラブルです。そのため、この項目は必ず入れましょう。 契約解除の条件 契約の解除についての条件も契約書に記載しましょう。 「相手方が本契約の義務の履行を怠った場合、本契約を解除することができる。解除権者は、相手方に対し契約解除によって生じた損害の賠償を請求することができる」といった内容を入れておくことで、取引をスムーズに進めることができます。 合意管轄に関する条項 合意管轄についても契約書に記載しましょう。 契約書には「本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、◯◯地方裁判所を専属管轄裁判所とする」というように記載します。 トラブルなく契約内容を遂行するのがベストですが、何らかのトラブルにより裁判が必要になった場合、どこの地方裁判所で第一審を行うのか揉めないために契約書に合意管轄を盛り込みましょう。 自動車売買契約書の注意点 ここからは、自動車売買契約書を作成するときや合意して署名するときの注意点を解説します。 口約束の内容は全て契約書に記載する 契約書には、口約束した内容も全て記載しましょう。 口約束も契約のひとつとは言われるものの、忘れてしまったり、言った言わないの水掛け論になったりすることがあります。 そのため、口頭で約束した内容も契約書に明記しておくことが重要です。 代理人がサインする場合は委任状が必要 代理人が売買契約書にサインする場合には、委任状が必要となります。 委任状とは、本人が代理人を選任して手続きを行うという意思表示を書面に書き記した文書です。本人が契約書にサインできない場合には、代理人を選任して委任状を作成しましょう。 未成年の場合は保護者の同意が必要 未成年が売買契約をする場合には、保護者の同意が必要です。そのため、未成年が売買契約をする場合には、同意書も作成しましょう。

10年後「旧車屋」となったZ32専門店の未来予想図とは?
今から25年前の1997年、平成9年に中古車販売店の営業の仕事をスタートした筆者。 雇われ店長として70スープラ専門店、Z32専門店と快進撃を続けるも、まさかの会社消失。 急遽、独立することに。スタートから様々な壁にぶちあたりながらも、Z32一本の専門店をやっていくことを決意。 その後、スポーツカー低迷とZ32が旧車になっていく場面に直面しながら徐々に旧車屋に転換。 今やレストアを行うまでに。 Z32はここからさらに旧車になっていくが、現状の課題や期待から、10年後の当店の未来を予想してみた。 実際は、まったく予想がつかないのというが本音ではあるけれど…。 お客様の高齢化が進み、Z-oneの店舗は憩いの場に!? お客様の平均年齢は年々高齢化し、60代の方が増えるでしょう。 話す内容は、親御さんの介護、自身の老後や健康、お孫さんのことで持ち切り。 皆さんの憩いの場になっていると思われます。 国内Z32の聖地として海外でも話題に! 国内Z32聖地として確固たる地位を確立! Z32を日本一大事にするお店として、海外からも注目されるショップになるでしょう。 海外も視野に入れた業務展開も始めているかもしれません。 中古純正部品や部品取り車のストックは日本一に! 純正部品の製廃が進み、全国的に修理難民の方が増えていくでしょう。 修理をするために、純正部品は必須です。中古純正部品や部品取り車のストック数は日本一となり、どんな修理も対応していると思われます。 自社部品製作も積極的に 修理には中古で対応できるものもありますが、どうしても新品を使いたいこともあります。 そのため、自社での部品製作も積極的に行う必要があります。 多種多様な部品のラインナップが増えていると思われます。 整備同時進行可能な巨大工場に! 今後、さらに旧車化が進み、修理内容は多岐に渡るでしょう。 長期修理も増えます。 そのためには、整備場所の確保が必須です。 巨大工場で効率的に整備を同時進行させていると思われます。 理想はエアコン完備。 自社板金工場完備に! 外装の劣化に伴い、オールペンも増えるでしょう。 綺麗に乗りたいニーズはいつでもあります。 外注を使わず自社板金工場を完備し、一貫した整備・作業を行っていると思われます。 販売車輛のほとんどがレストア車に! 10年後となれば40年落ちの車もあるわけです。 最終型でも30年落ちに。 販売する車輛は、ベースから仕上げて売るしかないでしょう。 ほとんどがレストア車になっていると思われます、一体いくらで売ることになるのだろう? 出張査定・買取り全国に! さまざまな事情により売却される方も増えるでしょう。 大事に乗ってきたからこそ「近くの買取店よりも専門店に売りたい」と、全国から査定・買取の依頼は増えます。 北は北海道から、南は沖縄まで出向いていると思われます。 スタッフは10人に! 業務も多様化し、分担制が必要になるでしょう。 さまざまなご相談やご要望に対応すべく、フロント・整備・板金塗装・部品管理・出張買取り…。 それぞれに精通したスタッフが最低でも10人はいると思われます。 最終目標のショップさんは! 未来を予想すると、既にそれに近いショップさんがあります。 R31 HOUSEさん、カーショップフレンドさん、アイスタイリングさん、エム・テック・サージョンさん、チューブガレージさん、イソマサオートさんなど。 ほぼ一車種の専門店さんです。 その領域に達するにはまだまだですが、必ず頑張ってみせます。 私はいつまでも現役です! 未来の私は容易に想像がつきます。 今と変わらず、整備以外のことをやっているでしょう。 接客応対、電話・メール応対、出張買取り、ご納車前の洗車、店舗の掃除や草取りの雑用など。 もちろん、季節を感じながらの早朝ドライブ&写真撮影は日課です。 Z32に人生を捧げ、年中無休で働いていると思われます(笑)。 これまでのエピソード お調子者営業マンだった私が、Z32専門店を立ち上げるまでhttps://www.qsha-oh.com/historia/article/z32-omura-vol1/ お調子者営業マンだった私が、Z32専門店を立ち上げるまで[エピソード2]https://www.qsha-oh.com/historia/article/z32-omura-vol2/ お調子者営業マンだった私が、Z32専門店を立ち上げるまで[エピソード3]https://www.qsha-oh.com/historia/article/z32-omura-vol3/ [ライター・撮影/小村英樹(Zone代表)]

旧車を象徴するマストアイテム!国産車におけるフェンダーミラーの歴史とメリット・デメリット
セダンやクーペなどと相性が良く、どこかノスタルジックな雰囲気を醸し出すフェンダーミラーは旧車ならではの特徴です。今回は旧車を語る上で欠かせないフェンダーミラーの歴史と、そのメリット・デメリットについて紹介します。 日本におけるフェンダーミラーの歴史 今ではほとんどのクルマがドアミラーを採用しており、もはや当たり前の仕様となりつつあります。しかし、かつて日本にはフェンダーミラー装着車しかなく、法律によってドアミラーは禁止されていました。 ここからは、フェンダーミラーが日本で義務化された歴史や、今再び注目されるようになった背景を紹介します。 フェンダーミラーがいつから登場した? フェンダーミラーが登場したのは、1950年代のイギリスです。それまでフロントガラス(風防)に取り付けられていたクルマはありましたが、屋根やドアが当たり前の装備になったことで車内ではなく車外に取り付けられるようになりました。 ただ、1940年代~50年代の日本では、後写鏡の装着が義務付けられていたものの数や位置についての規定はなく、トヨタ初代クラウン(1955年登場)やスバル360(1958年登場)など、フェンダーミラーもドアミラーも付いていない車種が多く販売されていました。 その後1962年には、すべてのクルマに左右のサイドミラーが義務付けられるようになり、日本では左右のフェンダーにサイドミラーを備えた光景が当たり前になったのです。 日本ではドアミラーが禁止されていた 欧米では1950年代からドアミラーを搭載した車種が登場していましたが、日本では1983年まで認められていませんでした。そのため、海外の自動車メーカーは日本向けにフェンダーミラーを新規に開発しなければならず、非関税障壁だと多くの批判を受けました。 安全性という観点で日本では許可できない状態にあったものの、デザイン性に優れたドアミラーが世界的に主流になっていきます。 結果的に外部からの圧力によってドアミラーは解禁され、1983年に発売された日産パルサーエクサがドアミラーを初採用。古臭いイメージを持たれていたフェンダーミラーは急速に人気を失い、一気にドアミラーが普及しました。 フェンダーミラーは日本の旧車を象徴するアイテム 現在では古臭いイメージで敬遠されがちなフェンダーミラーですが、海外の日本車好きや旧車好きにとって憧れの存在です。 ハコスカの愛称で知られる日産 スカイライン 2ドア ハードトップ 2000 GT-R(KPGC10型)や初代フェアレディZ(S30型)もフェンダーミラーを採用しています。(北米仕様のフェアレディZはドアミラーを採用)当時はフェンダーミラーであることが当たり前だったため、現代のクルマのような“デザイン的に似合わない”ということはありません。 旧車を彷彿とさせるデザインを復刻したような新型車も登場していますが、当然ながらドアミラーが採用されています。フェンダーミラーは、自動車史に残る名車を象徴するアイテムなのです。 フェンダーミラーのメリットとデメリット 法律で厳しく規制してまで、なぜ日本車が長らくフェンダーミラーを採用していたのか?ここではフェンダーミラーのメリット・デメリットをご紹介します。 フェンダーミラーのメリット フェンダーミラーの一番のメリットは、視線の移動が少ないことです。運転席よりも前方にミラーがあるため、少ない視線移動でミラーを見ることができることに加え、ドアミラーよりも広い後方視界を確保することができます。 さらに、雨天時もフェンダーミラーが力を発揮するシチュエーションです。前述したとおり、フェンダーミラーは運転席よりも前方、フロントガラスから見える範囲に設置されています。雨が降った際にワイパーがフロントガラスの雨粒をふき取ってくれるので、しっかりとミラーを視認できますドアミラーだとサイドウィンドウが雨粒で覆われてしまうと見にくくなってしまうため、この点はフェンダーミラーならではの強みです。 また、フェンダーミラーには車幅も抑えるという役割もあり、日本の狭い道でも容易に取り回しできます。フェンダーミラーは、安全性と日本の道路事情にマッチした合理的な装備と言えるでしょう。 フェンダーミラーのデメリット 一方フェンダーミラーのデメリットとして挙げられるのは、やはり現代のクルマに似合わない点です。 フェンダーミラーはボンネットが長く広い車種に合うものの、現在主流のボンネットが短く狭いミニバンやコンパクトカーには合いません。ボンネットの面積が広ければ大きなフェンダーミラーも映えますが、小さなスペースに大きな突起物が鎮座することとなり、車両前方のデザインを損なってしまいます。 また、ボンネットについた突起物だと考えると、万が一人身事故が発生した場合、フェンダーミラーが原因で歩行者への被害が大きくなってしまう可能性があります。 なぜタクシーはフェンダーミラーを採用しているのか 現在のクルマに似合わないフェンダーミラーですが、新車では唯一トヨタのJPNタクシーだけがフェンダーミラーを採用しています。そこには、タクシーならではの事情と日本人らしい国民性が大きく関係していました。 ここからは、タクシーがフェンダーミラーを採用している理由について紹介します。 日本人らしいおもてなしの心 ドアミラーで後方を確認する際、どうしても助手席側に視線を動かす必要があります。運転手が後席や助手席の乗客をチラチラ確認しているように見えるため、人によっては不快に感じるかもしれません。 フェンダーミラーであれば視線の移動が少ないため、乗客はよりリラックスして乗ることができ、日本人らしい「おもてなしの心」を表現しています。 また、人々の足としてさまざまな道を走行することがあるタクシーは、狭い路地に入っていかなければなりません。フェンダーミラーは車外への飛び出しが小さいことに加え、車幅感覚が掴みやすく、どんな道でも安全に走ることを求められるタクシーに適しているのです。 JPNタクシー専用開発のフェンダーミラー 2022年6月に国際自動車グループ会社のKmGオートアシストが、JPNタクシー用に視認性を高めるフェンダーミラーを開発し、実証実験を開始したと発表しました。 2017年10月の発売から4年以上経過しているにも関わらず、タクシー専用のフェンダーミラーが開発されることは異例です。タクシーにとって、いかにフェンダーミラーが大切な存在なのかがわかります。 まとめ 古臭く野暮ったいイメージを持たれやすいものの、フェンダーミラーは旧車好きにとってノスタルジーな雰囲気を醸し出す、なくてはならないアイテムです。また、運転にやや慣れは必要ですが、前方にあることで視線の移動が少なく、映し出す範囲が広い後方視野で安全を確保できます。 クルマを取り巻く技術が日々進化する中で、今ではミラーが小型カメラに置き換わりつつあります。 クルマにはどんなミラーが装着されているのかを見れば、その時のトレンドと時代背景が見えてくるかもしれません。

78プラドは価格高騰&値上がりしている?旧車買取専門店が相場推移を解説
78プラドは、トヨタの本格派オフロード車であるランドクルーザーに、初めてプラドというサブネームが与えられたモデルです。この78プラドの中古価格は、現在どのようになっているのでしょうか。今回は、78プラドの特徴や価格状況から、より高く売るためのポイントまで詳しく解説します。 78プラドとは 78プラドは、1990年から1996年までトヨタ自動車が製造したオフロード車です。以前は、ランドクルーザーの名前で世界の多くの国々で販売されていました。ランドクルーザーは補修が必要になる部品をあえて新規設計しないため、世界中どこでも修理しやすいという特徴があります。 プラドが誕生した1990年初頭の日本は、まさにRVブームでした。RVは「Recreational Vehicle」の略で、趣味やレジャーを楽しむために開発されたクルマです。天井にはルーフレール、正面には巨大な通称“カンガルーバンパー”とフォグランプ、背中にスペアタイヤを背負ったスタイルが特徴的でした。当時は三菱のRV車が人気で、ラインナップの頂点に君臨したのがパジェロです。 そんな人気のパジェロに対抗すべく、ランドクルーザーのイメージ一新を担ったのが78プラドでした。ランドクルーザーでも従来の70系バンから、乗用車としても使いやすい4ドア・セミロング車として登場しました。パワートレインは電子制御化した2.4L直列4気筒OHCディーゼルターボに、4速オートマチック・トランスミッションが組み合わされました。 1993年5月にマイナーチェンし、エンジンは3リッター直列4気筒OHCディーゼルターボへと変更されています。エンジンの変更により高出力化と環境性能の向上が図られました。 78プラドの価格は高騰している? 78プラドの価格は、新型コロナウィルスの蔓延により一時期値下がりしたものの、2024年3月頃から上昇傾向にあります(※2024年9月時点)。これは、SUV人気の高まりや中古車市場の需要増加が影響しているものと考えられます。 また、メーカーや車種によっては半導体不足により新車の生産の遅延が続いていることも、買取相場が上昇している理由の1つです。 78プラドの現在の買取相場 78プラドの現在の買取相場は、下記のとおりです。 型式 買取相場 KZJ78G 10万〜300万円 KZJ78W 10万〜300万円 LJ78G 10万〜150万円 LJ78W 10万〜150万円 78プラドは、ランドクルーザープラドの中でも人気があるモデルのため、車輌の状態がよければ高く売却できる可能性があります。なかでも1KZ-TE型エンジンを搭載している後期モデルには高値がつきやすいです。 また、カスタムされた個体が注目されているものの、元の状態を保った車輌も高い評価を受けています。リセールバリューを考慮すると、オリジナルの状態を維持している方が流行に左右されにくく、より高値で売却できる可能性が高いでしょう。 78プラドを高く売るにはどうすればよい? 78プラドの現在の買取相場を紹介しました。ここでは、より高く売るためにおさえておきたいポイントを解説します。 こまめにメンテナンスする 78プラドは、最終モデルであっても発売されたのが1996年で、車齢は25年を超えています。不具合が発生する可能性は低くはありません。 そのため、良好な状態を保つためにはこまめなメンテナンスが必須です。また78プラドのユーザーの声を聞くと「故障しない車」というよりは「故障してもすぐに直せる車」であるようです。モデルチェンジしても部品を新設計にしないなど、トヨタのランドクルーザーに対する設計思想が強く影響しています。少し異変を感じたら、症状が悪化する前に確認しましょう。 無茶な走行を控える いかに走破性の高いプラドとはいえ、何度も繰り返して悪路を走行すると負担がかかります。車重も大きいため、悪路走行時は特に足回り部品を酷使することになります。 とはいえ山道を走るために乗っているユーザーも多いでしょう。悪路走行時にはなるべく優しい運転を心がけることをおすすめします。 長距離運転では定期的に休憩する 78プラドは、エンジンや燃料噴射系の故障が多いといわれています。中にはシリンダーヘッドが割れたという事例もあり、これら部品への負担を抑えるためにも、長距離移動時には十分に休憩を取ることをおすすめします。
