「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
旧車の魅力と知識

997がポルシェ911らしさを取り戻した理由とは?! レースでも実力を発揮した人気モデルを徹底解説
6代目ポルシェ911として登場した997は、ファンを唸らせる完成されたデザインと性能からベストモデルとも評されています。「原点回帰」と「進化」をうまく融合した結果、商業的な成功も収めました。911の本質を取り戻したともいわれる997型の魅力を、レースでの活躍とともに徹底解説します。 ポルシェ本来のスタイリングに回帰した997 997型へのフルモデルチェンジでは、先代996型で不評だったポイントを中心にデザインの見直しが図られています。一方性能面でも、マイナーチェンジで新開発エンジンやトランスミッションを投入するなど、997型はポルシェが意欲的に開発したモデルといえるでしょう。マイナーチェンジでの変更点も含めて、997の特徴を改めてみていきましょう。 先代の外観と性能から大きく進化 2004年に登場した997型ポルシェ911は、7年ぶりのフルモデルチェンジを果たして2004年に登場しました。基本骨格やエンジンの一部こそ先代996型と共通ですが、賛否を呼んだ外観デザインは大幅に刷新されています。 ヘッドライトの形状は、不評だった「涙目」形状から丸型に戻されました。また、スモールランプとウインカーも、空冷時代を思い起こさせる別体型に変更。リアコンビネーションランプとリアバンパーの刷新とあわせて、再び“ポルシェらしさ”を取り戻したモデルとして高く評価されました。 マイナーチェンジでさらなる性能アップを果たす 997型は、発売後も意欲的に開発が続けられました。フルモデルチェンジから4年後の2008年6月には、ビッグマイナーチェンジを実施します。特筆すべきはエンジンの改良で、以前のモデルから大幅に出力を向上させました。自然吸気モデルに採用した新開発の直噴(DFI)エンジンによって、カレラが20psアップの345ps、カレラSでは30psも出力を向上させて385psを実現しています。 さらに、トランスミッションには、新開発のPDK(7速デュアルクラッチ)が新たな選択肢として投入されました。スポーツ走行だけでなく日常使用でもスムーズな変速を実現するPDKによって、さらなる操作性と快適性の向上が図られています。 多彩なラインナップを展開 997型では、ベーシックなカレラ/カレラSに加え、タルガ、カブリオレ、4WDモデル、ラグジュアリー路線のターボ/ターボSといった多彩なラインナップが展開されました。さらに、スポーツ性と快適性を両立したGTSに加えて、GT3やGT2という走行性能に特化したモデルも投入されています。 志向やライフスタイルに応じてモデルを選べるようにしたことで、幅広いユーザー層から支持を獲得しました。スポーツモデルという大きな枠組みはあるものの、さまざまな楽しみ方ができる点が997の大きな魅力です。 ポテンシャルの高さをレースで証明 旗艦モデルである911は、レースで結果を残すことが至上命題です。レースで勝てる力強い走りこそ、ポルシェ911最大の魅力だといえます。 幅広いモデル展開が特徴の997は、周囲の期待どおりレースで輝かしい実績を残しました。一方で、評価の高い997には、ひとつだけ大きな欠陥があります。997のレースでの活躍と、有名な「インタミ問題」について紹介します。 2度のル・マン24時間レース制覇 997のレーシングモデル「997 GT3 RSR」は、フルモデルチェンジから2年後の2006年に実戦投入されます。エンジンの最高出力は455psにまで高められ、435 N⋅mという強大なトルクも相まってさまざまなレースで実力を発揮しました。 過酷なレースとして知られるル・マン24時間レースでは、2007年と2010年にGT2クラスを制覇。また、プチ・ル・マンでも、2007年、2013年にクラス優勝を果たします。997のもつ高いポテンシャルと信頼性を、レースの結果で証明しました。 唯一の弱点「インタミ問題」 実力、人気ともに折り紙つきの997ですが、実はひとつだけ構造的な弱点を抱えています。「インタミ問題」という通称までつけられた、インターミディエイトシャフトを保持するベアリングが破損する問題です。 997のエンジンは、クランクシャフトとチェーンを介してつなげられたインターミディエイトシャフトによって、カムシャフトを回転させる機構を採用しています。しかし、インターミディエイトシャフトを保持するベアリングの耐久性に問題があり、数多くの破損が報告されました。ベアリングが破損すると当然インターミディエイトシャフトの回転に影響がでるため、カムシャフトを正確なタイミングで回せなくなります。結果、バルブタイミングが狂ってしまうことで、最悪の場合エンジンブローにもつながりかねません。 ただし、インタミ問題が発生するのは、初期モデルを中心にした前期型です。2008年のマイナーチェンジ以降のモデルでは、インターミディエイトシャフト自体が廃止されたため発生しません。。また、対策パーツがすぐに開発され、ポルシェがキャンペーンで交換を推進したため、現在ではあまり気にしすぎる必要はなさそうです。997を購入予定で気になる方は、販売店にインタミ問題の対応について確認してみましょう。 20万台以上も売り上げた6代目ポルシェ911 インタミ問題という致命的な欠陥があると、一般的に販売数は伸び悩みます。しかし、メーカーの真摯な対応と997のもつ魅力の高さから、実際には商業的にも大成功を収めました。997の販売台数は、2004年から2011年までの間で累計213,004台にものぼります。販売実績だけで車の価値は判断できないものの、モデルとしての完成度の高さを物語っている数字です。 スタイリングの原点回帰、幅広い層にリーチするラインナップの多彩さ、そして何より走行性能の進化とレースでの実績によって、997型ポルシェ911は伝説とも呼ばれる評価を得ました。販売終了からすでに14年(※2025年7月執筆当時)が経過していますが、今もなお高い人気を集める車種というのもうなずけます。

5つの理由で解説。最新モデルに魅力を感じない人って理解不能だけど・・・
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会のデータによると、2024年の日本の新車販売台数は、前年比7.5%減の442万1494台。 一方で、中古車登録・届け出台数は、前年比0.3%増の646万7884台とあります。 新車の販売台数より、中古車の方が多く動いているという感じなのですが、それは経済的な面であったり、まあ、中古車を買う理由はさまざまありましょう。 で、そのなかには「新車では手に入らないムカシのクルマが欲しい!」という人たちが少なからずいる、というのは間違いがないと思います。 ◾️最近のクルマってドウなんすか? ソレって「最近のクルマに魅力を感じない」と思っているヒトたちってこと・・・? え?そうなの? いや、ソレまじすか? でもホラ、現行のクルマ、新車で欲しいヤツあるでしょ?あるんじゃないの? といわれりゃあ、まあ、たしかに欲しいなGR86とかコペンもいいよねえ。 余裕があればジムニーもちょとイイ気がするし・・・。 あれれれれ?それ旧くね? ◾️ソレ、昭和世代だから? もちろんGR86&BRZ、ホンダS660みたいに、なんか「グッ」とくるクルマはときどき出てくるけど、いやこれマジ欲しい!っていうようなクルマ少なくなった・・・という気がしませんか? まあ、なんとなくそんな感じがするのは、ワタクシの周りが昭和世代ばかり、というのも大きな理由のひとつ・・・というような気がするのであります。 いやね、ショーワエイジの我々からすると、そもそもクルマの種類そのものが少なくなってないスか? 種類というかバリエーション・・・という印象が強いんですよレイワの現代。 例えばカローラでいえば、80年代とか90年代には「セダン」「ハッチバック」「クーペ」「ワゴン」「バン」「リフトバック」スポーツモデルの「レビン」「トレノ」そういや「カローラII」兄弟車に「スプリンター」なんてのもあったというか、もうバリエーションモデルだらけ。 覚えきれない派生モデルの嵐!しかもDXとかSE、XEとかGTとかグレードまで多種多様!覚えきれんっっっ! まあ、それだけ昭和時代は豊かだったのかもしれません。 とはいえ、今でも車種はたくさんあるし、派生モデルもそれなりに存在する。 相変わらずのバッジエンジニアリングも、以前ほどではないけれど、今でも続けられているし。 選択肢そのものはソレほど変わりがないかもしれません。 ◾️なのにナンでアナタはわざわざキューシャへ行くの? 今でも、そんなたくさん選択肢があるのに、じゃあなんでアナタは「旧車」に行くの? 新しいクルマは性能はおろか安全性でも利便性でも「旧車」に比べたら、はるかに「イイ」じゃないですか! 昔のクルマって古くて扱いにくくて不便で遅くてうるさくて税金高くて狭くてカーナビないしスマートフォン連動しないし、ヘタすりゃドリンクホルダーすらないじゃないすか! それでもアナタは旧車をみて「イイなあ」とおっしゃるのですか! あっ「旧車王」なんてサイトまであるじゃないか! ナンで!? ・・・ということで、5つの理由で解説いたします。 ●理由その1「最近のクルマのデザインがなんかヤ?(趣味や嗜好の変化)」 ・最近のクルマって、なんか「獅子舞」みたいなのばっかり・しかも色がなんか地味・顔つきがオラオラしててメッキテカテカ・でかいの強調して押しが強いくせに色が地味(色2回目) ●理由その2「最近のクルマって個性(キャラクター性)が希薄?(世の中の変化)」 ・パッとみて「何に使う」クルマなのか判りにくい・なんか四角いのばっかり・選べるカラーバリエーションが地味で少ない(色3回目)・シルバーとグレーと黒と白ばっかりなの?(色4回目) ●理由その3「最近のクルマは便利さと共に失ったものがある(ノスタルジー)」 ・運転しててラクチンで便利なんだけど「面白さ」には欠ける・一台で全部済んじゃう多様性・手間が掛からない分、愛着が沸く時間がほとんどなくなった・手探りでラジオのON/OFFや選曲ができない ●理由その4「クルマの性能や機能より大切なものがある(生活様式の変化)」 ・みんなで便利に使えるとイイよね・誰かとお出かけしたりする経験が大事、クルマはそのための移動手段・でかいクルマに限って乗ってる人が少ない・軽自動車はナンだかたくさん乗ってるイメージ ●理由その5「クルマはステータスでもナンでもない」 ・クルマ持ってると「スゲエ」というより、まあ便利だよね的な(特に都市部)・地方都市ではクルマは必需品なので、使いやすく便利で安上がりなやつがイイよね・つか、持っててアタリマエ・道具として優秀であればOK ■旧い時代を知っているから? いろいろと理由を挙げてゆけばキリがないんですけれど、実は、大きな理由のひとつとして、ユーザーとして、そしてオーナーとしての我々が「昭和時代の大狂乱ともいえるバラエティ豊かなクルマ社会を知っている」からというのがあるのかもしれませんね。 すなわち「あの頃よりは・・・」みたいに、ムカシと比べちゃうんですよ。 まったく年寄りの悪いクセだ。そんなんだから年寄り扱いされちゃうんだ・・・。ってワカってながら、ソレでもいっちゃうんですよね「あのころはよかった」って。 あの頃は「好きなクルマ」が確かにあったし、それぞれにユニークなキャラクターがあった。 本気で欲しいと思えるようなクルマがたくさんあったんですヨ。 同じカローラでもサラリーマンの若いパパの乗るカローラと、20代のやんちゃなワカゾーが乗るカローラはまったく違う。 でも同じカローラ。 マイナーな方がいいならスプリンターって選択肢もアリ。 塗装業のおっさんが乗るサニーバンとサーフィン好きのワカゾーが乗るサニーバンはまったく違う。 同じサニーバンなのに。 少し違うのが欲しけりゃパルサーはいかが?(チェリーでもいいゾ) ◾️今でも充分選択肢があるのに とはいえ、今の、すなわち現行カローラだって「カローラ」「カローラスポーツ」「カローラツーリング」「カローラクロス」「GRカローラ」「カローラアクシオ」「カローラフィールダー」の7種類あるんだからスゲえっすよね。いいクルマなんですよカローラって。いいクルマ。 それでも、7種類もある現行の「カローラ」じゃなくて、ショーワのおっさんたちは(たぶん)中古車がずらりと並んだ店先眺めたり、夜な夜なパソコンの画面に映るちょっと前のクルマを探したりしてるんですよね。 なんだソレ正直「理解不能」ではあります。 が、なんとなく「そうだよなあ」って「ワカる」のは、ワタクシもショーワのおっさんだからなのでしょう。 そう、身体では現行モデルが「イイもの」って解っているのに、脳みそが「イヤ、オマエのホシイのは本当にソレなのか?」っていってんの。 そのとき、アタマのなかでは、なんか知らないマスコットとか、エンブレムがついたキーホルダーがぶら下がってるキーを、ドアの穴に差し込んでガシャッとトアを開けるあの感触。 ボタンを押すんじゃなくて、キーを突っ込んでセルを回すあの感覚。 エンジンがかかると微妙な振動とともにブルブル震える車体とサウンド。 その感触を得てはじめて「クルマ運転してるぞオレ」感を得ることができる、みたいな。 ◾️旧車をこよなく愛する「困った人」たち(ほめ言葉) それは確かに、今よりも「安全じゃない」し「便利でもない」し、実際「お金かかる」し「面倒臭い」し、なんなら「古臭い」し「使いにくい」。でもそんなクルマに「魅かれて」しまう。 そんな人たちが一定数いる。 自動車を単なる道具としてだけでなく、クルマを「文化」として捉えて一緒に生きてゆく。 それは多分ヨーロッパでも、アメリカでも、アジアでも、一定数いるはずです。クルマを持つこと、運転することが目的の人たち。 ウンチク垂れたがるオッサンたちがイキイキとして、楽しげに走るために、走るのが目的で走ってゆく。 ときに故障に悩み、仲間が集まると自分のクルマの調子が悪いことをまるで自慢話のように語りたがる、13年以上経ったクルマの税金高いの何とかならんかねえ、とかいってるアノ人たちのことですよ・・・。 まったく困った人たちですよねえ(笑)。もう。 [画像・トヨタ,日産, マツダ、ライター / まつばらあつし]

デザインに革命を起こしたワンダーシビックを振り返る! グループAにおける活躍も紹介
切り立ったリアハッチの形状が特徴的な、ホンダ 3代目シビック。ワンダーシビックの愛称で親しまれるこのモデルは、シビックファンのみならず世界中のホットハッチ愛好家にインパクトを与えました。 ワンダーシビックがなぜ革新的モデルといわれるのか、その理由をレースでの輝かしい戦績とともに振り返ってみましょう。 3代目シビックがもたらした新たなホットハッチの形 「ワンダーシビック」と呼ばれる3代目ホンダ・シビックは、当時のハッチバックの概念を覆す存在でした。海外の有名自動車デザイナーでさえ解決できなかったデザイン上の問題を、見事な手法で解決します。 ワンダーシビックのデザインの特徴について、詳しくみていきましょう。 未来を予感させるデザイン 3代目シビックは、1983年に登場しました。先代のイメージを大きく刷新するばかりか、世界の常識をも打ち破った革新的なデザインが話題になりました。2代目シビックの販売台数がふるわなかったことから、大きな変化を求められていたという側面もあったのかも知れません。 ワンダーシビック最大の特徴は、リアハッチの切り立ったコーダトロンカです。ルーフラインを後方ギリギリまで水平に伸ばし、リアゲートを垂直に切り落とすという当時としては大胆な形状をしています。先代以前のシビックも含め、国産車では類を見ない未来的なフォルムでした。 その先進性と完成度の高さは専門家からも認められ、1984年度には自動車として初めてグッドデザイン大賞を受賞。さらに、同年の「'83~'84 日本カー・オブ・ザ・イヤー」にも輝きました。 名デザイナーでさえ避けた問題を打破 ワンダーシビックのデザインへの関心の高まりには、世界的な有名デザイナーでさえ避けた点に挑戦したことも影響しています。当時のハッチバック車は、フォルクスワーゲン社のゴルフを模倣したデザインのものがほとんどでした。イタリアの有名デザイナー、ジョルジェット・ジウジアーロ氏が徹底的に合理性を追求して生み出したフォルムだったため、覆す必要がなかったのです。 しかし、ゴルフのデザインには、唯一といえる欠点がありました。垂直にすると商用車にみえるという理由から、リアハッチに傾斜をつけていた点です。車室後部にリアハッチが倒れ込んでくるため、荷室の容積にどうしても制限が発生してしまいます。 そこで、ホンダ開発陣はリアハッチを垂直に立てつつも、ハッチバックの軽快さを失わないデザインを追求します。後部まで伸びたルーフになだらかな傾斜をつけつつ、リアのサイドウィンドウの下端ラインを後方に向かって微妙に上昇していくデザインとし、シャープな印象を与えるウェッジ効果を発揮しています。さらに、Bピラーを黒く塗りつぶすことで、横からみても愚鈍な商用車にはみえない軽快なデザインを実現しました。 ジウジアーロ氏が懸念したデザイン上の問題点を、新たな発想で見事に解決してみせたのです。ゴルフの呪縛ともいわれるほど定番化していたハッチバックのデザインを、根底から覆す画期的なアプローチでした。 高い走行性能がデザインの正当性を裏打ち いくらデザイン上の問題を解決して軽快に見せても、クルマとしての性能が伴っていなければ高い評価は得られません。ワンダーシビックは、デザイン性と走行性能を両立させるため、細部にまで徹底的にこだわって開発が行われました。 ワンダーシビックの走行性能とレースの活躍を振り返ってみましょう。 軽快な走りを実現したサスペンション ルーフデザインが大きな特徴といわれるワンダーシビックですが、実はボンネットラインを下げたことも外観のスポーティさを高めているポイントです。しかし、ボンネットラインを下げるには、足回りの構造が大きな課題として立ちはだかりました。 エンジン、ミッションともに横置きのFF車では、サスペンションのスペースに大きな成約が生まれます。一方で、ボンネットラインを下げるという命題があるため、コイルバネの高さを必要とするストラット式サスペンションも使用できません。 そこで、ポルシェ911にも採用されていた、トーションスプリング(ねじりバネ)式のサスペンションを採用して、低いボンネットとスペースの制約問題を解決します。さらにこだわったのはリアサスペンションでした。分類上はトーションビーム式サスペンションの一種ですが、極めてユニークな形状をしています。後部座席の制約も受けるなか、トレーリングリンク式ビーム・サスとも呼ぶべき形状のサスペンションは、後席の居住性と運動性を両立すべく考案されました。 シーズン全戦優勝 ワンダーシビックの性能が優れていたことは、レースの世界でも証明されています。発売から2年後の1985年に、ホンダはワンダーシビック(AT型)で全日本ツーリングカー選手権(JTC)に初参戦しました。 参戦2戦目の鈴鹿サーキットで、並み居る強豪を抑え総合優勝という快挙を成し遂げます。時折雨の降る優れない天候のなか、中嶋悟/中子修組はFFの強みを活かして安定した走りを披露しました。 さらに、「MOTUL 無限 CIVIC」にエントリー名が変わった1987年には、他を寄せ付けない圧倒的な速さを見せつけます。中子修/岡田秀樹組が6戦全勝を達成。ドライバーズとマニュファクチャラーズのダブルタイトルを獲得しました。 最終的に、JTCで通算12勝という輝かしい戦績を残し、1988年シーズン途中でその役目を終えました。 シビックの方向性を決定づけたワンダーシビック ワンダーシビックは、名車と呼ばれるEF型、EG型の原型ともいわれるモデルです。ホンダ・シビックは、1987年から1993年までの全日本ツーリングカー選手権(JTC)において、グループA規定の最小排気量クラス(1987年はクラス1、後にクラス3に改称)で、マニュファクチャラーズタイトルを7連覇という偉業を達成しました。ワンダーシビックは1988年のシーズン途中まで出場しており、偉業達成のきっかけとなったモデルです。 EG型になってやや丸みを帯びたものの、リアハッチが切り立った形状はシビックの伝統として踏襲され続けました。デザイン性と走行性能を両立したホットハッチとして、日本のみならず世界で愛され続けているシビック。ワンダーシビックの開発陣が踏み切った、コーダトロンカがなければ実現していなかったかも知れません。

「旧車(Old Car)祭り IN 美和」の舞台裏とは?主催者に聞く!親子で紡ぐ物語
2025年5月11日に、茨城県常陸大宮市で「第7回旧車(Old Car)祭り IN 美和」というイベントが開催された。 このイベントはこの媒体(旧車王ヒストリア)でも取材しており、読者の方々にも周知のことかもしれない。 ●クセ者ぞろいの参加車輌が魅了する「第7回旧車(Old Car)祭り IN 美和」イベントレポートhttps://www.qsha-oh.com/historia/article/oldcar-festival-7th/ イベントでは主催者が若かったり、大きな志を持って行われている方などもいることだろう。もちろん筆者もそうした方々の話を聞き、時にその思いに感銘を受けたり考えさせられたりもしたものだ。しかしながらこれを親子で始められたということがとても筆者の興味をそそらせた。これから話すのはそんな親子が紡いだイベント開催の物語だ。 ■「旧車(Old Car)祭り IN 美和」をはじめたきっかけ 今回で7回を数えるという「旧車(Old Car)祭り IN 美和」。しかし、主催者は実際に開催できたのは6回なのだと話す。過去に台風で中止になりかけ、前日まで頑張って準備をしていたこともあり、これもカウントしておきたいという想いから7回目としたという。 主催者の野澤氏は事業の関係から自身がイベントに参加することはなかなか難しい。「それなら来てもらったらどうだろう?」と考えて周囲に相談しつつ、「旧車(Old Car)祭り IN 美和」を立ち上げて今に至ったという。 ■思わぬ協力者が現る! 野澤氏がイベントを自ら興そうと動きはじめた矢先、ちょうど時を同じくしてご子息が氏より受け継いだ(ご本人はまだ自分の物だと否定・笑)3代目になるホンダ プレリュードに乗ってドライブやイベントに参加をする日々を送られていた。 そのこともあり、ご子息が「それならば」と、会場で起こるトラブルの元やアクシデントの事例を他のイベントに参加することで調べ、自身で感じたことを実際に対処する手段や実例のデータとして持ち帰る。 その後、野澤氏が開催に向けて手探り状態で行っていたトラブルシューティングに対して、ご子息が自らの体験をフィードバックすることでイベントをより良いものにしようと取り組んできたそうだ。 ご子息にも話しをお聞きした際に「もうある意味、情報収集のためにイベントに参加していた感じでしたね。それをまた持ち帰ってウチのイベントに当てはめるわけです」。そうしたご子息や多くのスタッフの支えにより、現在に至ったそうだ。 「旧車(Old Car)祭り IN 美和」の特色として、地域密着を大事にしており、ケータリングも地元の食を楽しんでもらうことを前提に声をかけていると話す。そうした思いが多くの参加者だけではなく、見学者にも現れているのではないだろうか。 ■心が折れずに済んだのは、ある参加者の一言がきっかけだった 野澤氏も7回の開催のあいだにはさまざまなことがあったと語る。数年前にはコロナもあり、苦渋の決断で中止にしたこともあったそうだ。もちろん開催においては天候にも左右されたこともあった。 今でこそ春先に開催されるイベントとして行われているが、かつては秋口に開催して台風でやむなく断念をしたこともあったそうだ。それだけに天候にはいつも悩まされるという。そんなときは、以前いわれた言葉が頭をよぎるそうだ。 開催するべきか悩んでいたとき、参加者の1人から掛かってきたある電話に背中を押されたのだという。「中止なら中止でも構わないよ。それでも俺は行くからさ。1台だけでもいくからさ」。 野澤氏は開催か延期か決断ときにはいつもこのひと言が頭にあるという。もし中止でも足を運んでくれる人もいる。今回は来てもらえなくても次回は必ず楽しんでもらいたい。その思いが今に至っているのではないだろうか。 ちなみに、昨年は1,000人を越える一般来場者があったそうだ。そのこともあり、今後駐車スペースの確保はますます大事だと考えているという。今年の来場者数はどうだったのか?それはこの前日までの予報を覆す好天を見れば聞くまでもないだろう。 ■やれることはわずかでも、地元に貢献したい 今後の展開はどうなるのか?どうしていきたいのか?の質問に意外にも野澤氏は大きくはならなくてもいいと語る。 いまくらいの台数や規模で続けて行けたらと思っているそうだ。欲がないと思えるかもしれないが、やはり管理の目を行き届かせるには現時点くらいが自身の限界と考えているという。 また、スペースの関係も起因している。少なくとも現時点で会場の移転は考えていないし、この美和地域でやりたいという揺るがない思いがあるからだ。それでもエントリーをしてくれる参加者を増やすことはなくても、見学者にはできる限り対応をしていきたいという。 それは、地元の方だけでなく、近隣はもちろん遠方からもこのイベントと常陸大宮市を知ってもらうきっかけにしたいと考えているからだ。奇しくもご子息にも同じ質問をした際にも同じ答えがかえってきた。 「正直、人口はどんどん減っていると思います。でも町おこしではないですが、昔あったお祭りのように、年に一回常陸大宮市のイベントといえば【旧車(Old Car)祭り IN 美和】だといってもらえるようにしたいですね」。そう笑う親子の笑顔はどちらも同じ笑顔で筆者に答えていた。 地道な努力は実を結び、今や市長や県会議員が開会あいさつに駆けつけるイベントに育つ。 この日の司会にマイクを握ったのはタレントのおふたり、電撃ネットワークの今日元気(きょうもげんき)氏とヨッシャ比留間氏だ。 地元の味を楽しんでもらえるようにと考えて声をかけているというケータリング。参加者に聞いた話では昨年は見学者も買うことが多く、うっかり出遅れた参加者が食べ損ねたといううわさもあるほど盛況だったそうだ。 [ライター・カメラ / きもだこよし]

軽自動車は引っ越し時に車庫証明の住所変更は不要!必要な手続きと方法を解説
引っ越した際は車庫証明の住所変更が必要と聞き、手続き方法を調べている方もいるでしょう。そもそも軽自動車は普通自動車とは異なり車庫証明の取得が不要です。 ただし、地域によっては期日までに新しい住所を管轄する警察署で「保管場所届出」をする必要があります。 この記事では、引っ越し時に軽自動車の車庫証明の住所変更が不要な理由や保管場所届出の手続き方法などについて解説します。 軽自動車において引っ越し時に車庫証明の変更手続きは不要 軽自動車は、普通自動車や小型自動車とは管理する行政機関が異なるため、引っ越しをしても車庫証明の住所変更手続きは必要ありません。 普通自動車や小型自動車は「運輸支局」が管理しています。そのため、新しくクルマを購入したときは、車庫がある住所を管轄する警察署で申請をして車庫証明書を入手しないと運輸支局で車検証(自動車検査証)やナンバープレートが交付されません。 引っ越しをして保管場所が変わったときは、新しい住所を管轄する警察署で車庫証明の住所変更手続きが必要です。 一方、軽自動車を管理するのは軽自動車検査協会です。軽自動車を購入したときは、車庫証明書がなくても軽自動車検査協会で車検証やナンバープレートが発行されます。 保管場所が変わった際は、必要に応じて管轄の警察署で保管場所届出の手続きをするのみでよいとされています。 軽自動車における引っ越し時に届出が必要な場合がある 管轄の警察署で保管場所届出の手続きが必要となるのは、以下のような地域に軽自動車の保管場所がある場合です。 ・県庁所在地 ・人口10万人以上の都市 ・東京や大阪などの都心部から30km以内の市区町村 上記に該当していても保管場所届出が不要な場合もあります。引っ越し先の住所が保管場所届出の必要がない「適用除外地域」に該当するかどうかを各都道府県の警察署のWebサイトで確認しましょう。 ここでは、保管場所変更届出をする際の必要書類や手続き先を解説します。 必要書類 警察署へ軽自動車の保管場所を届け出る際の主な必要書類は、以下のとおりです。 ・自動車保管場所届出書 ・保管場所の所在図・配置図 ・保管場所の使用権原を疎明する書類 →自身が所有する土地に保管:保管場所使用権原疎明書(自認書) →貸し駐車場に保管する場合:保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し など 所在図・配置図は、保管場所の位置や駐車スペースの寸法などを明記した図面です。保管場所使用承諾証明書は、駐車場の所有者や管理者に記入してもらう必要があります。 書類に不備があると再提出を求められることもあるため、記入漏れや添付書類の不足がないか、よく確認することが大切です。 申請書類を作成する際は、各警察署のWebサイトで公開されている様式や記載例を活用するとよいでしょう。 なお、以前は「保管場所標章交付申請書」の提出が必要でしたが、2025年(令和7年)4月1日から不要となっています。クルマに貼り付ける保管場所標章(ステッカー)も発行されなくなりました。 手続き方法 保管場所届出をする際は、新しい保管場所がある住所を管轄する警察署に必要書類を提出します。引っ越しをする前の住所を管轄する警察署ではない点に注意しましょう。 受付時間は月曜日から金曜日の午前9時〜午後4時までです。土日祝日と年末年始は原則として手続きできません。 受付の開始時間と終了時間は警察署によって異なるため、事前にWebサイトで確認しましょう。 警察署の窓口に必要書類を提出すると不備がなければ控えが渡され、その日のうちに手続きが完了します。 保管場所届出に手数料はかかりません。保管場所標章の廃止により、500〜600円程度の発行手数料もかからなくなりました。 引っ越し時は軽自動車の車検証の住所変更手続きが必要 軽自動車の所有者は、引っ越しで住所が変わった場合、道路運送車両法第12条にもとづき、その日から15日以内に車検証の住所変更手続きをする必要があります。 第十二条:自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 また、同法の109条では車検証の住所変更手続きを怠ると「50万円以下の罰金に処される」と定められています。 第百九条:次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 引用:e-gov 法令検索「道路運送車両法」 さらに、車検証の住所がそのままであると自動車税(種別割)の納税通知書が新しい自宅に届かず、納税を延滞してしまう可能性もあります。 住所が変わったときは必ず期日までに車検証の住所変更手続きを済ませましょう。 以下では、手続きの際に必要な書類や申請先を解説します。 必要書類 軽自動車の車検証の住所変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。 ・自動車検査証(車検証)の原本 ・住民票の写しや印鑑(登録)証明書など使用者の新しい住所を証明する書類 ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) ・ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ) ・希望番号の予約済証(希望ナンバーを希望する場合) ・申請依頼書(使用者ではない人が手続きをする場合) 自動車検査証記入申請書は、軽自動車検査協会の窓口で入手できる他、Webサイトからダウンロードすることも可能です。 住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを準備しましょう。 引っ越しにより住所を管轄する軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。 車検証の住所変更手続きは無料ですが、ナンバープレートを変更する場合は別途手数料がかかります。 手続き方法 軽自動車の車検証の住所変更をする場所は、新しい住所地を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室の窓口です。 申請書に必要事項を記入し、その他の書類とあわせて窓口に提出すると、不備がなければ新しい情報が記載された車検証が交付されます。 住所の管轄が変更になる場合は、古いナンバープレートを返納して新しいナンバープレートを取り付けて封印をしてもらいます。封印は、ナンバープレートを固定するボルトにアルミ製のキャップを取り付けることです。 ▼関連記事車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 軽自動車の引っ越し時には保険の住所変更も必要 引っ越しにより住所が変わったときは、自動車保険の住所変更手続きも必要です。 自動車保険には、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」と、加入が個人の判断に任せられている「任意保険」があり、それぞれ手続き方法が異なります。 以下では、自賠責保険と任意保険の住所変更手続きについて詳しく解説します。 自賠責保険 自賠責保険の住所変更手続きをするときは、加入している保険会社の窓口に訪れるか、保険代理店の担当者に連絡をします。 また、スマートフォンやパソコンなどから「One-JIBAI」という損害保険業界共通の専用Webサイトにアクセスして手続きをすることもできます。 住所手続きの際に必要な書類は以下のとおりです。 ・自動車損害賠償責任保険証明書 ・運転免許証や健康保険証など新しい住所が確認できる書類 ・ナンバープレートまたは軽自動車届出済証(住所変更と同時に変更がある場合) One-JIBAIで手続きをする場合、画面の指示にしたがって項目を入力し、必要書類をスキャンするかスマートフォンで撮影してアップロードします。 手続きが完了すると、後日住所が変更された自賠責保険証明書が届きます。届けられた新しい証明書の記載項目に誤りがなければ、古い証明書を破棄しましょう。 任意保険 ほとんどの任意保険は、インターネットから保険会社の契約者専用ページで住所変更手続きができます。 他にも「保険代理店の担当者に連絡する」「保険会社に電話する」「保険会社の窓口に出向く」などの方法で手続きが可能です。 手続きの際には、住民票の写し・運転免許証・マイナンバーカードなど新しい住所がわかる書類を準備しましょう。 地域ごとの事故や盗難、自然災害などのリスクに応じて保険料が設定される保険会社の任意保険は、住所変更によって保険料が変わることがあります。その場合は、住所変更手続きの際にクレジットカードや銀行口座の情報がわかるものが必要です。 手続きの際は、年間の予想走行距離やクルマの使用目的、運転する人の範囲なども申告するため、引っ越しにともないこれらに変更がないか検討しましょう。 また、補償に過不足がないかも検討し、必要に応じて見直しをすることもおすすめします。 軽自動車の引っ越し時には運転免許証の住所変更も必要 道路交通法の第94条では、運転免許証の記載事項に変更があった場合、速やかに届け出ることが義務付けられています。そのため、引っ越しをしたときは運転免許証に記載される住所の変更手続きが必要です。 手続きを怠ると「2万円以下の罰金または科料」に処される可能性があります。 また、更新のお知らせハガキが新しい住所に届かず、免許の更新を失念するリスクも高まるため、引っ越しをしたときは運転免許証に記載される住所を速やかに変更しましょう。 以下では、運転免許証の住所変更をする際の必要書類や手続き先を解説します。 必要書類 運転免許証の住所変更手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。 ・運転免許証またはマイナ免許証(どちらも持っている場合は両方) ・住民票の写しや公共料金の領収書、健康保険証など新しい住所が確認できる書類 マイナ免許証は、免許情報が記載されるマイナンバーカードです。2025年(令和7年)3月24日から運用が開始されました。 住所変更手続きの際に、新しい住所が確認できる書類が必要となるのはマイナ免許証を発行しておらず通常の運転免許証を利用している人です。 マイナ免許証を取得し、市区町村役場でマイナンバーカードに登録されている住所を変更している場合、運転免許証の住所変更手続きをする際に新しい住所を確認できる書類を準備する必要はありません。 運転免許証を返納してマイナ免許証のみを保有しており、所定の手続きをするとワンストップサービスにより、住所・氏名・本籍の変更時に警察署等への届出が不要となります。 新しい住所が確認できる書類の種類や条件は、警察署や運転免許センターのWebサイトに記載されています。「住民票の写しはマイナンバーが記載されていないもの」「マイナンバーの通知カードは不可」などの条件が設けられているため、事前に確認しておきましょう。 手続き方法 運転免許証の住所変更手続きは、新しい住所地を管轄する以下の施設で行えます。 ・各警察署 ・運転免許試験場 ・運転免許更新センター 警察署と運転免許更新センターで手続きができるのは、原則として平日の日中です。土日祝日と年末年始は手続きできません。 一方、運転免許試験場は平日に加え日曜日も手続きができる場合があります。 受付時間は「午前8時30分〜午後4時30分」「午前9時〜午後5時」など地域や施設によって異なります。 運転免許証の住所を変更する際は、インターネットで受付場所や受付時間を事前に確認しましょう。なお、手続きをする場所にかかわらず手数料は無料です。 手続きの際は、窓口に備え付けられている「運転免許証記載事項変更届」を記入し、必要書類とあわせて提出します。 提出された書類に不備がなければ、運転免許証の裏面に新しい住所が追記されるため、誤りがないかよく確認しましょう。裏面の記載欄が埋まっている場合は、新しい住所が記載されたシールが貼り付けられます。 まとめ 軽自動車の場合、引っ越しをしても車庫証明に関する手続きは不要ですが、新しい住所を管轄する警察署で保管場所届出が必要となる場合があります。 また、車検証や自動車保険(自賠責保険・任意保険)、運転免許証の住所変更も必要です。 車検証や運転免許証の住所変更を怠ると罰則や科料が科される可能性もあるため、引っ越しをしたときは漏れなく手続きをしましょう。

最強のマツダ サバンナRX-7?! タケヤリ山路で有名な風林火山・FC3Sの実力を振り返る
白いボディに大きな「風林火山」のカッティングロゴ。タケヤリ仕様として話題を集めたFC3Sは、今見ても存在感があります。しかし、風林火山・FC3Sは見た目だけではなく、サーキットでも高い実力を示しました。 販売終了から10年近くが経過しても第一線で戦えることを証明した風林火山・FC3Sの開発秘話を中心に、FC3Sの実力の高さを改めて紹介します。 オーナーに夢を与えた風林火山・FC3S 1990年代初頭に販売が終了したサバンナRX-7 FC3Sですが、2000年代に伝説のチューニングプロジェクトが立ち上がりました。タケヤリ山路氏とRE雨宮が手掛けた、風林火山・FC3Sです。 FC3Sの概要とともに、風林火山・FC3Sの開発秘話を振り返ってみましょう。 サバンナを冠した最後のRX-7 2代目RX-7のマツダ サバンナRX-7 FC3Sは、1985年から1992年まで販売されました。RX-3から引き継いできた、伝統の「サバンナ」という名称が与えられた最後のモデルです。RX系の集大成として、ロータリーエンジンの実力を世界に知らしめました。 FC3Sへのモデルチェンジでもっとも話題になったのは、新開発の13B-T型ロータリーターボエンジンです。前期型で185ps、最終のアンフィニIIIでは215psもの最高出力を発揮。さらに、軽量コンパクトなロータリーエンジンの利点を活かし、わずか1.2tの車重と前後重量バランスのよさからライバル車と肩を並べる存在でした。 5万円の事故車をレストア&フルチューン 風林火山・FC3Sとは、タケヤリ山路こと故・山路慎一選手が筑波最速を目指してRE雨宮と共同で立ち上げたプロジェクトです。また、ベース車輌は5万円で購入した大事故車だったことから、FC3Sオーナーの間で話題になりました。 フレームが曲がるほどのダメージでエンジンもまともに動かない状態でしたが、RE雨宮の協力のもと丁寧に補修箇所の修復が進められます。また、同時に各部の補強やチューニングも施され、最強のFC3Sへと変貌を遂げました。 また、白に塗装されたボディサイドにはFC3Sの直線を活かすようにカッティングステッカーが貼られ、峠を走るストリートカーのような雰囲気を醸し出しています。東京オートサロン2002で、チューニングカー部門のグランプリに輝きました。 RE雨宮だから実現した最強FC3S 風林火山・FC3Sは、RE雨宮のチューニングによって最強と呼べるにふさわしいスペックに仕上げられました。エンジンは13BターボをベースにTD07S-25Gタービンをセットし、最高出力は463psにまで高められています。 足回りは、ダンパーはクァンタムベースのRE雨宮スペック、スプリングはスウィフト製という組み合わせを選択。ロール時の前後キャンバー変化量の違いを抑える、最適なセッティングが施されています。 また、製作にあたっては、事故車という点も多大に考慮されました。事故を修復すると剛性が下がってしまうため、ボディに直接溶接したロールバーが張り巡らされています。 RE雨宮のフルカウルプロを軸にまとめられたエアロパーツは、リアウィングが特徴的です。フロントオーバーハングの長いFC3Sの特性を考えて、できるだけ後方に装着されました。エアロパーツまで含めて、筑波最速を目指して綿密に設計されていることがうかがい知れます。 驚異的な記録を樹立したFC3Sの実力 FC3Sは峠でのイメージはあるものの、あまりモータースポーツでの活躍の印象はありません。しかし、実はレースの世界でも、FC3Sの高い実力が証明されています。 風林火山・FC3Sが筑波サーキットで樹立した記録も含めて、レースでの活躍を振り返ってみましょう。 風林火山・FC3Sが筑波で残した大記録 風林火山・FC3Sは、開発の目的だった筑波サーキットのタイムアタックで58秒890という大記録を叩き出しました。FC3Sの実力とともに、RE雨宮のチューニングとタケヤリ山路選手のドライビングがもたらした結果といえるでしょう。 真実は不明ではありますが、後発のFD3Sや日産 R34型GT-Rなどが筑波サーキットで58秒台という情報は確認できました。FC3Sが1980年代に発売されたことを考えると、風林火山・FC3Sがマークした記録がいかに驚異的だったかがわかります。旧車の枠に収まらない高い実力は、多くのRX-7に夢を与えました。 あの土屋圭市氏がドライブしてモータースポーツでも活躍 一般的に、FC3Sはモータースポーツのイメージが薄いかもしれません。しかし、JSS(ジャパンスーパースポーツセダン)ではタイトルこそ獲得できなかったものの、数々の勝利を挙げ、その実力の高さを証明しました。 特に1991年の最終戦となった富士スピードウェイでの雨のレースにおいて、土屋圭市選手(ドリキン)が見せたドリフト走行は、伝説として今も語り継がれています。 FC3Sによって地位を確立したRX-7 サバンナの集大成とも呼べるFC3Sは、ロータリーエンジンとスポーツカーRX-7の地位を確立しました。ボディデザインこそ直線基調から曲線ベースに変更されましたが、リトラクタブルライトやワイド&ローに構えるスタイリングといった特徴は、後発のFD3Sにも引き継がれています。 また、しっかりとしたチューニングさえ施せば、現代でも十分戦えるマシンであることを風林火山・FC3Sが証明しました。タケヤリ山路氏の情熱とRE雨宮の技術力が不可欠だったことはいうまでもありませんが、ベースの設計から実力が高い車種であることは間違いありません。
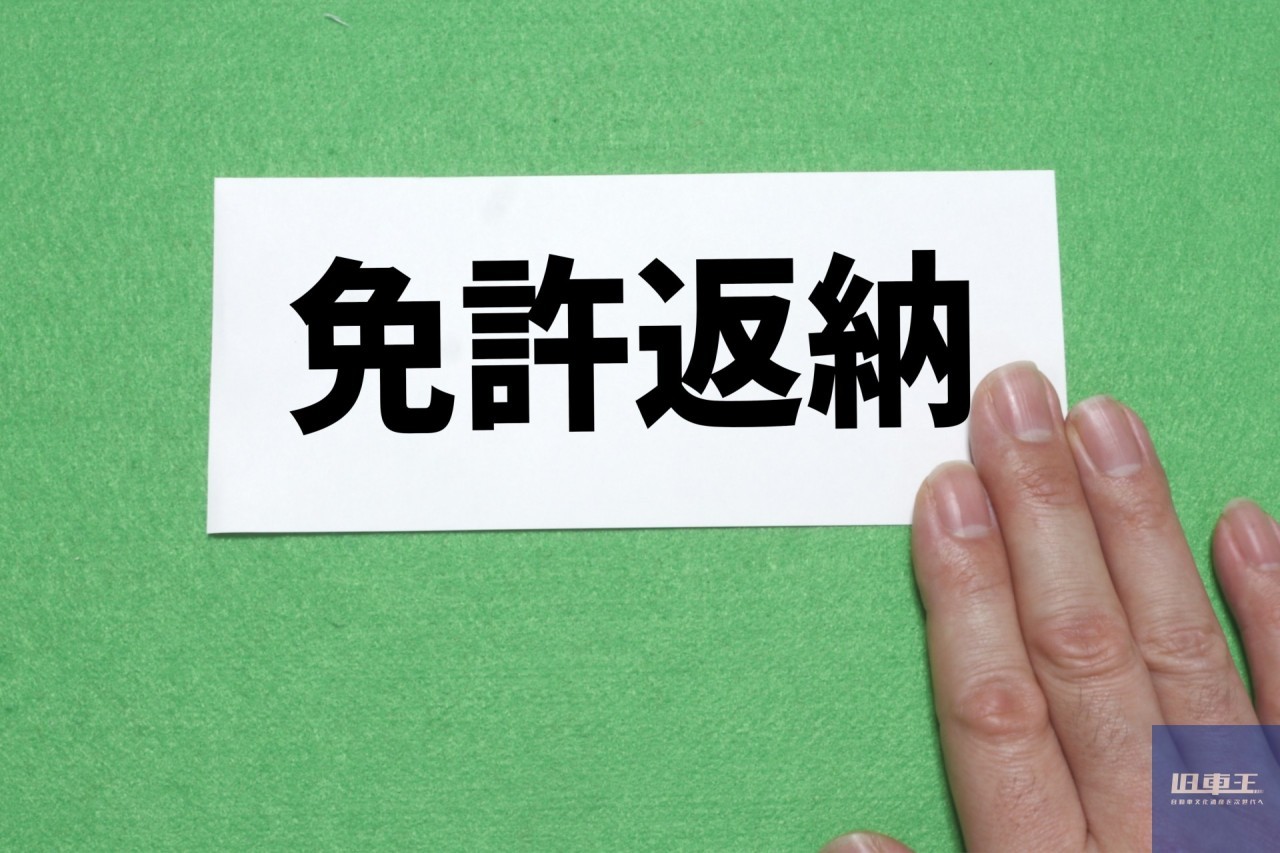
免許返納後にクルマの名義変更は必要?必要な手続きと注意点まとめ
運転免許証を返納した後、愛用してきたクルマの取扱いに悩む方は少なくありません。「もう運転しないけれど、クルマは手元に置いておきたい」「家族が使うかもしれないから、名義はそのままにしておいても大丈夫だろうか」そんな考えが頭をよぎることもあるでしょう。しかし、免許返納後にクルマを所有し続けることにはリスクが伴います。 この記事では、免許返納後にクルマの名義をそのままにしておくことのリスク、必要な名義変更手続きや保険の取り扱いについて解説します。 免許返納後もクルマの名義をそのままにしてよい? 免許返納後にクルマの名義変更をすることは、法的には義務づけられていません。しかし、クルマを使用する人が変わる場合には、適切なタイミングで名義変更手続きを行うことが推奨されています。これは、名義変更をしないことにさまざまなリスクがあるためです。免許返納後もクルマの名義を変えないことの影響について、詳しくみていきましょう。 名義変更をしないリスク クルマの名義変更をしないまま放置すると、いくつかのリスクが生じる可能性があります。 たとえば、自動車税の納付義務は車検証上の所有者に課せられるため、免許返納後も税金を納める義務があります。また、ご家族などがそのクルマを運転して事故を起こした場合、所有者として責任を問われる可能性も否定できません。 さらに、将来的にクルマの売却や廃車の手続きが煩雑になるおそれがあります。こうしたリスクを避けるためにも、使用実態に合わせて名義変更することが重要です。 クルマの使用者が変わるなら名義変更は原則必要 免許返納後、主な使用者が自分以外の人になるのであれば、原則としてその使用者の名義に変更する必要があります。 これは、自動車賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険の契約、万が一の事故時の責任の所在を明確にするべきだからです。 クルマの所有者と使用者が異なる状態では、保険の適用範囲や税金の通知先などで混乱が生じる可能性があるため、実態に合わせて適切に名義変更しましょう。 実際に運転する人が異なる場合の保険の影響 クルマの所有者の名義と実際に運転する人が異なる場合、任意保険の契約内容に影響が出ることがあります。 任意保険は、主にクルマを運転する人である記名被保険者を基準に保険料が算出されます。そのため免許返納した方を記名被保険者のままにしておくと、ご家族が運転中に事故を起こした際に、運転者と保険の内容が一致しないため、十分な補償を受けられない可能性があります。 もし保険契約内容と使用実態が合致していない場合は、契約内容の変更や運転者限定の見直しなど、適切な対応が必要です。 親子間でクルマを譲渡する場合の名義変更は3つの手続きが必要 免許返納を機に、クルマを子どもや親族に譲るケースは少なくありません。親族関係者あっても、クルマを譲渡する際には法的な手続きとして車検証(自動車検査証)、自賠責保険、任意保険の名義変更が必要です。 車検証の名義変更に必要な書類と注意点 車検証の名義変更(移転登録)は、クルマの公的な所有者を変更する手続きです。免許返納後にクルマを譲渡する場合、この手続きは避けて通れません。必要書類を事前にしっかりと準備し、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。 ▼関連記事クルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 必要書類 車検証の名義変更の必要書類は、クルマを譲り渡す方(旧所有者)と譲り受ける方(新所有者)で異なります。 <旧所有者>・自動車検査証(車検証)の原本◎実印を押印した譲渡証明書・実印を押印した委任状 ※代理人が申請する場合・印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内 <新所有者>◎実印を押印した移転登録申請書★自動車検査証記入申請書・実印を押印した委任状 ※代理人が申請する場合・印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内★新所有者の住所を証明する書面の写し◎手数料納付書◎自動車税申告書★軽自動車税申告書◎自動車保管場所証明書(車庫証明) ※発行から1ヶ月以内 ◎ …… 普通自動車の名義変更にのみ必要な書類★ …… 軽自動車の名義変更にのみ必要な書類 車庫証明の有無 車庫証明(自動車保管場所証明書)は、原則として普通自動車の名義変更手続きで必要です。 車庫証明はクルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。申請・取得は新しい所有者の住所を管轄する警察署で行います。 なお、同居の親族間で譲渡する場合、クルマの保管場所に変更がない場合など、特定の条件下では車庫証明が不要です。 ▼関連記事車庫証明の発行にかかる期間は?有効期限や申請方法なども紹介車庫証明の取得にかかる費用は?支払い方法や取得の流れも紹介 手続き場所と受付時間 普通自動車の名義変更手続きは、原則として新しい所有者の住所を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)で行います。 一方、軽自動車の場合は、新しい使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。 これらの窓口は、一般的に平日の日中のみ開いており、受付時間も午前と午後に分かれているため注意が必要です。事前に管轄の窓口のWebサイトで受付時間を確認しましょう。 自賠責保険の名義変更手続き クルマを運転する際に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)も、クルマの所有者が変わる場合には名義変更が必要です。この手続きを忘れると、万が一の事故の際に保険金の請求がスムーズに行えないなどの不都合が生じる可能性があります。 必要書類と手続きの流れ 自賠責保険の名義変更は、加入している保険会社の窓口や郵送で行うことができます。 一般的に必要な書類は、保険会社が指定する「自賠責保険承認請求書」と「自賠責保険証明書の原本」です。加えて、譲渡意思の確認ができる書類として、旧所有者の実印が押された譲渡確認書類や、新旧所有者双方の本人確認書類などが求められます。 保険会社によって必要書類が異なる場合があるため、事前に保険会社に問い合わせて確認することをおすすめします。 手続き期間と注意点 自賠責保険の名義変更手続きにかかる期間は、保険会社や手続き方法によって異なりますが、窓口であれば即日、郵送であれば数日から1週間程度を見込んでおくとよいでしょう。 名義変更手続きを行わないまま事故が発生した場合、保険金の支払い不可や遅れにつながる可能性があります。また、車検を受ける際にも自賠責保険証明書が必要なため、名義変更手続きは早急に行う必要があります。 任意保険の名義変更と等級引き継ぎ 任意保険も、クルマの譲渡と同時に名義変更や契約内容の見直しを行う必要があります。保険の等級は、条件を満たせば新所有者に引き継ぐことができます。 等級引き継ぎの条件や手続きについて詳しく見ていきましょう。 等級の引き継ぎの可否 任意保険の等級は、一定の条件を満たせば配偶者や同居の親族への引き継ぎが可能です。免許返納を機にクルマを同居の子どもに譲る際には、この制度を利用できる可能性が高いでしょう。 等級が高ければ高いほど保険料の割引率も大きくなるため、引き継ぎが可能かどうかは必ず保険会社に確認しましょう。た可否< だし、友人や別居の親族など、前述の範囲外への等級引き継ぎは認められていません。引継ぎ可能・不可のケースの例を紹介します。 引き継ぎ可能なケース 引き継ぎ不可なケース ・保険会社を変更する場合・契約期間中に事故があった場合(事故内容に応じて等級ダウン反映)z・クルマを買い替えた場合(車両入替手続きが必要)・記名被保険者またはその配偶者と同居している親族への引き継ぎ・配偶者への引き継ぎ(別居でも可)・クルマを一時的に手放す場合(廃車・譲渡・返還など、所定の手続きが必要)・2台目以降の車を購入する場合(条件付き)・一定期間の海外渡航後に再契約する場合(条件付き) ・別居の親族(配偶者を除く)・別居の未婚の子・友人や同居していない知人への引き継ぎ・記名被保険者またはその配偶者と関係のない人物への引き継ぎ 保険会社によって条件が異なるため、事前に確認しましょう。 ▼関連記事免許返納で自動車保険の等級を引き継ぐメリットは?押さえるべきポイントについても解説! 必要書類と手続きの流れ 任意保険の名義変更や等級引き継ぎの手続きは、加入している保険会社に連絡して行います。 まずは保険会社に連絡し、任意保険の名義変更に必要な書類を確認しましょう。 具体的な必要書類は保険会社によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。 ・保険証券・名義変更後の車検証のコピー・新記名被保険者の運転免許証のコピー・旧記名被保険者と新記名被保険者の関係を証明する書類 ※等級を引き継ぐ場合 必要書類が揃ったなら、保険会社へ引き継ぎ後の「保険契約者」「記名被保険者」「車輌所有者」を伝え、名義変更の手続きを進めてもらいましょう。 免許返納の方法と手続きの流れ 免許返納の手続きは、クルマの名義変更より前に行うのが理想的です。スムーズに返納を済ませられるよう、手続きの流れについても理解しておきましょう。 返納手順 運転免許証の自主返納は、本人の住所地を管轄する運転免許センターや警察署の窓口で申請できます。手続きは窓口で申請書に必要事項を記入し、免許証とともに提出すれば完了します。 ▼関連記事免許返納する時の手続きとは?免許返納するメリットについて解説 代理人による返納も可能 本人が病気や怪我などの理由で窓口に出向くのが難しい場合には、代理人による免許返納の申請も認められています。 代理人が申請する場合、本人の運転免許証、委任状や申立書、代理人の本人確認書類などが必要です。 必要書類や条件は都道府県によって異なる場合があるため、事前に必ず管轄の警察署や運転免許センターに問い合わせて確認してください。 ▼関連記事免許返納の代理申請は可能?手続きの場所や必要なものも解説 運転経歴証明書の申請もあわせて検討する 免許返納時に希望すれば「運転経歴証明書」の交付を申請することができます。 これは過去の運転経歴を証明する公的な書類であり、身分証明書として利用できるほか、公共交通機関の割引や提携店舗での割引など、さまざまな特典を受けられる場合があります。 申請は免許返納後5年以内であれば可能です。交付には手数料がかかりますがメリットも多いため、免許返納の際にはあわせて申請を検討してみましょう。 ▼関連記事免許返納後にもらえる運転経歴証明書とは?受け取り方法も解説運転経歴証明書を取得するメリットは?地域別特典の内容や申請方法を紹介 まとめ 免許返納後もクルマの名義をそのままにしておくことには、自動車税の支払いや事故時の責任など、いくつかのリスクが伴います。特に、他の誰かがクルマに乗る場合は、車検証、自賠責保険、任意保険のそれぞれについて、速やかに名義変更の手続きを行うことが重要です。 もし、免許返納を機にクルマ自体が不要になるのであれば、売却も有効な選択肢の1つです。クルマを所有している間は維持費がかかり続けるだけでなく、時間とともに価値も下がっていきます。家族への譲渡や買取業者への売却を含め、クルマを手放す適切な方法を検討しましょう。

今後価値が高騰し、値上がりしそうな旧車・ネオクラシックカー15選
クルマの購入時に気になるのが、資産としての価値。せっかくクルマを買うなら、価値が上がって高くなっていったほうがいいですよね。多くのクルマが購入すると時間の経過とともに価値が下がっていく一方で、一部のクルマは旧車市場で価値が上がり高額で取引されることがあります。そこで今後、価値が上がる可能性のある日本車と輸入車のクラシックカーを予想してみましょう。 ■旧車の価格はなぜ高騰するのか? 旧車が値上がりするのには、いくつかの要因がありますので整理してみましょう。 ●旧車市場での需要: 日本はもちろん海外でも旧車は売り買いされています。需要が多ければ、そのぶんだけ価値が上がっていきます。国外では、とりわけ北アメリカやヨーロッパで旧車市場が活況です。 ●希少価値: 新車としての販売台数が少ない車種や、販売終了して久しい車種は、時間の経過とともに故障や廃車などにより市場に流通する台数が減少していくため希少性が高まっていきます。そのなかで、旧車愛好家に人気があるクルマは価格が上昇していきます。 ●カスタムやレストア: クルマをカスタムやレストアして乗るオーナーがいます。自分の所有物を最大限に楽しむことは素晴らしいですが、クルマ本来の状態は失われていきます。オリジナルの状態に近いほうが、旧車としては価値が高まっていく傾向があります。しかし、時間の経過とともにオーナーが変わり、オリジナルの状態が失われる可能性がでてきます。 ●規制の影響: 国によっては、排ガスや環境の規制が厳しくなり、登録が困難になる前に憧れの旧車を購入する動きが見られます。 またアメリカには、製造から25年が経過すると右ハンドルのクルマをそのまま輸入してクラシックカーとして登録できる「25年ルール」があります。そのため、25年を境にアメリカで日本の旧車の需要が増えるのです。 ●知名度: 「レースに出場した」「映画に登場した」「ゲーム化された」など脚光を浴びると、人気を集めることがあります。 ■価値が上がりそうな日本車 ●1.日産 スカイライン GT-R(R32・R33・R34): スカイライン GT-Rシリーズは根強い人気があり、特にR32・R33・R34のモデルは今後も価値が上がる可能性が高いでしょう。R34は海外からの需要が高まっており、もともと生産台数が少ないため、価格が上昇することが考えられます。 ●2.日産 シルビア(S13・S14・S15): シルビアは、ドリフトカーとして認知されていてコアなファンがいます。年々、コンディションが良好なものが少なくなっています。S13やS14もそうですが、とりわけS15は価値の上昇が期待できます。 ●3.日産 フェアレディZ(Z31): 日産のスポーツカーで、海外でもよく知られています。グランドツーリング志向が強く、ターボチャージャー搭載モデルは特に人気です。 ●4.ホンダ NSX(NA1・NA2): 初代NSXはホンダが誇るミッドシップスポーツカーで、フェラーリにも引けを取らない技術と性能を誇りました。アルミボディやVTECエンジンといった先進的な技術が採用され、開発には伝説のF1レーサーであるアイルトン・セナも参加しました。 ●5.ホンダ プレリュード: デザインが洗練されている5代目ホンダ プレリュード。ステアリングにトルクベクタリングを採用するなど、先進技術が注目を集めました。若いコレクターにも人気があります。 ●6.トヨタ スープラ(A80): トヨタのA80スープラは、90年代の国産スポーツカーの中でも特に人気が高いモデルです。パワーと耐久性に優れる2JZ-GTEエンジン搭載車は、人気があります。北米市場での需要が高まっており、価格が上昇しています。 ●7.マツダ RX-7(FD3S): RX-7 FD3S型は、ロータリーエンジンを搭載したスポーツカーです。特徴的な設計と独特の走りで、ファンを魅了しています。パーツの入手が困難な場合もありますが、根強く支持されています。 ●8.三菱 ランサーエボリューション(エボV~エボIX): 三菱のラリーカーとして名を馳せたランサーエボリューションシリーズ。エボVからエボIXまでのモデルが、特に人気です。高性能な4WDターボを誇り、世界ラリー選手権で認知度を高めました。 ●9.スバル インプレッサ WRX STI(GC8・GDB): スバルのインプレッサ WRX STIは、ターボエンジンを搭載したAWDスポーツカーです。GC8(初代)とGDB(2代目)は軽量で扱いやすく、ファンに人気です。 ■価値が上がりそうな輸入車 ●11.デロリアン DMC-12: 映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で有名になったデロリアン DMC-12。ステンレス鋼のボディは、一目ですぐわかるデザインです。ノスタルジーの高まりにより、近年になって価格が高騰しています。 ●12.フェラーリ 400・412: 4シータークーペであるフェラーリ 400と412。優雅なデザインで、V12エンジンを搭載しています。創業者エンツォ・フェラーリの最後のモデルとして近年、評価が高まっています。 ●13.ボルボ P1800: ボルボ初のスポーツクーペであるP1800は、高い耐久性もさることながら絶妙なフォルムのデザインがファンを唸らせます。イギリスのテレビドラマ『セイント 天国野郎』で主演のロジャー・ムーアが運転したことでも知られ、若者に人気です。 ●14.BMW ミニ クーパーS: BMWが復活させた初代ミニ クーパーSは、クラシックな外観ながらスポーティーな走行性能があります。近年、緩やかに価値が上がってきています。 ●15.フォード ブロンコ II: 約四半世紀ぶりとなる2020年にフォードがブロンコを復活させました。これに伴い、3ドア ワゴンのフォード ブロンコ IIの人気が上昇しています。価格帯が手頃なことから、若者にも人気があります。今後も需要が見込まれているため、価値が上昇すると見られています。 ■まとめ このなかにお目当ての旧車はありましたか。クルマを買うのには、いろいろな理由があるでしょうが、自分の利用ニーズにあっているものを選びたいものです。そして所有して乗っているうちに価値が目減りしていくどころか、その逆に高騰したらこんなに嬉しいことはないですよね。 [画像/Toyota,Nissan,Honda,Mazda,Mitsubishi,Volvo,BMW MINI,Ford・ライター/Takuya Nagata]

日産 ER34スカイラインのD1での活躍を振り返る! 進化するGT-R化についても詳しく紹介
スカイラインといえば「GT-R」のイメージですが、プロドライバーによるドリフト競技「D1 GRAND PRIX」で注目を浴びたのはER34です。また、GT-Rが極端に高騰したことを背景に、GT-R仕様にカスタマイズする文化も生まれました。 目的によってはGT-R以上に魅力のあるER34スカイラインについて、D1での活躍を中心に詳しくみていきましょう。 ドライバーの個性とともに異彩を放ったER34スカイライン ER34のD1ドライバーといえば、博多弁丸出しの独特な口調とひょうきんなキャラクターで人気を博した野村謙氏です。黎明期を支えたレジェンドドライバーとして、現在もD1を中心に各方面で活躍しています。 野村氏のキャラクターとともに、強烈な個性を発揮したER34スカイラインのD1での活躍を振り返ってみましょう。 D1初年度からBLITZのドライバーとして参戦 ノムケンこと野村謙氏は、D1初年度の2001年からBLITZのER34スカイラインで参戦します。しかも、使用したのは4ドアモデルで、小柄なご本人とのコントラストが印象的でした。 大量のタイヤスモークをあげるドリフトは、大柄なボディと相まって迫力満点。「白煙番長」の異名で呼ばれ、個性的なドライビングスタイルを確立しました。 無冠ながら節目での印象的な活躍 D1のレジェンドドライバーとも評される野村氏ですが、実はシリーズチャンピオンの獲得経験はありません。しかし、1ポイント差の激闘やアメリカ開催のエキシビション戦での勝利など、印象に残る名勝負を数多く繰り広げました。 参戦当初の2001~2003年までは、迫力のある走りとは裏腹に準優勝が最高成績でした。マシンの完成度が向上するとともに、野村氏の実力が発揮されたのが2004年シーズン以降です。2004年仕様のマシンが投入された第2戦SUGOでは追走で強さをみせ、続く第3戦エビスサーキットで念願の初優勝を果たします。 さらに、2006年にはシーケンシャルミッションを投入するなどブラッシュアップを図り、シーズン最多タイの2勝を挙げました。初のシリーズタイトル獲得の期待もかかりましたが、ライバルの熊久保信重選手に僅か1ポイント差で破れ、シーズン2位という結果になりました。 ER34スカイラインでとことん楽しむ R34型スカイラインといえば、「GT-R」の人気が高いことは言うまでもありません。しかし、野村氏がD1で走らせたER34も、スポーツカーファンから高く評価されています。以前は難しかったGT-R化のハードルも下がり、ますます注目を集めているモデルです。 ここでは、そんなER34の魅力とトレンドを紹介します。 スポーツ走行ならGT-Rよりも楽しめる 絶対的な性能面では、ER34よりもBNR34(GT-R)に軍配があがります。アテーサによって高度に制御された4WDシステム、RB26DETTによる圧倒的なパワーはER34にはありません。しかし、ドリフトはもちろん、手足のようにクルマを操る感覚を楽しむという意味では、ER34は魅力的なモデルです。また、GT-Rよりも車重が軽いことも、スポーツ走行を楽しむうえでは大きなアドバンテージです。 さらに、性能を突き詰めたGT-Rではなく、あえてER34を選ぶことで自分好みにセッティングを仕上げられるのも魅力といえるでしょう。 定番のGT-R仕様はリーズナブルに進化 GT-R仕様へのカスタマイズは、ER34の定番メニューです。実はER34の人気の高まりから、最近では少しトレンドが変わってきています。以前は純正パーツの流用がおもな手段だったため、価格の高さや入手の難しさがネックでした。しかし、現在では多くの社外パーツがそろってきているため、比較的リーズナブルにGT-R化が可能です。 たとえば、GT-R化をする際に欠かせない、リアフェンダーの整形。これまでは、リアフェンダーをカットして、GT-Rのような張り出す形に加工していました。作業に手間がかかる分コストは高く、さらにフェンダーをカットすると修復歴ありになってしまいます。しかし、現在では貼り付けるタイプのFRP製のリアフェンダーが登場し、車輌本体を加工することなく装着できるようになりました。 D1の夢は息子の野村圭市選手が引き継ぐ 車重が重くドリフト競技では不利とされるER34ですが、大柄でホイールベースの長い車体がドリフト姿勢でコーナーを駆け抜ける姿は迫力満点です。ER34のよさを活かした豪快なドリフトでD1を盛り上げた野村氏ですが、2018年に惜しまれつつ引退をしました。 迫力のあるドリフトが見られなくなるかに思われましたが、入れ替わるように息子の野村圭市選手がER34でD1(当初はLIGHTS)に参戦しています。D1史上初の2世ドライバーとして、2ドアながらER34で現在も活躍中です。父が果たせなかったシリーズタイトルを、息子の圭市選手が獲得できるのか今後も注目していきましょう。

車検が満期日の2ヶ月前から受けられるように!改正の背景やメリットを解説
2024年6月、国土交通省は道路運送車両法施行規則を改正し、車検(自動車検査)を受けられる期間を延長することを発表しました。 今回の改正により、2025年4月1日からは車検を受けられる期間が満了日前の1ヶ月間(離島は2ヶ月)から2ヶ月間に延長されます。 この記事では、車検を受けられる期間が延長される背景やメリット、デメリットなどについて詳しく解説します。 車検は有効期間満了日の2ヶ月前から受けられるようになった これまでは、車検証の有効期限が満了する日の1ヶ月前(離島は2ヶ月前)から車検を受ける人がほとんどでした。この期間に車検を受けると、新しい車検証の有効期間が「旧車検証の期限が満了する日から2年」となるためです。 満了日の1ヶ月よりも前に車検を受けることもできましたが、新しい有効期間が「車検を受けた日から2年間」となるため、残りの有効期限分だけ損をする仕組みでした。 2025年4月1日以降は、有効期限満了日の2ヶ月前から車検を受けても残りの有効期間が失われないようになります。また、今回の改正にともない自賠責保険の更新手続きができる期間についても、満期日の1ヶ月前から2ヶ月前に延長されました。 以下では制度変更の背景や改正前後の違いを詳しく解説します。 制度変更の背景 車検を受けられる期間が延長される背景にあるのは、年度末に集中する車検需要です。 国土交通省の発表によると、2019年〜2023年の5年間における月別の車検台数は以下のとおりです。 画像引用:国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます~年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします~」 3月に車検を受ける車輌の台数は約389万台と他の月に比べて突出しており、月平均の約281万台も大きく上回っています。 3月に車検を受ける人が殺到すると、整備工場やディーラー、車検専門の予約が取りにくくなります。また、自動車整備士の残業や休日出勤が増加するという問題も生じていました。 そこで、年度末に車検の需要が過度に集中しないようにするために、道路運送車両法施行規則が改正され、車検の有効期間満了日2ヶ月前から受検できるようになりました。 改正前と改正後の違い 改正後は、有効期限満了日の2ヶ月前から満了日までの間に車検を受けた場合でも、新しい車検証の有効期間が「旧車検証の有効期限の2年後」となります。 たとえば、車検証の有効期限が7月30日、車検を受ける日が6月8日であるとしましょう。 改正前の場合、有効期限満了日の1ヶ月前よりも早いタイミングで受検することになるため、新しい有効期限は受検日である6月8日の2年後です。旧車検証の6月9日〜7月30日までの有効期間は失われてしまいます。 一方、改正後は5月30日以降に車検を受けると新しい車検証の有効期限は7月30日の2年後になるため、6月8日に受検しても残りの有効期間は失われません。 車検を2ヶ月前に受けるメリット 車検証の有効期限満了日の2ヶ月前から車検を受けられるようになったことには、以下のようなメリットがあると考えられます。 車検の予約が取りやすくなる 改正により、有効期限満了日の2ヶ月前から車検を受けられるようになったことで需要が集中する時期を避けやすくなります。 たとえば、車検証の有効期限が3月下旬の場合、車検を受ける人が比較的少ない1月の下旬に受検することも可能です。 混雑する時期を避けられると、仕事や旅行などの予定に合わせて柔軟に車検の日程を調整しやすくなります。 クルマにトラブルが発覚した際も対処しやすい 車検の際、クルマに不具合が発覚すると修理や部品の取り寄せなどに時間がかかることがあります。有効期限までにクルマが車検に通過できる基準を満たす状態にならないと「車検切れ」とみなされ公道を走行できなくなります。 有効期限満了日の2ヶ月前に車検を受ける場合、時間的な余裕があるため、万が一クルマに不具合が見つかっても対処しやすいでしょう。 代車を手配しやすくなる 車検を受けている間、通勤やお買い物、子どもの送り迎えなどでクルマが必要な場合は代車を借りることが可能です。ただし、車検を受ける人の数だけ代車が用意されているとは限らず、混雑する時期は借りられない場合もあります。 繁忙期を避けて車検を受けることで、代車を確保しやすくなるでしょう。 車検費用を分散できる 車検を受けられる期間の延長にあわせて、自賠責保険の更新手続きも満期日の2ヶ月前からできるようになったことで、費用負担を分散させやすくなりました。 車検を受けるときに自賠責保険の更新手続きをするケースがほとんどなため、車検費用や部品の交換費用などとあわせて保険料を支払います。 2回目以降の車検の有効期間は原則として2年間のため、自賠責保険の契約期間もそれに合わせて24ヶ月や25ヶ月とするのが一般的です。その場合の保険料は約1万8,000万円です。 改正後は、自賠責保険の満期日の2ヶ月前に更新をし、その1ヶ月ほど後に車検を受けて保険料とその他の車検費用を別々に支払えば、1回あたりの負担を軽減できます。 車検を2ヶ月前に受けるデメリット・注意点 車検を2ヶ月前に受けるデメリットと注意点は、以下のとおりです。 車検費用の支払い時期が早まる 車検を2ヶ月前に受けると費用を支払うタイミングが前回よりも前倒しになります。 車検を受ける際は、基本料や自賠責保険料の他にも、自動車重量税や部品交換・整備費用などで数万〜20万円程度の費用がかかります。 満了日の2ヶ月前に車検を受ける場合は入念に資金計画を立てておきましょう。 必ず予約が取れるとは限らない 車検の有効期限が4月の場合、改正後はその2ヶ月前の2月から受検できるようになります。 しかし、国土交通省の発表によると2019年〜2023年の5年間で2月に車検を受けたクルマの平均台数は300万台弱であり、6月や7月と並び3月の次に多い水準です。 有効期限満了日の2ヶ月前であっても希望する日に車検を受けられるとは限らないため、スケジュールに余裕をもって予約することをおすすめします。 参考:国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます~年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします~」 かえって繁忙期と重なることがある 満了日の2ヶ月前が混雑する時期と重なる場合は、予約が取りにくい可能性があります。 たとえば、車検証の有効期限が5月の場合、その2ヶ月前は3月となり繁忙期と重なるため、満了日の1ヶ月前である4月のほうが車検の予約は取りやすいでしょう。 2025年3月31日以前に車検を受けると有効期限が短縮される 車検証の有効期限満了日が2025年4月1日以降でも、車検を受けるタイミングが3月31日以前になると車検証の残りの有効期間が失われてしまいます。 たとえば、有効期限満了日が5月20日の場合、3月23日に車検を受けると3月24日〜5月20日までの有効期間が消滅します。一方、4月3日に車検を受ける場合、残りの車検期間は短縮されません。 まとめ 2025年4月1日以降は、満了日を迎える前の2ヶ月間に車検を受けても残りの有効期間が失われなくなるため、希望日に車検の予約を取りやすくなるでしょう。 また、自賠責保険の更新手続きも満期日の2ヶ月前からできるようになるため、車検の際にかかる費用の支払いを分散しやすくなります。 ただし、前倒しで車検を受けると費用を支払うタイミングが早まるため、入念に資金計画を立てる必要があります。有効期限満了日の2ヶ月前に車検の予約が必ず取れるとも限らないため、スケジュールに余裕をもって準備を始めましょう。
