「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
旧車の魅力と知識

不動の1位はあのモデル!ドイツ「Hナンバーとヒストリックカー」を深掘り!
ドイツでは、あえて古い年代のクラシックカーを好んで乗る人がとても多いのです。 筆者の住むベルリンでも例外はなく、街で見かけない日はありません。 クルマに限らず、歴史的建造物を現代に残して別の用途で再利用したり、アンティーク家具や骨董品も同様に人気があります。 古きよきものを大切にする文化が根付いているドイツならではともいえますが、中世ヨーロッパの風情が残る街並みに、クラシックカーはとても美しく映えます。 そんなクラシックカーの中でも「ヒストリックカー」と呼ばれる、特別なクラシックカーがあることを知っているでしょうか? 「ヒストリックカー」とは、製造年数が古く、状態の良さなどいくつかの条件を満たしたクラシックカーを指しますが、認定を受けたクルマには「Hナンバー」と呼ばれる専用ナンバープレートが与えられます。 「H」とはドイツ語の“Historisch(ヒストリック)”からきており、“歴史的”という意味を持ちます。 また、単に古いというだけでなく、税金や車検が優遇されるといった特典もあります。 世界的にEV化に注目が集まる2020年代においても「ヒストリックカー」の認定を受けるクルマが増え続けているドイツですが、そこにはどんな理由があるのでしょうか? 先に述べた古いものを大事にする文化や、税金の優遇以外にもメリットがあるのでしょうか? では、「ヒストリックカー」と「Hナンバー」について、詳しく深掘りしていきましょう。 ドイツにおける「ヒストリックカー」の定義とは? 「ヒストリックカー」の制度は、古き良きクルマを文化遺産として現世に残そうという目的のもと、1997年に導入されました。 製造から30年以上経過しており、オリジナルの状態を保持している、もしくは現代的に修復された状態の良いクルマのことを「ヒストリックカー」と呼びます。 「Hナンバー」とは? 「ヒストリックカー」には、正式名称「Kennzeichen historischer Fahrzeuge(歴史的工業遺産)」、通称「Hナンバー」と呼ばれる専用のプレートがついています。 見た目は普通のナンバープレートと変わりませんが、末尾にヒストリックの意味を記した「H」が入っているのが特徴です。 資格が得られる条件は? クラシックカーに限らず、どんなクルマであっても当然ではありますが、まず自動車保険に加入しており、車検が有効でなければなりません。 一般検査(StVZO第29条に基づく)と、専門家による車輌の整備状態や保存状態の査定を行ない、その証明となるクラシックカーレポートを取得する必要があります。 ボディ、フレーム、ドライブトレイン、ブレーキシステム、ホイール、タイヤ、電気システムなどが主な査定対象となります。 必要書類をすべて揃えて登録事務所へ提出し、基準を満たしていた場合に限り、「Hナンバー」が取得できます。 どんなメリットが? 「Hナンバー」のついたヒストリックカーは、税金や車検などが優遇されるといった特別なメリットがあります。 所有者は文化財保護者として扱われ、排気量にかかわらず、年間の自動車税が一律で191.73ユーロ(約30,000円)に抑えることができます。 また、都市ごとに設定されている環境規制にしばられることがありません。 さらに「シーズンナンバー」という使用期間限定ナンバーも用意されています。 これは「Hナンバー」と「シーズンナンバー」を組み合わせて年間の税金を12ヵ月で割り、使用期間分のみの税金を支払えばいい仕組みです。 温暖な季節にしか乗らないなど、通年使用しないオーナーにとってはありがたいですね。 人気の「ヒストリックカー」は? ドイツにおける不動の1位ともいえるのが、やはりメルセデス・ベンツの「W123」シリーズです。 連邦自動車交通局(KBA)が2022年に発表した結果ですが、街中でもいちばんよく見かけます。 続く2位は、同じくドイツメーカーで、街でもよく見かけるフォルクスワーゲン ビートル。 「ヒストリックカー」の登録比率が78%となっており、所有者の8割近くが「Hナンバー」を取得していることがわかります。 3位は、同じくフォルクスワーゲンからバスがランクイン。 通称ワーゲンバスと呼ばれており、初代の「T1」から「T2」「T3」「T4」とシリーズ化され、モデルチェンジを繰り返してきました。 ツートーンカラーのレトロなデザインが愛らしい「T1」「T2」が最も人気です。 上位3位以外では、ポルシェがランクインしており、「ヒストリックカー」においても圧倒的にドイツの国産車が人気のようです。 EV化が進むなかにおける「ヒストリックカー」の立ち位置 ドイツでは、温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指していることから、2030年までにEVの登録台数を最低1,500万台にするといった高い目標を掲げています。 2022年にドイツ自動車産業連合会(VDA)が発表した結果によると、バッテリー式電気自動車(BEV)とプラグインハイブリッド車(PHEV)が88万4,576台(42.9%増)という、脅威の台数を叩き出しています。 しかし、ここまで増えた要因の1つは、4万ユーロ以下のEVに対して9,000ユーロの補助金が出ていたこと。 経済問題などから補助金が削減されて以降、EV市場は縮小傾向にあり、大手のフォルクスワーゲンは減産にシフトしました。 対する「ヒストリックカー」ですが、「Hナンバー」制度が設けられた1997年当時の保有台数は、翌年1998年までの間でわずか18,000台でした。 その後、2008年には16万台に増え、2020年代に入ると50万台以上にも増えました。 ヒストリック人気の裏では、フォルクスワーゲンのビートルがEVに改造され販売されるという、これまでにない動きを見せています。 名車と呼ばれるクラシックカーたちが、現代のライフスタイルや環境問題改善のために変わっていくのは避けられないのかもしれません。 今後、それぞれの台数がどのように変化していくか注目していきたいですね。 [ライター・Kana / 画像・Kana, Mercedes-benz]
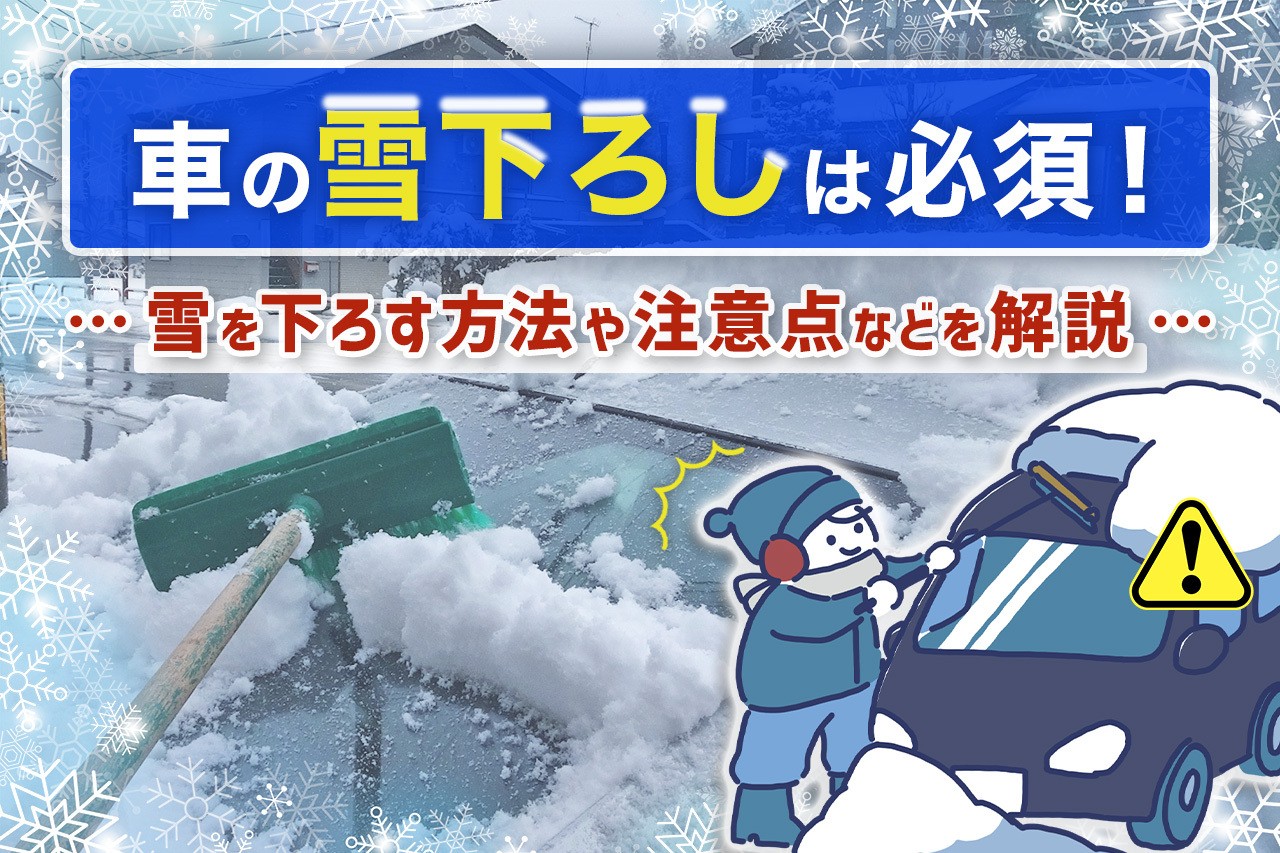
車の雪下ろしは必須!雪を下ろす方法や注意点などを解説
地域によって程度は異なりますが、冬になると雪が降ったり積もったりします。また、屋根がない駐車場に車を止めているときに雪が降れば、車の上にも雪が積もります。車に降り積もった雪は、運転する前に必ず下ろさなければなりません。 今回は、車の雪下ろしが必要な理由、雪下ろしの方法、注意点などを解説します。雪国での生活を始める人はもちろん、休暇を利用して雪が降る地域に出かける方も参考にしてみてください。 なぜ雪下ろしが必要なのか 雪が降り積もっている車を動かすときは、必ず雪下ろしをしてから動かしましょう。 雪国で生活している方や雪が降る場所へ出かけたことがある方なら当たり前のように行っていることですが、はじめて雪国で生活する人や普段雪が降り積もることがない地域に住んでいる人にとっては疑問に感じるかもしれません。 まずは、なぜ車の雪下ろしが必要なのか詳しく解説します。 雪下ろしをしないで運転するとどうなる? 車に降り積もった雪を下ろさずに車を動かしてしまうと、走行中や加速・減速をした時にドサッと雪が落ち、後続車に迷惑がかかったり視界が塞がれてしまうため大変危険です。 少しの雪なら大丈夫ではないかと思う方もいるかもしれませんが、油断は禁物です。少量であっても、走行中に勢いよくまとまった雪が飛んでいくと、大きな事故やトラブルに発展する可能性があります。 そのため、車に積もった雪は必ず下ろしてから運転しましょう。 雪下ろしをせずに放置するとどうなる? 雪下ろしをせずに放置するのも危険です。雪は水や氷より軽いものの、数メートルの高さまで降り積もると非常に重たくなります。 高く積み上がった雪の重さに車が耐えられなくなると、ルーフやボンネットがへこみます。そのため、雪下ろしをせずに放置するのは非常に危険なのです。 地域によって雪の質が違う 雪は、地域によって質が異なります。サラサラな雪が降る地域もあれば、水分を多く含んだシャーベット状の雪が降るところもあります。 この雪の質の違いは、重さの違いともいえるでしょう。降り積もる雪がサラサラであれば重さは軽く、水分を含むシャーベット状であれば重いです。このように雪の質によって雪の重さ、つまり車にかかる重量が異なるため、雪下ろしは定期的に行ったほうがよいでしょう。 雪下ろしの基本的な方法 車の雪下ろしをするときは、スノーブラシやスノースクレーパーなどを使います。また、道路の雪を除雪するためのスコップも用意しておくとよいでしょう。 ここからは、車の雪下ろしの基本的な手順を紹介します。 雪下ろしの手順 雪下ろしは次の順番で行います。 1.車を出すための通り道をスコップで作り出す2.車に積もった雪を大まかに下ろす(ルーフ→フロントガラス・リヤガラス→ボンネット→トランクの順に下ろす。雪は車体の左右に落とす)3.運転席まわり(ドアやルーフなど)の雪を取り除きエンジンをかけて暖房をつける(マフラー周辺に雪が積もっている場合はマフラー付近の雪を取り除く)4.車に積もった雪をしっかりと下ろす(1番目と同様に車の左右に雪を下ろす) 雪下ろしの際の注意点 車に積もった雪は車体の左右に落としましょう。 車の前後に雪を下ろしてしまうと、車を出せなくなったり、マフラーが塞がり一酸化炭素中毒になったりする可能性があります。このようなことに気をつけながら車の雪下ろしをしましょう。 雪下ろしで車に傷をつけないコツ 雪下ろしをするときは、車を傷つけないよう注意しましょう。ここからは、車の雪下ろしをする時に車体を傷つけないようにするコツを紹介します。 雪下ろしで傷がつく原因 まず、車の雪下ろしをする時に傷がついてしまう原因について知ることが大切です。雪下ろしの際に車が傷つく原因として、主に次の2つが挙げられます。 ・車に付着した砂やホコリと雪の摩擦で傷がつく・スノーブラシやスノースクレーパーが車体に当たって傷がつく 傷をつけない雪下ろしのポイント 雪下ろしの際に車に傷がついてしまう原因がわかったところで、車に傷をつけないためのポイントを紹介します。そのポイントは次の2つです。 ・雪が降る前に車の砂やホコリを洗い流しておく(コーティングをかけておくと更によい)・ボディに付着している雪をスノーブラシやスノースクレーパーで下ろす時はマイクロファイバークロスなどで硬い部分を覆う この2点に気をつけるだけでも、雪下ろしするときに車に傷がつきにくくなります。 雪下ろしに必要な道具と保管場所 雪下ろしする際には次の3つの道具を用意しておくとよいでしょう。 ・スノーブラシやスノースクレーパー・スコップ・マイクロファイバークロス また、雪が降ることがわかっている場合は、あらかじめ積雪対策をしておくとよいでしょう。主な積雪対策は次のとおりです。 ・屋根がある場所に車を止める・屋根がない場所に止める時はカバーをかける このような道具の準備や積雪対策をしておくと、雪下ろしが楽になります。 突然雪が積もった場合はどうする? ここまで、雪国での生活を前提に解説してきましたが、休暇を利用して出かける場合、運転中に雪が降ってきたりSA・PAで食事や休憩をしているときに車に雪が積もったりすることがあります。 もし、突然雪が降ってきたときは、どのようにすればよいのでしょうか。 突然雪が降り始めて積もったら、厚手のゴム手袋をして、ほうきやタオルなどを使って雪下ろしをしてから出発してください。雪下ろしの道具がないという理由で車に雪を積もらせたまま出かけることは厳禁です。 まとめ 雪は、車の運転において雨より気を使います。また、雪下ろしをせずに車を走らせるのは危険を伴います。そのため、わずかな積雪であっても雪下ろしを必ずしてから運転しましょう。

聖地巡礼!イタリアで元フィアットの工場に泊まってみた!
イタリアでは築年数が経っている建物を壊して新しいものを建てる、ということはあまりなく、古いものは綺麗に改装し使い続けるという建築文化が根付いている気がします。 したがって、由緒ある建物にもかかわらず、中に入ると近代的! でも、実は築年数が100年だったりすることがよくあります。 そんなイタリアで、なんとフィアットの元工場をホテルに改装し、誰でも宿泊することができるという素晴らしい場所がトリノにあるのです。 今回はそこに宿泊してきましたので、ホテルの様子を皆さまにお届けしたいと思います。 ■「NH Torino Lingotto Congress」について ホテルの名前は「NH トリノ リンゴット コングレス」。 こちらの建物についてまず少し紹介します。 こちらの建物は、当時フィアットグループ(現FCA)のもっともシンボリックな工場としてトリノに誕生しました。 その建物の屋上には、1919年に建設された1.5kmのテストトラックが併設されており、組み立てられた自動車のテストに使用されていました。 このテストトラックは今でも残されており、立ち入ることも可能です。 そこからフランスとの国境でもあるアルプス山脈を一望することができ、それを目的に来館する方もいらっしゃるようです。 工場が閉鎖されたのち、この建物はエンターテインメントと文化の発信地として再開発が行なわれ、ショッピングモールやホテル、美術館等が併設する施設として利用されることになりました。 リノベーションを手掛けたのは、関西国際空港のターミナルを設計したことでも有名なレンゾ・ピアノ氏。 ホテルは特に部屋にこだわりがない場合、比較的お財布にやさしい価格帯なので、私たちも連泊することに。 ホテル内にはレストランやスポーツジムもあり、充実した時間を過ごせること間違いなしです! ■ホテルへのアクセス方法について トリノ中心街の「Torino Porta Nuova」駅から直通電車で約10分の「Torino Lingotto Railway Station」で下車すると、駅はホテルにほぼ直結しています。 もちろんホテルには駐車場も完備されているので、クルマでアクセスすることも可能。 トリノの中心街に近いのも嬉しいポイントです。 ■ホテルの中は一体どんな感じ? さて、早速中に入ってみると、元工場だったとは想像がつかないくらい綺麗で近代的なホテルです。 エントランスを入ってすぐには、旧車の展示があります。 この展示車は常連のお客さまが飽きないようにでしょうか、定期的に変わるようです。 ホテルの中には竹林の中庭もあり、和洋折衷な一面も感じられました。 宿泊部屋も窓が非常に大きく、明るく清潔感のある部屋で、この部屋で製造されていた車輌が写されたポスターが壁に貼られていました。 ポスターにはクルマ乗る楽しそうな女性・・・ このポスターを見ながら、この部屋でこのクルマが作られていたのかと思うと、なぜでしょう、ノスタルジックな気持ちになりました。 ■このホテル宿泊者の特権はずばり?! 屋上にはテストトラックがあるのですが、お金を払えば誰でもアクセスすることが可能となっています。 ですがホテル宿泊者なら、いつでも無料でテストトラックに入場することができるんです! エレベーターで屋上に上ると、まずはカフェ兼展示物コーナーに行き着きました。 そのカフェを抜けると、さあ、お待ちかねのテストトラックが見えてきました! 屋上のテストトラックとは一体どんなものなのでしょうか?! 第一印象は、傾斜の効いたカーブの迫力がすごい・・・!でした。 ちなみにこの傾斜カーブに登ろうとしたところ、警備員さんに怒られてしまいました。 それもそのはず、人間が立てないくらいの傾斜になっているので、普通に危険です(汗)。 そして次に印象的だったのは屋上から見るアルプス山脈です。 こんな絶景の中、車輌の走行テストを行なっていたのですね。 今はカフェと化しているようですが、当時の司令塔も残されています。 トラックには当時の歴史を記した写真等が展示されているため、この施設が実際に工場であり、自分がいるところが本当にテストトラックであったことを実感させられました。 この建物がどのような目的で建てられ、どのような歴史を経て閉鎖することになったのか、展示物をみながら学習することもできます。 ところで皆さん、このクルマがどうやって屋上に上ってくるか想像つきますか? 私は下方の階から組み立てが始まり、徐々に上階に来て、最終的に出来上がった車輌が屋上にたどり着くのか?と想像しましたが、そうではないようです。 下記写真のように、クルマ用螺旋階段のようなものがあり、これで車輌が屋上まで到着するという構造でした! 日本では過去にも現在にもこのような工場またはテストトラックが存在していないと思うので、螺旋階段でクルマを屋上に持ってくるとは、なかなか想像がつきませんでした。 さすがイタリアです!洒落ていますよね。 ■最後に フィアットはイタリアが誇る自動車メーカーの一つで、イタリアでは誰からも愛される存在であると思います。 民衆とともにイタリアの歴史を刻んできた由緒あるブランドの建造物を壊すことなく、新たな形でこのような人々の憩いの場として利用されているのは、歴史を無駄にしない、正しい使われ方である、そう感じました。 トリノはピエモンテ州の首都で、イタリアで4番目に大きな都市。 1861年、イタリア全土が統一国家になった際に、最初の都市が置かれたのがトリノなのです。 このホテル以外にも、歴史的建造物や美食文化も(クルマに関する博物館ももちろん)充実しています! クルマを好きの方は絶対に楽しめるトリノ、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。 特にフィアットオーナーの聖地巡礼には欠かせない街ですよ! [ライター・画像 / PINO]

引っ越し後は車庫証明の変更が必要!そのままにするのがダメな理由や罰則は?
引っ越しによって住所が変わった場合は、クルマを購入したときと同様に車庫証明を取得する必要があります。取得しないまま放置すると、罰金を科される可能性があるため、必ず申請手続きを行いましょう。この記事では、引っ越し時の車庫証明の手続き方法や、取得しないまま放置するとどうなるかなどを紹介します。 車庫証明は引っ越し後に変更が必要 引っ越しをした際、車庫証明をそのままにしておくのはNGです。法律違反とみなされて罰金が科される場合があります。ここでは、引っ越し時に車庫証明を変更しなかった場合のペナルティと手続き期限について解説します。 住所変更しないと罰金が科されるおそれがある 引越し時の車庫証明手続きをしないと、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)違反となります。 (保管場所の変更届出等)第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知において証された保管場所の位置を変更したとき又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条1項 上記に違反すると、10万円の罰金が科せられます。 (罰則)第十七条3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条3項 なお、車庫法に違反した際は「刑事罰」とみなされます。スピード違反や駐車違反などの交通違反は「行政罰」に該当し、反則金を支払えば刑事責任は問われませんが、刑事罰では前科がつきます。なお、虚偽の保管場所を申告した場合は20万円以下の罰金を科せられる可能性があるため、あわせて気をつけましょう。 (罰則)第十七条2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条2項 15日以内に手続きが必要 車庫証明の住所変更手続きは、変更した日から15日以内と法律で決まっています。期限を超過すると、前述の通り10万円の罰金が科せられるため、余裕をもって手続きしましょう。 【普通車】車庫証明の住所変更の方法 引っ越し時の車庫証明の住所変更は、クルマを購入する際と同じように、保管場所の所在地を管轄する警察署の「交通課」で必要書類を提出して手続きします。事前に必要書類と手続きの具体的な流れについて把握しておくと、スムーズに住所変更できるでしょう。 車庫の要件 クルマを保管する車庫は、下記すべての要件を満たす必要があります。 ・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所・使用の本拠の位置から2kmを超えない・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させられる・自動車の全体を収容できる・保管場所として使用できる権原を持っている 1つでも要件を満たさない場合、車庫証明が取得できません。必ず確認しておきましょう。 参考:警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」 必要書類 引っ越し時の車庫証明の手続きをする際は、下記の書類を提出する必要があります。 ・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書・保管場所の配置図・所在図・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合 車庫証明手続きに必要な書類は警察署で入手できます。各警察署のWebサイトでも、PDFファイルをダウンロードできるため、警察署に出向く時間がない場合は活用してみてください。 <警察署Webサイト一例>保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察各種申請用紙 - 愛知県警察 手続きの流れ 車庫証明の住所変更の流れは、下記のとおりです。 保管場所の所在地を管轄する警察署に出向く 必要書類を準備したら、管轄の警察署に行きましょう。受付時間は都道府県により違いますが、おおむね平日の9時〜17時頃までです。なお、交通課に出向く前に警察署に隣接している交通安全協会に申請手数料分の収入印紙を購入します。申請手数料は都道府県によって異なり、2,500〜3,000円程度です。警察署によっては、交通課の窓口で収入印紙を購入できるケースもあるため、確認しましょう。 交通課の窓口に必要書類を提出 収入印紙を書類に貼り付けて提出します。書類に間違いがあった場合は訂正印を押して修正する必要があるため、認印を持参するとよいでしょう。 警察署に再度出向いて車庫証明を受け取る 車庫証明は申請してから3〜7日程度で交付されるため、再度警察署に行く必要があります。受取時は申請書類の控えを提出する必要があるため、紛失しないよう注意してください。 なお、同時に渡される「保管場所標章シール」は、車庫証明が交付された車であることを証明するものです。罰則はないものの、リアガラスに貼り付ける義務があるため、忘れないようにしましょう。 ▼関連記事はこちら車庫証明の取り方とは?取得の流れや必要書類などを解説 【軽自動車】保管場所届出の住所変更の方法 軽自動車は普通車と異なり、車庫証明の制度がないため、代わりに「保管場所届出」の手続きをする必要があります。ここでは、保管場所届出の申請に必要な書類や手続き内容を紹介します。 必要書類 保管場所届出の住所変更には、下記の書類が必要です。 ・自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書・保管場所の配置図・所在図・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合 普通車の車庫証明の住所変更に必要な書類とほとんど同じです。警察署の窓口で入手できるほか、公式WebサイトでもPDFファイルをダウンロードできます。 <警察署Webサイト一例>保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察各種申請用紙 - 愛知県警察 手続きの流れ 保管場所届出の住所変更の流れは下記のとおりです。 保管場所の所在地を管轄する警察署に出向く 普通車と同様に、書類が準備できたら管轄の警察署に出向きます。受付時間はおおむね平日の9時〜17時頃までです。交通課に行く前に警察署に隣接している交通安全協会で申請手数料分の収入印紙を購入します。保管場所届出の申請手数料は500円です。 交通課の窓口に必要書類を提出 収入印紙を書類に貼り付けてから提出します。書類に誤りがあると修正の際に訂正印が必要なため、認印を持参するとよいでしょう。 窓口で控えをもらう 書類提出後、当日中に窓口で控えと保管場所標章シールをもらって手続きは終了です。普通車の場合は交付までに数日かかりますが、軽自動車はその場で住所変更が完結します。 保管場所標章シールは、保管場所届出を申請したクルマであることを証明するものであるため、忘れずにリアガラスに貼り付けましょう。 軽自動車は手続きが不要な場合がある 軽自動車だと、地域によっては保管場所届出の手続き自体が不要な場合があります。たとえば、東京都では福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町など、一部の市区町村では保管場所を届け出る必要がありません。詳細は各都道府県の警察署の公式Webサイトで確認できるため、チェックしてみてください。 ▼関連記事はこちら軽自動車は車庫証明がいらないって本当?必要なケースも紹介 車庫証明の手続きは代理人でもOK 車庫証明の住所変更手続きは、代理人に依頼しても問題ありません。警察署は平日の日中しか窓口があいていないため、なかなか時間を確保できない方も多いはずです。自分での対応が難しい場合には、家族や知人に代理で手続きしてもらうとよいでしょう。なお、行政書士や自動車販売店への代行依頼も可能です。ただし、代行手数料がかかることに留意しましょう。 代理人に車庫証明の手続きを依頼する場合は、委任状を用意しておくと安心です。書類に不備があった際、委任状がないと代理人がその場で修正できません。可能な限り事前に準備しておきましょう。 ▼関連記事はこちら車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介 車庫証明の引っ越し後の手続きの注意点 引っ越し先が賃貸アパートやマンションであっても、または引越し後にクルマの保管場所が変わらなくても車庫証明の手続きは必要です。ここでは、引っ越し時の車庫証明の手続きにおける注意ポイントについて解説します。 賃貸アパート・マンションでも手続き必須 住まいが賃貸のアパートやマンションである場合も、車庫証明の手続きを行う必要があります。賃貸物件の敷地内の駐車スペースでも、別で借りている月極駐車場でも必須です。 ▼関連記事はこちら賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説 保管場所が変わらなくても手続き必須 近所に引っ越した場合には、クルマの保管場所が変わらないことがあるでしょう。同じ場所に駐車していても、引っ越し時には必ず車庫証明の手続きをしなければなりません。クルマの保管場所には「使用の本拠の位置(自宅)から保管場所まで2km以内」という条件があり、引越し後も条件を満たしている旨を警察署に証明する必要があるためです。 車庫証明以外で引っ越し時に必要な手続き 引越し時には、車庫証明のほかに「車検証」「ナンバープレート」「運転免許証」「保険(自賠責・任意)」の住所変更手続きも必要です。それぞれの変更手続きについて紹介します。 車検証 車検証上の住所と現住所が異なると、リコールの通知や自動車税の納付書が自宅に届かないため、住所を管轄する運輸支局で「住所変更」手続きを行う必要があります。車検証の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。 ■普通自動車1.車検証2.車庫証明書 ※有効期限内のもの3.住民票4.OCRシート(第1号様式)※押印欄は認印でも可5.手数料納付書6.自動車税申告書7.委任状 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ 4〜6は運輸支局で入手できるため、手続きする当日に記入しましょう。 また、普通自動車の車検証の住所変更には、350円の申請手数料が発生します。隣接している「整備振興会」で、350円分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。 印紙を貼り付けたら、必要書類を「検査登録事務所に」提出すると、変更後の車検証を発行してもらうことが可能です。発行後は内容に間違いがないかを、その場で確認しておきましょう。 ■軽自動車1.車検証2.車庫証明書3.住民票もしくは印鑑証明書4.自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)5.軽自動車税申告6.申請依頼書 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ 軽自動車の場合は、運輸支局ではなく住所を管轄する「軽自動車検査協会」で住所変更を行います。手数料は発生しないため、収入印紙は不要です。なお、4〜6は軽自動車検査協会で入手できます。 ▼関連記事はこちら車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 ナンバープレート 管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。たとえば、練馬区から足立区に引っ越した場合、練馬ナンバーから足立ナンバーに変わるためナンバープレートを変更する必要があります。管轄の運輸支局や軽自動車検査協会がわからない場合は、以下から確認してみましょう。 ・運輸支局・軽自動車検査協会 また、普通自動車の場合は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せる「封印」を運輸支局内で取り付ける必要があります。手続き時は、必ず車を運輸支局に持ち込みましょう。 なお、ナンバープレートを変更すると、今までの数字は引き継げません。変更前と同様の数字にしたい場合は「希望ナンバー」を申請する必要があります。 希望ナンバーは、交付までに4〜5日程度かかるため、日数を要することを把握しておきましょう。「・・・1」や「8888」、「・777」などの人気な数字は抽選制のため、当選するまで希望ナンバーは申請できません。 運転免許証 運転免許証上の住所と現住所が異なる場合、身分証明書として認められなくなるほか、運転免許更新の通知が自宅に届かなくなります。また、手続きをしないと、道路交通法第121条第1項第10号により、2万円以下の罰金または科料が科される可能性もあります。 参考:e-gov法令検索「道路交通法第121条第1項第10号」 そのため、新住所を管轄する警察署または運転免許センター・運転免許試験場で住所を変更しましょう。 運転免許証の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。 ・運転免許証・運転免許証記載事項変更届※窓口に備え付けられています・新住所が記載された下記5つの書類のいずれか1つ1.住民票の写し(マイナンバーの記載されていないもの)2.マイナンバーカード3.健康保険証4.在留カード5.公共料金の領収証や消印付き郵便物など 書類に不備がなければ、手続き自体は通常10分程度で完了します。提出後は新住所が免許証の裏面に記載されます。表面記載の住所が最新のものになるのは、次回更新時です。発行後は内容に間違いがないかを、必ずその場で確認しましょう。 なお、代理人による手続きも可能ですが、住民票に記載されている同一世帯者に限定される場合があります。都道府県によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。 保険(自賠責・任意) 引っ越しで住所が変わった際は、自賠責保険と任意保険(自動車保険)ともに契約している保険会社に連絡し、手続きを済ませる必要があります。なぜなら、住所変更を怠ると、万が一の事故の際に保険金が適切に支払われないなどの不都合が生じる可能性があるためです。 それぞれの手続き内容は、下表のとおりです。 手続き内容 自賠責保険 任意保険 方法 1.契約している保険会社の窓口に連絡2.専用Webサイト「One-JIBAI」でのオンライン手続き 1.契約している保険会社に直接連絡2.保険会社のWebサイト、電話窓口、または代理店を通じて手続き 必要書類 ・自動車損害賠償責任保険承認請求書(記入済み)・ナンバープレートまたは用途・種別、使用の本拠地の確認書類・専用封筒 保険会社により異なる(事前に確認が必要) 手続きの流れ 1.専用Webサイト「One-JIBAI」にアクセスしてログイン2.手続き内容を入力・申請3.自賠責保険証明書や必要書類をアップロード4.保険会社での確認後、手続き完了メールが送信5.新しい証明書の受取(郵送約2週間、オンライン4営業日後) 1. 契約している保険会社に連絡2. 住所変更に必要な書類を準備3. 手続き申請(Webサイト、電話、代理店)4. 契約内容変更手続き完了5. 変更後の保険証券等の受取 まとめ 引っ越しにより住所に変更があった場合は、クルマを購入するときと同様に、管轄の警察署で車庫証明手続きをする必要があります。住所が変更されてから15日以内に手続きしないと、10万円の罰金を科される可能性があるため期日に注意しましょう。 また、車庫証明に加えて車検証とナンバープレートの変更手続きも行う必要があります。警察署や運輸支局は、平日9時〜17時頃までしかあいていないため、都合が悪い場合は手続きできないケースもあるでしょう。 行政書士や自動車販売店などに、車庫証明や車検証の住所変更手続きなどの代行を依頼できる場合があります。都合がつかず手続きできない場合は、代行の依頼を検討してみてください。

ドイツ現地のガソリン価格事情とEVのニーズとは?
こんにちは!西尾菜々実です。 今回は、ドイツ在住の筆者の視点で「ドイツにおけるガソリンの価格事情」、そして「EVのニーズ」についてご紹介いたします。 ■ドイツでのガソリンの価格変動についての考察 ドイツではどのようにガソリンの価格が決められるのでしょうか? 筆者自身、昨年の夏からドイツへと移住しました。 それから1年以上が経過した現在、当時よりもガソリンの価格が高騰しています。 ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ドイツをはじめとするヨーロッパ全体で、内燃機関のクルマからEVへの置き換えの動きが加速しています。 それと当時に、環境に配慮した代替燃料への置き換えも進みつつあります。 ドイツはヨーロッパ各国と隣接していることもあり、他国からのエネルギー資源の供給を受けやすい位置にあります。 そんなドイツですら、ガソリンの価格をはじめ、光熱費も上昇傾向にあるのです。 ドイツ各地においてガソリン車とEVの比率が異なる事情もあり、ハイブリッド車が多い地域や県ではもとより、経済的な変動や時事的な環境によってガソリンの値段の変動が起こりやすいのです。 さらに、ヨーロッパでは他国からのガソリンの輸入が行われているため、近隣国との関係が価格にも影響を及ぼします。 ■ドイツにおけるガソリンの値段が高めな地域とは? 筆者がドイツ国内で気づいたことがあります。 同じ県内でも日本円にして1000円近い価格差があるガソリンスタンドを見掛けたことがあるのです。 基本的に、街や都市の中心部ではガソリンの価格は高め、郊外の方が安い傾向にあります。 このあたりは日本とあまり変わらないように感じます。 ■ドイツではどのようにEVが親しまれているのか? 「eオート」と呼ばれ親しまれているEV車。 ここドイツでは、ガソリンスタンドの敷地内にEV用の充電スタンドが置かれているケースはほとんどありません。 むしろ、スーパーや日用雑貨店の方が多い印象です。 買い物のついでに充電してください、ということなのだと推察します。 筆者が暮らす地域でも、EVが充電可能であることを示すマークが路上に描かれており、かわいらしい印象を受けました。 ■EVのニーズはどのように反映されるのか? ドイツではEVの導入について目標値が掲げられていることもあり、目にする機会も多い印象です。 古いクルマがEVに改造され、雑誌に掲載されるケースも増えつつあります。 旧東ドイツ製のトラバントがEVにコンバートされた例もあるほどです。 また、EVの商用利用が広がりつつあり、配達用の小型EVをはじめ、多種多様になりつつあるようです。 ■広がりを見せるドイツにおけるEVのニーズ 最新のEVをはじめ、クラシックカーをEVにコンバートしたり、デリバリーバンなどの配達用の小型EVなど、人々の生活に確実にEVが浸透しつつあることを日々実感しています。 これからもEV事情など、ドイツに暮らしているからこそお伝えできる情報を発信していきたいと思います。 [ライター・画像 / 西尾 菜々実]

ナンバープレートから個人情報は特定できる?特定できる情報を解説
道路を走行するには、必ずナンバープレートを取り付けなければなりません。さまざまな情報が記載されているため、第三者に個人情報が知られてしまわないか気になる方もいるでしょう。この記事では、ナンバープレートで個人を識別できるかどうかや、特定できる情報などを解説します。 ナンバープレートの記載内容 ナンバープレートの記載内容は、以下のとおりです。 地名 ナンバープレートには、クルマを登録している「運輸支局」や「自動車検査登録事務所」の所在地の地名が記載されています。たとえば、東京運輸支局で車を登録すると「品川」神奈川運輸支局の場合は「横浜」と、それぞれの地域によって区別されています。 2006年10月からは「ご当地ナンバー」が導入されたため、運輸支局や自動車検査登録事務所の所在地以外の地名が記載されているケースもあります。世田谷区に住んでいる場合、東京運輸支局で車を登録する必要があるため、本来であれば品川ナンバーが付与されます。ご当地ナンバーを申請すれば「世田谷」と記載されたナンバープレートを発行してもらうことも可能です。 分類番号 地名の隣の3桁の数字は、クルマの種類や用途を区別する分類番号です。たとえば、普通乗用車は「3ナンバー」、小型乗用車や軽自動車は「5ナンバー」と区別されています。 ひらがな ひらがなはクルマの用途を区別するためにあり、自家用車やレンタカー、事業用車両なのかを判別できます。 一連指定番号 一連指定番号とは、1〜9999までの4桁以下の数字のことです。4桁以下の数字は登録時にランダムで与えられます。ただし、「希望ナンバー」を申請すれば、好きな数字を自由に設定できます。 そもそも個人情報とは 個人情報とは、氏名や顔写真など生存している個人に関する情報です。生年月日や住所など、2つ以上の情報を組み合わせて、特定の個人を識別できるものも個人情報に含まれます。たとえば、「中村」や「鈴木」では識別できませんが、名前や住所などを組み合わせると、個人を特定できるため個人情報に該当します。また、運転免許証やパスポートなどの「個人識別番号」が含まれたものも個人情報です。 ナンバープレートからは、所有者を識別できる情報を得られないため、個人情報には含まれません。ただし、車検証や注文書には氏名や住所などが記載されているため、個人情報に該当します。 参考:日本自動車整備振興会連合会公式Webサイト「個人情報保護法Q&A」 ナンバープレートから個人情報は特定できる? クルマのナンバープレートから個人情報を特定することは可能です。ただし、正当な理由がなければ情報の開示ができないため、単に「所有者を知りたいからクルマに関する個人情報を開示してください」と請求しても断られるでしょう。 もし、ナンバープレートを元に個人情報を開示してもらわなければならない理由があるときは、「登録事項等証明書」を運輸支局に請求することで開示されます。 登録事項等証明書は、車の登録内容が記載されている書類です。車検証と同様の情報が記載されており、所有者の名前や住所、使用の本拠地などを特定できます。運輸支局内で入手できる「手数料納付書」と「OCR申請書(第3号様式)」を記入し、以下を窓口へ提示すれば発行してもらうことが可能です。 ・ナンバープレートの記載内容・車体番号下7桁・本人確認書類・請求理由 登録事項等証明書は、所有者に限らず誰でも請求できます。そのため、悪用される可能性がゼロではありません。 たとえば、自分の私有地に停められている放置車輌によって迷惑しているなど、個人情報を開示する正当な理由があると客観的に判断される場合は、第三者であってもクルマに関する個人情報を開示してもらうことができるでしょう。 ただし、実際には迷惑駐車がないのにそのように請求事由を記載することで、不正に取得される可能性があります。 なお、軽自動車の場合は登録事項等証明書ではなく「検査記録事項等証明書」を請求すれば、クルマの情報を確認できます。検査記録事項等証明書は、車検証に記載されている所有者しか請求できないため、紛失しない限り個人情報は特定されることはないでしょう ナンバープレートからわかる個人情報 ナンバープレートからは、クルマを登録している地域しか特定できません。ただし、クルマを登録している地域に加えて、他の情報と組み合わせた場合は個人情報が特定される可能性があります。 たとえば、よく利用している洗車場で洗車後の愛車の写真をSNSにアップしたときや、職場の制服を着た所有者も写り込んでいる場合などです。所有者の行動範囲や住んでいるおおよその地域、職場を特定される可能性があります。 ナンバープレートだけでは個人を識別できないものの、他の情報が加わると個人情報を特定される可能性があるため注意しましょう。 なお、警察署ではナンバープレートの記載内容を照会すると、所有者を特定できるシステムを保有しています。事件性がある場合に限り、ナンバープレートから所有者を特定します。 クルマをSNSにアップするときはナンバープレートを隠した方がよい クルマをSNSにアップするときは、ナンバープレートを隠したほうがよいでしょう。ナンバープレートには地名が記載されているため、他の情報が加われば住んでいるおおよその地域を特定される可能性があります。自分のクルマだけではなく、他人のクルマが写り込んだ場合にも、ナンバープレートを隠しクルマの持ち主に承諾を得たうえでアップするとトラブルに発展しにくいです。 現に、個人情報を保護する観点から「Googleのストリートビュー」に写っている車のナンバーには、ぼかしが入っています。建物や風景なども同時に写してSNSに写真をアップした場合は、ナンバープレートにスタンプやぼかしを入れて隠してから投稿しましょう。 まとめ ナンバープレートでは、個人を特定できる情報は得られないため、個人情報に該当しません。また、所有者の氏名や住所などが記載されている「登録事項等証明書」は、車体番号下7桁の明示や正当な請求理由が求められるため、第三者には容易に取得できません。 ただし、ナンバープレートからはクルマを登録している地域がわかるため、他の情報が加わった場合は個人情報を特定される可能性があります。SNSに車の写真をアップする場合は、ナンバープレートをスタンプで加工したり、ぼかしを入れたりして個人情報の流失を防止しましょう。

旧車ユーザーは三重苦に悩まされる?! 苦労を減らすためのポイントも解説
「人とは違う車に乗れる」「現在の車にはないスタイリング」など多くの魅力が詰まった旧車。しかし、旧車を保有するには、現行車にはない特有の苦労もあります。旧車に乗る際は、魅力だけではなくリスクも十分検討することが重要です。 そこで、オーナーを悩ませる旧車所有の苦労を紹介します。少しでも苦労をなくすためのポイントも紹介しているため、これから旧車を購入予定の方はぜひ参考にしてみてください。 旧車乗りが必ず直面する三重苦 旧車オーナーが直面する問題は、税金を含めた維持費用の高騰です。一方で、そもそもパーツが入手できないという、お金では解決できない問題もあります。 まずは旧車の所有により直面する、3つの問題点を詳しくみていきましょう。 税金が高い 旧車に乗るうえでオーナーの直接的な負担になるのが、毎年かかる自動車税と車検ごとの自動車重量税です。自動車税は、新車登録から13年が経過すると15%程度(ガソリン車の場合)上昇します。自動車重量税に関しては13年経過のあと、さらに18年経過でも加算されるため注意が必要です。 また、明確に旧車に乗ろうと思っていない方でも、13年経過時点での重課は車の購入時に意識しておく必要があります。日本の自動車の平均保有期間は7年というデータもあり、購入時点で6年が経過していれば、普通に車を保有しているだけでも13年に達してしまうためです。 故障リスクが高い 旧車最大の問題は、故障リスクが高い点です。自動車の実際の耐用年数は一概にはいえないものの、目安として法定耐用年数を参考にすると、普通車でも6年とされています。新車登録から10年どころか20年以上が経過する旧車であれば、ゴムや革製パーツの劣化、ポンプやコンプレッサーといった稼動部の故障リスクは避けられません。 旧車に乗る際は日常的に小まめなメンテナンスを行い、故障箇所をできるだけ早く見つけることが重要です。また、一ヶ所を修理すると他の部品に負荷がかかり、連鎖的に故障するケースも少なくありません。旧車を所有する場合は、小さな違和感にも常に気を配るようにしましょう。 パーツが入手しにくくなる 旧車が故障した場合、パーツが入手しにくい点にも気をつけましょう。税金の高くなる13〜18年程度であれば、国産メーカーなら入手可能です。しかし、ゴルフ 5を始めとした欧州車などでは部品の廃盤も始まっている車種もあります。 ただし、国産メーカーでも生産終了から10年を目安としているほか、ディーラーオプションなどは車輌の生産終了とともにパーツの生産も打ち切られるケースもあるため注意が必要です。 故障の発生しやすくなる旧車だけに、パーツの入手性は事前に確認しておきましょう。 旧車に乗るなら特に注意したいポイント 旧車を保有する以上、三重苦を完全になくすことはできません。しかし、いくつかのポイントに注意すれば、苦労を軽減できます。せっかく入手した旧車をできるだけ長く維持するために、ぜひ参考にしてください。 旧車を維持するうえで気をつけたいポイントを3つ紹介します。 夏や冬といった温度変化の激しい季節 旧車で故障が発生しやすいのは、真夏や真冬といった温度変化の激しい季節です。特に真夏は、温暖化の進行によって新車販売時には想定していなかった気温になる日も少なくありません。 具体的に注意したいポイントは、温度変化に弱いゴムや革製のパーツの劣化です。例えば、2008年式のプジョー308SWでは、酷暑の影響でシフトノブが突然ポロポロと崩れ落ちたといった事例もあります。 また、ボディ塗装の劣化も、旧車を保有していると避けられない問題です。塗装は紫外線の影響で、時間経過とともに徐々に劣化していきます。特に夏場は紫外線が強いうえ、雨上がりの水滴がレンズの役目をして、太陽光線がボディを焼いてしまうこともあるようです。屋根付きのガレージや車全体を覆うカバー、日除けの装備など、できるだけ温度変化を抑えられる工夫をして保管しましょう。 さらに、酷暑による影響は劣化しやすいパーツだけではありません。エンジンの冷却系やエアコンのコンプレッサーなど、熱を逃がすための機器類に過剰に負荷がかかる恐れもあります。特にエアコンは、夏を迎える前に点検とメンテナンスを実施し、突然の故障に見舞われないよう注意しましょう。 比較的新しくても油断しない 旧車というと、極端に古いクルマをイメージしがちです。しかし、FD2型シビックタイプR 、Z33型フェアレディZ 、GRB型やGVB型インプレッサWRX STI、NC型ロードスター、ポルシェ911(Type99)など、現代的なイメージの強いクルマも製造から10年以上経過する旧車の域に入っています。 今は目立った劣化がなくても、ちょっとしたきっかけで故障に発展する恐れもあるため注意が必要です。日常的に点検をすることで、大きな故障への発展を防げる場合もあります。できるだけ軽微なうちに故障箇所に対応して、愛車をより長く健全な状態を保ちましょう。 重要なパーツは予備を保有しておく 旧車を保有する場合は、重要パーツの予備を準備しておくことをおすすめします。生産終了から一定の年数が経過するとパーツの生産が打ち切られるケースもあるほか、仮に生産されていても供給自体が絞られる可能性が高いためです。 例えば、1996年式のトヨタ AE111型カローラレビンのリアハブベアリングは、メーカーによる供給は続いているものの受注生産のため納品まで数ヶ月かかります。万が一故障した場合は、数ヶ月間クルマを動かせません。 旧車には「持病」と呼ばれる、特有の故障しやすい箇所が判明している車種もあります。修理する可能性の高い部品は、入手可能なタイミングで予備を用意しておきましょう。 三重苦があってもやはり旧車は魅力的 現代では考えられないスタイリングや設計思想など、旧車には多くの魅力があります。避けられない三重苦があってもなお旧車は人気を集める存在です。また、しっかりとメンテナンスされた旧車であれば、車種によっては資産としての価値も生まれます。 一方で、旧車の売買をする際は、一般的な中古車業者での取引はおすすめしません。購入時は当然、専門業者によるメンテナンスや車輌状態の説明が必要不可欠です。一方、売却時には、やむを得ない経年劣化も含めて、正しく査定してもらうことが重要になります。一般的な中古車店では、古いというだけで減額されるかもしれません。三重苦に耐えて維持してきた旧車なだけに、売却の際は正確な査定をしてもらえる専門業者に相談してください。

ディフェンダー90の魅力はスペックじゃない?! ランドローバーのロマンあふれる希少車を徹底紹介
イギリスに本拠を置く、ランドローバー社のディフェンダー90。特に初代モデルはヘビーデューティーのクロスカントリー車として、現在も多くのファンを魅了し続けています。 現代のSUVのような高い利便性やスペックを持ち合わせていないにも関わらず、なぜディフェンダー90が人を惹きつけるのでしょうか。ルーツをたどりながら、ディフェンダー90本来の魅力を徹底的に解説します。 伝統の外観を踏襲した初代ディフェンダー90 1990年に登場したディフェンダー90ですが、実は1983年に行われたランドローバーⅢのマイナーチェンジが事実上の初登場です。さらに、外観も含め硬派なオフロード車輌という面では、ローバー社最初のモデルがルーツともいえます。 まずは、ディフェンダー90の開発背景と、日本国内での人気ぶりを紹介します。 由緒正しいランドローバーシリーズがルーツ ディフェンダー90のルーツは、1948年に製造が始まったランドローバーシリーズです。1983年のマイナーチェンジによりランドローバー90/110と改称されたモデルが、直接的にディフェンダー90につながっています。最初のモデルを開発した当時のローバー社が、オフロードに特化したクルマとして「ランドローバー」と名付けました。 「ディフェンダー90」(110/130)の名称に変わったのは1990年。「ランドローバー ディスカバリー」という新モデルの登場に合わせて、混乱を避けるために命名されました。なお、数字の「90」はホイールベースのインチ表記を表しており、ランドローバー90が最も短いモデルです。 ちなみに、ディフェンダー90をはじめ、ランドローバーのアイデンティティとも呼べるアルミ製のボディは、意図して狙ったわけではなく時代背景によって生まれたという逸話が残っています。第二次世界大戦直後の1948年当時、戦争の影響で鉄が不足していた影響からアルミボディが採用されたそうです。 国内ファンが待ちわびた正規輸入の開始 ディフェンダー90の日本国内での正規販売は、登場から7年後の1997年です。限定輸入された500台は、わずか1年足らずで完売。いかに日本のファンが、ディフェンダー90の輸入を待ちわびていたかがわかります。なお、最初の輸入モデルは、左ハンドル車でトランスミッションはATのみでした。 翌年の1998年には、ランドローバー50周年記念の限定モデル450台が追加輸入されました。数百台単位と聞くと、それほど多く感じないかもしれません。しかし、日本国内では実用面での需要がほとんどない、オフロードに特化したクルマという点を考慮すると驚異的な数字です。 便利で高性能ではないのになぜか魅力のある初代ディフェンダー90 初代ディフェンダー90の販売は1990年〜2016年ですが、外観のルーツは1948年まで遡るなど、当時としても最新装備を身にまとったクルマとはいえません。しかし、ディフェンダー90のもつ魅力は、仕様やスペックだけでは語れない部分に詰まっています。 ここからは、ディフェンダー90の魅力を詳しく紐解いていきましょう。 英国の気品漂う外観 緑豊かなイギリスの大地に映える、初代ディフェンダー。オフロードカーらしいシンプルな直線基調のボディにリベット留めと無骨なデザインですが、どこかイギリスの気品が漂っています。 初代ディフェンダー90の外観は、最初のランドローバーが登場した1948年から受け継がれ続けたものです。ヘッドライト位置の変更などモデルによって異なる部分もありますが、大枠は踏襲しています。ディフェンダー90も2007年と2012年に二度のマイナーチェンジを実施しましたが、外観に関しては2016年の販売終了までほぼ手を加えられることはありませんでした。 ローバー社が「ランドローバー」を世に送り出したコンセプトを、初代ディフェンダー90は忠実に踏襲しています。1948年当時の空気感を感じられる点も、ディフェンダー90が人気の理由なのかもしれません。 特徴的なリアシートは一部から不評を買った ディフェンダー90のリアシートは、左右対面式のベンチシートです。対面になっているシートを折りたたむと広大なラゲッジスペースが生まれるため、ヘビーユースに適した形状として採用されたのでしょう。また、兵員輸送車のような硬派な雰囲気を醸し出すという点で、ディフェンダー90を特別なクルマに昇華させている一因です。 一方で、ファミリー層からは、乗り心地の悪さや乗降のしにくさから不評を買いました。リアシートの形状に我慢できず、ディフェンダー90を手放したという話も珍しくなかったようです。 高性能車ではないがロマンという言葉がしっくりくる ディフェンダー90は、今の基準でみると決して性能の高いクルマではありません。正規輸入されたモデルには、4LのV8ガソリンエンジンを搭載。スペックも最高出力182ps、最大トルク32.2kgmを絞り出すという、数字上は迫力のあるエンジンです。しかし、アルミ製の軽量ボディながら2tを超える車体を、俊敏なSUV車のように加速させるには力不足が否めません。 また、オフロード車としての堅牢性を実現するラダーフレームと、構造がシンプルな前後リジッドサスペンションは、お世辞にも乗り心地がよいとはいえず古臭さを感じます。 それでもなおディフェンダー90に魅了されるのは、終戦直後から脈々と受け継がれてきたランドローバーへのリスペクトとロマンなのかもしれません。 新型車が出てもなお人気の初代ディフェンダー90 ディフェンダー90は、2020年のモデルチェンジで2代目に移行しました。長年継承されてきた外観は一新され、課題だったパワーや装備面も克服し、現代に相応しい仕様で販売されています。しかし、新車かつ現行型が買えるにもかかわらず、初代ディフェンダー90の根強い人気は衰えません。 人気の高さは価格にも表れており、状態によっては当時の新車価格よりも高値で取引されるケースもあります。ただし、初代ディフェンダー90を中古車で売買する際は、必ず旧車専門業者に相談しましょう。1990年代のクルマとはいえ各部の設計が古いため、適切なメンテナンスがされていないと、購入しても故障に悩まされかねません。また、正規輸入車輌は台数限定だったため、現在では希少車です。希少車の買取に慣れた業者でないと、実際の価値を正しく査定してもらえない可能性があります。 ロマンのあるクルマが少なくなった現代だからこそ、ディフェンダー90は貴重な一台です。売却の際には、慎重に業者を選びましょう。

御年70歳でもまだまだ現役。小さなクラシックカーショーで見つけた1953年製の赤いMG
イギリスでは、日照時間が長い夏時間(サマーマイム)というものがあります。 そしてこの時期にはいろいろな場所でクラッシクカーショーが毎週のように行われています。 そのなかのある田舎町の小さなクラッシックカーショーに行ってみました。 その日は晴天で、カーショーにはもってこいの日でした。 イギリス南西にあるウィギントンという小さな村ですが、カーショーの他に日本でいう遊園地の乗り物があったり、出店がでていたりと、ちょっとしたお祭りのような雰囲気でした。 様々な魅力的なクラッシクカーが芝生の上に並んでいましたが、そこで真っ先に目の飛び込んできたのが赤いMGでした。 何とも言えないボディーシェイプで可愛らしさがあり、一瞬で魅了させられました。 それは、1953年製のMG YB。 MG Y-タイプのYAが初めて世に出たのは1947年で、YBは初期のYAをさらに強化したもので、1951年から1953年の2年間で1300台ほど製造されました。 元は黒で錆がかかっていたMG YB オーナーであるジョンさんに話を聞いたところ、彼はこのMGを約20年前に格安で購入し、年月をかけてここまで素敵なクルマに変えていきました。 ジョンさんに古い写真を見せていただきましたが、画像を見てもお分かりのように庭におきっぱなしにされていて、元の黒いボディはさびて廃車に近い状態でした。 この廃車状態から赤いMGに生まれ変わるまでの時間と費用は相当だったそうです。 まず彼はクルマを解体しすべて、ひとつひとつのパーツにしたそうです。 そして、自ら持ち得たクルマの知識を活かし、少しづつ元通りに組み立てていきました。 そのなかで使えるパーツはそのまま使用したそうですが、中には入手困難なパーツもあり、その時はMG協会から譲ってもらったりしたそうです。 どうしても手に入らないときは、特別にオーダーしてオリジナルのもの作ってもらったとのこと。 黒に塗られていたボディは、一度すべて塗料を削ってはがしてから、新たに赤に塗っていきました。 これらの一つ一つに、当然相当な時間とお金を要しましたのはいうまでもありません。 実際の値段は聞きませんでしたが、「普通に家が買えるぐらい」と苦笑いしながら話していました。 ハンドルや内装はオリジナルのものをできるだけ使用しており、英国感を醸し出しています。 私もクルマに乗車させていただきましたが、一瞬ちょっと田舎のおばあちゃんちの家の匂いを思い出しました。 車内はわりと狭く、サルーンなのでバックシートもありますが、本当に4人も乗れるの?という感じでした。 でも、木製の大きなハンドルはとっても素敵で握りやすかったです。 1953年製の希少なMG YB 冒頭でも少し触れましたが、ここで改めてMG YBがどのようなクルマかを簡単に説明しましょう。 MG社のサルーンとして発売されたYタイプには、YA、YT(コンバーチブル)、YBと3つのモデルがありますが、1947年から1953年までの総生産は約8000台。 YBのみの場合、1951年から1953年までに製造されたのはトータルで1300台ほどでした。 エンジンスペックは1250cc(4シリンダー)、トップスピードは70mph(約112kmph)、加速スピードは60mphまで30秒。 約1300台作られたうち、現在もオーナーがいるYBは世界で141台のみ。 聞くところによれば、イギリス92台、アメリカ22台、オーストラリア3台、ヨーロッパ18台、カナダ3台、ニュージーランド1台、そして日本を含めたアジアにはたったの1台のみだそうです。 約1300台もあったクルマが、70年間の間に廃車となって消えていき、世界で141台のみが今だに生き残っていると思うと、なんて希少なんだと思わされますね。 当時のMG YBの車体値段は£635、税金が£354で計£989でした。 イギリスは税金が高い国ですが、当時の税金は60%で車体の値段の半分以上。 これには驚きです。 70年前の£989がどのくらいの価値があったかというと、今でいう£34,000(日本円で約620万円)。 この時代の平均収入は年間£100だったので、かなりの高価であることがわかります。 クルマを持つこと自体が贅沢だった時代ですから、税率が高いのも仕方なかったのかもしれません。 クラッシクカーを持つ本当の意味とは このクラシックカーショーでMGとジョンさんに出会い、素敵なお話も聞かせてもらいました。 なぜ家が買えるほどのお金と20年という年月をかけてまで、このMGを保持し大切にしているのでしょうか? ジョンさんがいうには、子供の頃に見ていた古いクルマの印象とその光景が彼にとっては当たり前で、時代が変わってもその光景が変わることなく、ずっと頭のなかにあったのだそう。 近代のクルマも素敵ではあるけれど、彼の子供心が続く限り、このクルマをかわいがるつもりだと話してくれました。 そんな彼を見て、いつまでも子供心を大事にしてほしいと思いました。 ちなみに彼はこのMGを週末だけ、しかも天気が晴れているときのみ運転するそうです。 田舎町でピクニックをしたり、もちろんロンドンにも行かれるそうです。 以前の記事でも述べましたが、このYBには車輌税やULEZなど一切の税金がかからないので、どこへでも行けますね。 クラッシックカーと超低排気量ゾーン(ULEZ)の税金 ~ロンドン事情~https://www.qsha-oh.com/historia/article/ulez-london-classic-cars/ それ以外はガレージに保管していて、時々磨いているそうです。 今回偶然出逢ったMG YBですが、どのクラッシクカーにも歴史とそのオーナーの思入れがあるようなので、それを探求するため今後も素敵なクラッシクカーを紹介していきたいと思います。 Thank you, John. *文中の車輌解説は、ジョン氏からお借りしたMG社のものと思われる資料より引用しました。 [ライター・画像 / SANAE]

ランクル70のトゥループキャリアは隠れた人気車種?! 海外限定モデルの全貌に迫る
高級SUV路線のモデルも発売されるなかで、硬派な出で立ちのヘビーデューティー仕様を貫くトヨタ 70系ランドクルーザー。通称「ランクル70」とも呼ばれるこのモデルは、販売終了後に再販されるなど、現在でも高い人気を誇っています。 数あるランクル70のモデルのなかでも、マニアを中心に注目を集めているのがオーストラリアや中東を中心に販売されている「トゥループキャリア」です。「トゥルーピー」という通称で呼ばれるほどファンが多く、日本国内では販売されていないものの、並行輸入で入手する人もいるほどの人気を誇ります。今回は、隠れた人気モデルであるランドクルーザー トゥループキャリアの魅力に迫ります。 国内販売終了後も世界で作り続けられたランクル70 ランドクルーザー70は、日本国内での販売が終了した後も、中東やオーストラリアといった需要の高い一部の地域で生産され続けています。しかも、ただ同モデルを生産するだけでなく、精力的な年次改良やバリエーションの追加までされるほどの人気車種です。 まずは現在のランドクルーザー70の事情について紹介します。 今もなお人気の70系ランドクルーザー 70系ランドクルーザーは、ロングライフだった40系の後を受ける形で1984年にリリースされました。ヘビーデューティー系と呼ばれる、ランドクルーザー本来のオフロードユースを想定したモデルで、高い走破性と耐久性から人気を集めます。2004年に日本国内での販売が終了するまで、わずかなマイナーチェンジのみで20年間も販売されました。 一方で、国内販売が終了した後も、オーストラリア向けを中心に70系ランドクルーザーは生産され続けます。日本国内でも2014年に限定で再販されましたが、2023年に再度の再販が決定したことも報じられました。 オーストラリアで販売されているトゥループキャリア ランドクルーザーは、用途に応じてさまざまなボディタイプが用意されています。「トゥループキャリア」は、「一団、軍隊」などを意味する英語の「troop」に由来し、人員を輸送することに特化したモデルです。 ロングタイプボディのリアシートは、前後ではなくボディ左右に対面式のシートが設置され、より多くの人員を輸送できるようになっています。 並行輸入という形で国内入手も可能 ランドクルーザー70は、日本国内では販売されていません。(新型車の国内再販は2023年に発表済)しかし、現在も販売の続くオーストラリアのモデルを、並行輸入品として取り扱う専門店もあります。 また、並行輸入モデルは、国内販売されていないエンジンが搭載されている点も大きな魅力です。現行型のトゥループキャリアは、最高出力205ps、最大トルク430Nmを発揮する4.5L V型8気筒のディーゼルターボエンジンを搭載。大柄なボディに見合ったビッグサイズエンジンは、国内販売車にはない迫力を感じさせてくれます。 ただし、公道で乗るためには、排気システムや架装を国内登録可能な仕様に変更する必要があるため注意しましょう。多くの場合は、取扱い業者で対応してくれます。 国内版では見られない個性的なランクル オーストラリアで販売されているトゥループキャリアは、国内のランドクルーザー70にはない個性的なモデルです。法令的な問題はあるものの、広大な自然のあるオーストラリアだからこそ生まれたモデルといえるでしょう。 今すぐにでもアウトドアに出かけたくなるランドクルーザー70 トゥループキャリアの魅力に迫ります。 横向き対面式に配置されたリアシート トゥループキャリア最大の魅力は、後席の対面式シートです。通常は前後に配置される座席が、通勤電車のようにボディサイドに沿って左右に配置され、多くの人々が乗車できます。約5.2mというロングボディということもあり、リア部分は広々としていて使い勝手も抜群です。 日本国内では新規の登録ができない影響から、新しく購入した場合は前席の3名乗車ですが、広大な荷室はアウトドアや車中泊といった場面で大活躍します。 質実剛健を地で行く力強いデザイン もともとヘビーデューティ仕様として開発されたランドクルーザー70は、車高、全高ともに高く、全体に直線基調の機能性を重視したデザインが採用されています。さらにトゥループキャリアは、車輌側面に後席のドアがありません。開口部が最小限のデザインは、ランドクルーザーの力強さをより強調しています。 後席の乗員は後部に設置された観音開きのドアから乗降するという、まさに兵員輸送車のようなデザイン。デザイン性はもちろん、実使用時の堅牢性という面でもランドクルーザー70のコンセプトを体現しています。 国内正規販売されていない希少車 トヨタ 70型ランドクルーザー トゥループキャリアは、国内で正規販売されていないだけに流通量の少ない希少車です。また、根強いファンからの人気が高く、状態次第では通常のランクル70の2倍近い価格がつくこともあります。 一方で、流通量の少ない車種は、どの中古車業者でも買取ってもらえるわけではありません。特にトゥループキャリアのように特殊な車輌の場合、取り扱いに慣れている業者でなければ正確に査定することさえ難しいでしょう。旧車や希少車の売却を検討する際は、取扱い経験が豊富な専門業者への相談がおすすめです。 例えば、多くの旧車や希少車を取り扱う旧車王では、今回紹介したトゥループキャリアを最近買取しました。高い専門性を持っているからこそ、大切に乗ってきた愛車に正しい査定額の提示が可能です。
