「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
旧車の再生と維持

ベテラン旧車オーナーがひそかに心がける、愛車維持の秘訣とは?
昨今の旧車ブームによって、旧いクルマに対してにわかに興味を持たれた方は多いことだろう。 これまでもお伝えしてきた通り、旧車には現代のクルマにはない魅力があるのは紛れもない事実である。 しかし、相手は最低でも20~30年落ちのクルマだ。 快適装備をこれでもか!と装備した現代のクルマと同じように扱えるとは到底思えない。 同じように感じる方は少なくないだろう。 旧車に憧れはあっても、実際に手に入れようとすると、どうしても購入をためらってしまうことは決して不思議なことではない。 クルマは自身の生活の一部分になるものだ。 初めて旧車を購入しようとする方にとって、旧いクルマを一筋縄に扱えるか、不安なことこの上ないものだろう。 筆者自身、プロ・アマチュアにかかわらず、数多くの旧車愛好家とお付き合いをさせていただいている。 これらの観点および自身の経験も含め、これから旧車を購入予定の方に少しでも参考になるように、愛車を末永く維持して旧車ライフを満喫できるヒケツを紹介したい。 旧車の不便な部分とは? ▲エアコンが備わる前の旧いクルマ独特の装備、三角窓 この記事をご覧のあなたは旧車、すなわち旧いクルマは現代のクルマに比べて、何かと不便な部分が多いイメージをお持ちではないだろうか? 当時を知る由もない、とくに20代の若いオーナーにとっては、憧れの旧車とはいえ、自身が生まれる前のクルマの購入を考えたときに悩みがちな部分であろう。 ある程度、歳を重ねたベテランオーナーには当たり前のことかもしれないが、ここで具体的にどのような部分が不便なのか、ここで一例を挙げてみよう。 「エアコン・パワステ・パワーウィンドウ」が装備されていない 昭和や平成初期の中古車には、「フル装備」と表示がされていたが、これは「エアコン・パワステ・パワーウィンドウ」の3点を指す。 ある一定の年代より旧いクルマは、これらが備わらない車種が多いため、快適性能からして劣るイメージを持たれる方が多いよう感じるが、まずこの部分から考えてみよう。 なお、エアコンについては後述する。 パワステ(パワーステアリング)については備わらなくとも、カスタムなどで極端に太いタイヤを履かせていたり、小径ステアリングを装着していない限りは、それほど困ることはないだろう。 ステアリング操作の軽い現代車に慣れてしまっていると、やや旧車への抵抗感を感じるかもしれない。 しかし、クルマが停車した状態で無理に据え切りをせずに、少しでもクルマが動いている状態でステアリングを切るなど、当時、誰もが行っていた運転方法に慣れれば、それほど苦にならないはずだ。 思えば、筆者の母も当時細い腕で、ノンパワステのVWゴルフを転がしていたものだ。 次に、パワーウィンドウが備わらないクルマについて述べよう。 よく、パワー(いるんです)ウィンドウなどと揶揄されるが、そんなことはない。 レギュレーター周りのメンテナンスがしっかり行き届いていれば、窓の開閉が重いということはまずないはずだ。 むしろ筆者はクルマを修理する観点から、旧車にパワーウィンドウが装備されていると、逆に身構えてしまう。 まずパワーウィンドウの開閉スイッチは、そもそも旧車でなくとも壊れる可能性が高い部品であるし、経年劣化によりモーターやレギュレーターが傷んでいるクルマが多い割には、部品の供給を心配しないといけない部分でもある。 偏った考えではあるが、パワーウィンドウが備わらないことで、イグニッションスイッチがオフの状態、さらにバッテリーが上がっている状態でも窓の開閉ができるといえば、これは意味メリットではなかろうか? パワステにしても、パワーウィンドウにしても、無くてもなんとかなるものではないだろうか? 最後にエアコンについて述べる。 エアコン(エアーコンディショナー)とは、その名の通り、空気を調整する機能だ。 クーラーとヒーター両方の風を混合(ミックス)し、室内空間をドライバーにとって快適な温度と湿度に調整する機能がエアコンである。 少なくとも70年代前半までのクルマには、エアコンという概念がないクルマが数多く存在する。 ヒーターと三角窓(画像参照)のみ備わるのだ。 旧車であれば、現代のクルマには絶対にない三角窓やクロッチクーラー(外気取り入れ口)といった装備がある。 これらはドライバーの体感温度をそれなりに下げてくれるが、気温40℃を超えることもある昨今の猛暑では完全に役不足だ。 旧車にはクーラーのみ後付けできることが多い。 これは当時からの贅沢な手段ともいえる。 旧車にクーラー装着はエンジンに悪影響があり、NGという意見もあることは確かだ。 しかし、昨今のクーラーキットは旧来のものに比べ、コンパクトかつ性能が良く、とても冷えるものが多い。 高額な装備ではあるが、検討してみても良いと思う。 現代のクルマでは当たり前のものが装備されていない その他、旧車にはナビやドライブレコーダーはおろか、ETCも後付けが当たり前、ドリンクホルダーなども当然のごとく備わらない。 リモコンドアロックなど、もっての外だ。 シートについてもフルフラットはおろか、ある年代より旧くなるとリクライニングすらできない車種もある。 ビジュアル面からのイメージが先行して、こういった部分を知らずに旧車を購入してしまい後悔したという話もないわけではない。 多少不便な部分があっても、まずは自分をクルマに合わせる ▲エアコンが備わらないクルマの、後付けクーラーの一例 ここまで、ほんの一部分ではあるが、旧車の不便な点を解説した。 今日は空前の旧車ブーム真っただなかであり、業界はとても賑やかだ。 旧車であっても、自分好みのカスタムを楽しんでいるオーナーは多く存在する。 なかには旧車カスタムの域を超え、旧車の不便な部分をフォローすべく、現代の最新デバイスを装着する例も決して珍しくはない。 極めればそれをレストカスタムとも、魔改造とも呼ぶ。 いかんせん旧車の構造は現代車に比べれば、とてもシンプルである。 例えば、クラシックな鉄板製のダッシュボードを切削加工して、最新の2DINナビを装着することも可能であろう。 リクライニングができないシートの代わりに、現代車のパワーシートをシートレールごと溶接して装着する方法だってある。 筆者も20代の頃は個人的に、このようなカスタムが好みであったが、皆さまはいかがお考えだろうか? 不便だからといってあまり深く考えず、これ見よがしに最新装備を旧車に移植するようでは、何のために旧車に乗っているのか分からない。 一度加工したものを元に戻すことはとても面倒である。 そもそも絶版となった部品はハード・トゥ・ファインドである場合が多く、失ったら最後、2度と手に入らないモノも多い。 決して、現代の装備を旧車に装着することを否定するわけではないが、その最新のデバイスが自身にとって本当に必要なものかを考えることも重要である。 多少不便な部分があっても、その当時の時代背景を考えることも、旧車趣味のひとつではなかろうか? 旧車に乗れば、現代車への進化の過程を身をもって体感できる。 なぜ、現代においてマニアがビートルズを真空管アンプとLPで聴く趣味があるのかを、よく考えてみたい。 旧車趣味も同じベクトルであるのは間違いないのだ。 なお、ベテランかつ通なオーナーは、あたかもそのクルマが新車のころのオプションを装着したかのように巧みにカスタマイズする。 筆者はこういった先輩オーナーの隠れたこだわりをみて、自分もまだまだであると感じるものである。 当時モノのモモやナルディーのステアリング、レカロシートなどが高額で売買される理由はここにある。 旧車と長く付き合いたいのであれば、自身にとって本当に足らないと感じたモノを後付けすれば良いのではなかろうか。 機能がなくなることで、その大切さやありがたみが分かってからでも決して遅くはないはずだ。 クルマを自分に合わせるのではなく、まず自分をクルマに合わせることが、ベテラン旧車オーナーへの道ではなかろうか。 洗車をしたら、車庫にしまわずにドライブへ 旧車は磨きがいのあるクルマが多い。 旧いクルマはその佇まいこそが特別なものであり、一切カスタムせずとも存在感のあるクルマが多いものだ。 ボディーにしっかりワックスが乗りかかり、モールに磨きがかかっていれば、多少のキズヘコミがあろうとも、凛として見えるモノだ。 旧車を手に入れれば、クルマを磨くことも趣味の一つになることであろう。 ただ、一つここで注意を促したい。 雨を浴びたり、洗車後のクルマは、ボディ内側の至る部分に水分が溜まっている。 フェンダーやトランクの裏側、足回り、そしてフロアやドアの内側などだ。当然この部分は、手の届かない部分である。 タオルで水分を拭き上げることはまず不可能だ。 では、いったいどうすれば良いのか? それは、クルマが水を浴びたらまずは走行してほしい。 クルマの内部は走行することで、至る部分で負圧が生まれる。 この負圧が、クルマに溜まった水分を吸い上げてくれるのだ。 旧いクルマは錆びるからといって、バケツに水を汲み、軽く絞ったタオルで吹き上げる。 いわゆるバケツ洗車を行うと、塗装に傷が入りやすい。 しっかりと水を使ってホコリを流したうえで、シャンプーで汚れを浮かし、入念に泡を流し、これを吹き上げる。 これこそ洗車の基本だ。 そのうえで、先述の通り、クルマを走らせることでしっかりと水を切りたい。 洗車後のドライブも、洗車の一工程といえるのだ。 ドライブから帰ってきたら、各部をグリスアップすれば完璧だ。 これも旧車維持のための必須事項だ(旧車のグリスアップについては以前の記事をぜひお目通しいただきたい)。 目先のカスタムよりも、メカにお金をかける ▲旧車は一筋縄とはいえない。常にメンテナンスは念頭に入れておくべきだ 憧れのクルマを購入した次には、自分好みにカスタムをしたくなったり、アクセサリーを購入したくなる。 これは至極当然のことだ。 ただ少し待ってほしい。 購入したクルマのコンディションはいかがだろうか? 購入したクルマの見た目はキレイであっても、クルマの下回り、すなわちメカの状態が悪かったということは決して珍しい話ではない。 クルマを購入するときに、下回りを見て購入することはほとんどないことであろう。 また旧車の場合、車検切れなどで、試乗をせずに購入することも多いことだろう。 購入元がメンテナンスや修理に力を入れているショップであれば心配はないであろう。 しかし、これが販売専門のショップであったり、個人売買などでクルマを手に入れた場合、まずメンテナンスを引き受けてくれる工場を探すべきである。 購入したばかりの愛車が、次回の車検に問題なく合格できるとは限らない。 大きな費用がかかる場合もあれば、入手困難な部品が必要になる場合もある。 旧車は一筋縄では行かないとよくいわれるが、こういった場合に痛感することが多い。 カスタムは、購入したクルマが本当の意味で絶好調になってからでも遅くはない。 クルマを購入してから、少なくとも最初の車検を通すまでは、しっかりメンテナンスの予算を用意しておくべきだ。 とにかくクルマに乗ろう!使用による傷はなんのその ▲さほど使用せずとも、家庭用充電器では完全放電したバッテリーの充電は難しい どうしても愛車を大切にしている気持ちから、なかにはセカンドカーを購入し、クルマをガレージにしまいがちになるオーナーもいることだろう。 そして、それは筆者も同様だ。 色々な要因があると思う。 雨風に愛車をさらしたくないといった、至極単純なことから、燃料の高騰が叫ばれるなか、燃費が悪いため、ガソリン代がかさんだり、絶版部品が多く、できる限り事故に遭いたくなかったり・・・。 しかし、旧車を放置するとロクなことがない。 まず、キャブレター内のガソリンが劣化しエンジンが掛かりづらくなる。 さらに、ガソリンタンク内は結露が発生するため、ガソリンに水分が混じりやすい。 そしてこれがタンク内部の錆の原因となり、これが燃料ポンプの故障の原因ともなる。 タイヤは常に地面に接している部分に力がかかるので、丸いタイヤが四角く潰れる。 これがいわゆるフラットスポットだ。 このまま走ると、バタバタとした振動が不快なこと極まりない。 バッテリーも短命になる。 充電器を繋げれば良いと思われるかもしれないが、一般的な家庭用充電器は劣化して抵抗と化したバッテリーの過充電を避けるため、50%以上容量が消耗したと思われるバッテリーの充電を行わない。 バッテリーを交換するか、ブースターケーブルを繋げない限り、エンジンを始動できなくなってしまうのだ。 とにかく旧車は1週間に一度はエンジンに火を入れて、それなりの距離を走るべきだ。 旧車の日常使いはもったいないという意見を耳にするが、こればかりは肯定も否定もできない。 しかし、愛車のコンディションを隅から隅まで理解しているオーナーは、やはり日常使いをしている方が多い。 筆者もその傾向にあるのだが、どうしてもバッテリーを放電しがちなほどクルマに乗らないと、自身のクルマであっても、完調なのか不調なのか分かりづらくなってくる。 旧いクルマの扱いに長けたベテランの旧車オーナーは「やはりクルマは乗ってなんぼ」であることをよく理解している。 日常的に火が入るエンジンは、隅々までオイルが行き渡り、クランクの回りも軽くとても調子の良いものだ。 とにかく乗ることが、愛車の維持管理の近道であることは間違いない。 多少の傷など、何のその。 とにかくクルマは乗って楽しもうではないか! ※私クマダはYouTubeでポンコツ再生動画を公開しております。ぜひ動画もご覧になってください。チャンネル登録お待ちしております。 ●YouTube:BEARMAN’s チャンネル(ベアマンチャンネル)https://www.youtube.com/channel/UCTSqWZgEnLSfT8Lvl923p1g/ ●Twitter:https://twitter.com/BEARMANs_Ch [ライター・撮影/クマダトシロー]

ハリアーのよくある故障箇所は?修理費用の目安についても解説
ハリアーは絶大な人気を誇るクロスオーバーSUVです。また、トヨタのブランド力による信頼性の高さや、クルマとしての完成度にも定評があります。しかし、新車で購入してから10年以上経過すれば、経年劣化による故障は起こりやすくなります。 この記事では、20年以上前に発売された30系ハリアーのよくある故障箇所と、修理費用の目安を解説します。30系ハリアーを現在所有している方はもちろん、これから中古車で購入を検討している方も、ぜひ参考にしてください。 ハリアーのよくある故障箇所 車検に通したり、購入を検討したりする際に、予測されるトラブルをあらかじめ把握しておくことは大切です。 ここでは、30系ハリアーのよくある故障箇所について解説します。 ヘッドライト内部に水が浸入する 30系ハリアーは、ヘッドライトの内部に水が浸入することがよくあります。修理方法としては、中古のヘッドライトに交換という方法もありますが、水漏れに弱い部分も同時に修理できる加工修理のほうがおすすめです。加工修理であれば、シーリング剤、もしくはコーキング剤を使って水漏れ対策ができるため、長い目で見れば中古のヘッドライトを購入するよりもコストがかかりません。 修理費用は、左右とも修理した場合で2万〜3万円です。黄ばみなどを落とすヘッドライトクリーニングも同時に行えば、見た目の改善を図ることができます。ただし、30系ハリアーの場合、年数の経過から簡易的なヘッドライトクリーニングでは綺麗にできない可能性があります。耐水紙やすりでヘッドライトの黄ばみを削り落とし、その上でクリアコーティング剤を塗布するという作業が発生するため、2万〜3万円程度の追加の施工費用がかかるでしょう。 ラジエーターからの冷却水漏れ ラジエーターからの冷却水漏れは、30系ハリアーで定番のトラブルです。そのため、購入前に必ずラジエーターを交換してあるかどうか確認してください。具体的には、ラジエーターコアとラジエーターサイドタンクの接合部のカシメ部分から冷却水漏れが起こります。 ラジエーターASSYへの交換により修理が可能です。純正部品はもちろん、社外品への交換でも使用するにあたって大きな問題はありません。おおよその修理費用は、純正部品を使用した場合で6万5,000円程度、社外品を使用した場合で5万円程度です。 ハブベアリングのガタつき 走行中に「ゴーゴー」などの異音が出る場合は、ハブベアリングがガタついている可能性があります。 ハブベアリングのガタつきは、走行距離が10万km以内であればそれほど心配する必要はないといわれているものの、足回りに負担がかかるような運転をしていたり、社外品の大径ホイールやハイグリップタイヤを履いていたりする場合は、ハブベアリングへの負担が大きくなって寿命が縮まります。状況によっては6万km程度で交換に迫られるかもしれません。 修理の際にはハブベアリングそのものを交換します。費用は、1箇所あたり2万5,000円〜3万円程度です。 マルチナビゲーションのタッチディスプレイの不具合 30系ハリアーでは、マルチナビゲーションのタッチパネルが全く反応しなくなるという故障が散見されます。 カーナビの操作やエアコンの細かい設定ができなくなるため、運転に大きな支障が出てしまうトラブルです。 おおよその修理費用は、電装系の修理が対応可能な整備工場で修理した場合で5万〜9万円程度、ディーラーに修理を依頼した場合で10万〜20万円程度です。 タイミングベルトの寿命 ハリアーハイブリッドの3MZ-FE型エンジンに使用されているタイミングベルトは、走行距離に応じて交換を検討しましょう。 タイミングベルトは、多くのメーカーで10万kmごとの交換を推奨されています。寿命を迎えても目立った症状のない部品ですが、万が一タイミングベルトが切れると深刻なエンジントラブルに繋がるため、推奨されている距離で交換しましょう。また、タイミングベルトの奥にあるウォータポンプも同時に交換するとよいとされています。 おおよその修理費用は、ウォーターポンプと一緒に交換した場合で、11万〜15万円程度です。工場によってはもっと安い場合もありますが、非常に重要な部品であるため、費用だけで依頼先を決めるのは危険です。信頼できる技術力をもつ修理工場、もしくはディーラーに依頼することをおすすめします。 そもそもハリアーとは? ハリアーは日本を代表するクロスオーバーSUVの1台です。1997年から現在まで、25年以上もの間販売が続いています。 ハリアーの確固たる地位を築いたのは、先進的なデザインと高い質感のインテリアが特徴の30系です。2代目のモデルにあたり、2003年から発売が開始されました。 日本国内のみならず海外でも販売されており、初代10系と2代目30系まではレクサスブランドの1つとして展開されていました。 2013年12月には、その人気の高さから実に10年振りとなるフルモデルチェンジが行われ、3代目にあたる60系が国内専用車として登場します。国内のみだと販売台数が稼げないために製造コストがかさむといわれているなかで異例の存在でした。4代目の80系はグローバルモデルとして再び海外で販売されているため、60系はハリアーの歴史のなかでも異彩を放つ存在といってよいでしょう。 まとめ ハリアーの歴史やよくある故障箇所について解説しました。 ハリアーは故障の少ない車種といわれていますが、2010年以前の30系ハリアーに関してはここで紹介した故障を想定しておく必要があります。また、購入を検討している方は、比較的故障のリスクが低い2010年〜2013年の個体をおすすめします。 もしくは、30系ハリアーよりも高年式な中古車を購入するとより安心感を得られるかもしれません。たとえば、故障に対する備えを車輌代に回して、2016年くらいのお手頃な価格帯の60系ハリアーを手に入れるというのも1つの方法です。

「限界レストアラー」による限界ガレージライフ
紆余曲折を経て、ガレージを借りることとなり、電気が開通して早1年が経ちました。 ガレージ通いも、いまやすっかり日々のルーティーンです。 最近はカブオーナー(世にいう「カブ主」)で、ウーバー専業配達員の友人も同じ敷地内でガレージを借り、仕事道具のカブのメンテナンスピットとして使っています。 ときには壁にかけてあるソケットレンチや、電気をシェアすることもあります。 ■まさしく「限界ガレージライフ」? ガレージライフといえば、例えばGQやPOPEYE、BRUTUSあたりのライフスタイル雑誌に出てくるような、古い英国車と骨董品や雑貨のインテリアのファッションセンスに満ちたガレージを思い浮かべる方がいるかもしれません。 あるいはオールドタイマーやガレージ系YouTubeに出てくるような、二柱リフトもあって、加工機や特殊工具がちょっとした町工場並みの設備を揃えた「DIYメカニックガチ勢」を期待するかもしれません。 残念ながら、筆者にそんな甲斐性はなく、物置小屋に工具や設備を無理やり詰め込んだ雰囲気のガレージです。 サイズ的にも、スバル360だからかろうじて作業スペースとしてどうにか……という状況です。 ゆえに、同じ旧車王ヒストリア執筆陣のクマダ氏の記事を見ていると、これでガレージライフを名乗るのも正直穴があったら入りたいとさえ思えてくる有様です(苦笑)。 本来はあくまで、屋根付きシャッター付の月極駐車場。 ガレージや車庫というと、車両の保管場所以外に車両のメンテナンススペースという意味合いも出てくると個人的には思っています。 しかし、筆者が借りているガレージは昔の2Lのクラウンクラスを基準に最低限保管できる間取りのようです。 2ドアクーペのようなドアの大きい車両では、片方に寄せないとドアを開けるのにも苦労します。 おそらく現在のフルサイズSUVではかなり乗り降りが大変だろう、というのも予想がつきます。 賃料が比較的安価で、ほとんどの利用者がレンタルコンテナとして使っているのも、自動車の保管場所(特に本来室内保管が必須の高級車)には小さいという事情があると思われます。 ■昔の小型車の趣味車やオートバイとなると 車庫としては小ぶりですが、筆者のような昔の360cc規格の軽自動車をレストアしたいとなると事情は変わります。 エンジンの不調で一時的にセリカLBを保管したときは、ボンネットを開けて圧縮を計ったり、ラジエターホースを外したりするにも狭くて大変でした。 しかし、スバル360程度なら工具棚や機材を車庫内に設置して、外した部品を周りに置いてもどうにか作業スペースを確保できます。 現在は足回りもすべて外して、モノコックのみの状態ですが、単管パイプと自在キャスターを組み合わせた台車の上に載せてあります。 手で押すだけで前後左右に動かせるので、タイヤが装着されている状態より、狭い場所の移動は楽かもしれません。 ちなみに、この単管パイプは自宅に簡易ガレージを作ろうとしたときのもので、どうにかここで役に立ってくれました。 ■収納は自作の棚 いくらスバル360が小さいといっても、工具類や部品、スプレー等の置き場所は限りがあります。 内見したときに即思いついたのが、波板の壁の梁を利用して棚を作ることでした。 不動産屋さんに聞くと、壁や柱への多少の穴あけはOKとのこと。 よく見ると古い鉄板ビスがそのままになっていたり、床にアンカーを打ち込んであったりします。 退去時に自費で撤去さえすればいいとのことで、寛容な大家さんには本当に感謝です。 ちなみに、壁にかかっている流木らしき物体は、なぜかこのガレージの屋根の上に載っていた状態で、これは電気工事の際に見つけたものです。 エアガンは職場の引っ越しの際に出てきた、社長が昔遊んでいたというつづみ玉型のボルトアクションの空気銃、今ではガレージのオブジェになっています。 ■極力、もらいものや廃品を再利用 棚は新品の木材を使いましたが、配電盤は廃業したパチンコ店から出た中古、照明器具は職場の移転で出た廃棄品の再利用です。 中の工具や機材は20年間かかって集めたものです。 ボール盤は元土木関係のお隣さんからもらったもの、コンプレッサーは昔の職場の自転車屋でエア漏れを起こしたコンプレッサーを譲り受け、自力でエア漏れを直したものです。 一方で、溶接機はネットで買った格安のノンガス半自動溶接機。 仕上がりはそれなりですが、DIYで腐食部分の切り継ぎをする分にはどうにか使えるという感じです。 ■自分のガレージでDIYで弄ればリーズナブルになんて思われがち 専門業者に出せば最低でも数百万円といわれているレストア費用も、確かに自分でやれば部品代、油脂類代、塗料代だけで済みます。 全部自分でやれば数十万円でフルレストアできるのでは?と思ってしまいますが、なかなかそうはいきません。 筆者もここまで工具類を揃えるのに20年以上かかりました。 整備マニュアルと首っ引きでエンジンやサスペンションを自力で脱着して分解、組立ができるようになるまでに10年、そろそろ鈑金も自分でやってみるかと思い始めるまで15年かかりました。 自分でやってみて(仕事でもするようになって)、改めてレストア費用には工賃はもちろん、ノウハウの蓄積や、想定外の損傷に対応するための労力など、相応の意味があるのだなと思い知らされます。 筆者のスバル360は完全に個人の趣味なので、あえて仕事で請けるようなレストア作業なら絶対にやらないような(採算が合わないであろう)やり方とペースでのんびり作業しています。 クルマを実用品として考えている人は、安くクルマを買ってDIYで整備すれば安上りだと考えてはなりません。 やっぱりクルマの値段や整備の工賃には意味があり、それなりの金額を出して買ったクルマを信頼できる整備工場に出すのが費用対効果では安くつきます。 何かしら得るものがあるという意味で苦労は買ってでもしろという言葉があります。 しかし、何も得るものがなくても苦労したことの達成感に価値を見出せる人ではないとガレージライフは向いてないかもしれません。 [ライター・撮影/鈴木修一郎]

トヨタ2代目ソアラ(20系)の維持費は高い?内訳といくらかかるかを解説
ソアラといえば、1981年から2005年まで製造・販売されたトヨタ自動車の高級クーペです。初代が登場した際は高嶺の花として扱われていましたが、2代目の20系はバブル期と重なり予想を上回るヒットとなりました。現在は中古市場でも人気があり、状態によっては新車価格に匹敵する値段で取り引きされている個体も存在します。昨今の旧車ブームで欲しいと思っている方も多いかもしれませんが、古いクルマであるために維持費が気になりますよね。そこでこの記事では20系ソアラの維持費に関して解説いたします。 20系ソアラの特徴 20系ソアラは1986年~1991年に発売された2代目のモデルです。近未来的なデジタルメーターを採用し、贅沢な内装で高級欧州車にも引けをとらないクオリティを実現しました。バブル時代には、究極のデートカーとして若者たちからの人気を博しました。女子大生からも多くの支持を集め「迎えにきてほしい車ランキング」の上位に名を連ねていました。当時、ソアラは最高のステータスシンボルだったのです。 20系ソアラ維持費の内訳 ここからは20系ソアラの維持費について、5項目に分けて解説します。 燃料代 20系ソアラは2Lと3Lの2種類のガソリンエンジンモデルがあります。それぞれの燃費を見ていきましょう。 2.0L ガソリンエンジン:8.3〜10.4km/リットル3.0L ガソリンエンジン:7.4〜8.3km/リットル 10・15モードのカタログ数値は上記の通りです。実燃費は2.0Lで6〜7km/リットル、3.0Lで5〜6km/リットルほどといわれています。 ここからは金額をシミュレーションします。仮に通勤で人気の3.0Lエンジンモデルを使用し月間1,000km走行した場合、ガソリンは約182リットル使用(*1) し、燃料代は31,254円(*2) です。この条件で1年間走行した場合は、375,054円(*2) かかります。*1 燃費は5.5km/リットルで算出*2 2023年4月4日のハイオクガソリン1リットル当たりの平均価格171.9円で算出 自動車税 2023年4月現在、2019年9月30日以前に新車登録した場合2.5リットル超~3.0リットル以下の自動車税は51,000円/年です。20系ソアラの場合は車齢13年超えになるため、自動車税は重課税され58,600円かかります。 任意保険 20系ソアラの任意保険について大手のネット型保険で見積もりをしました。 <条件>年齢:30歳等級:6E使用目的:通勤・通学運転者:本人限定 <補償内容>対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):なし人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):3,000万円入院諸費用特約:なし車両保険:なし 上記内容でシミュレーションしたところ、総額が約57,000円/年で、車両保険はつけられませんでした。中古市場でどんなに値段が上がっていても、保険会社はプレミア価格を考慮しません。大変残念ですが、古いクルマで価値のないものとみなされ、補償を受けられないのです。 車検 20系ソアラの車検代について見ていきましょう。 <ディーラー車検の場合>自賠責保険:17,650円(24ヶ月)自動車重量税:50,400円(24ヶ月)※初年度登録から18年以上経過で算出印紙代:2,300円車検料:60,000円合計:130,350円※車検料は内容、整備工場などにより費用は増減します 注目すべきポイントは自動車税の重課税です。1.5トン超~2.0トン以下の重量税は32,800円ですが、初年度登録から18年以上経過した車両は二段階重課税され、17,600円も高くなります。 メンテナンス費用 最後にメンテナンス費用を見ていきましょう。20系ソアラのメンテナンスについては下記の費用がかかってきます。 ・洗車代・ワイパーゴム交換代・ウォッシャー液交換代・冷却水補充代・エアコンフィルター交換代・ヘッドライト交換代・エンジンオイル交換代・オイルフィルター交換代・ブレーキオイル交換代・エアクリーナー交換代 1年間でこれらの費用が発生します。高く見積もって5万円ほどを見込んでおけば良いでしょう。20系ソアラのタイヤ交換が発生する場合は高級車用のため10万以上追加でかかるケースもあります。 20系ソアラ年間維持費はいくら? 維持費の内訳を見てきましたが、20系ソアラの場合、合計でいくらぐらいになるのでしょうか。合計額を見ていきましょう。 <自家用車登録の20系ソアラ年間維持費>ガソリン代:375,054円自動車税:58,600円任意保険:57,000円車検:65,175円(2年ごとにかかる費用の半額分)メンテナンス費:50,000円合計:605,829円 月額では50,480円ほどかかる計算です。通勤で使用しない場合はガソリン代と任意保険料を下げられます。ローンで購入するとさらに月々の返済が発生し、月極駐車場を契約する場合は別途駐車場代が毎月かかってきます。 20系ソアラの維持費が高いと思った時の対処法 大排気量の定車は、維持費がどうしても高額になります。また、最終モデルでも発売から30年以上経過するクルマのため、こまめにメンテナンスする必要がありお金がかかります。20系ソアラの維持費が高いと思ったら、手放すことを検討してみてはいかがでしょうか。一昔前は10年落ち10万km以上走行したクルマは価値がないと言われていました。しかし、近年の旧車ブームの影響もあり、過走行かつ古いクルマでも高く売却できる可能性があります。

日産シルビアS14の維持費は年間48万円!内訳を徹底解説
シルビアといえば日産を代表するコンパクトなクーペモデルです。2ドアクーペモデルのデートカーとして爆発的人気を得たS13から一変し、S14型はボディサイズが拡大しパワーアップしました。発売当初は大型化によりS13型のような軽快感が失われたことで人気に陰りがありましたが、空前の国産旧車スポーツカーブームでS14型も現代の中古市場を賑わせています。しかし、購入しようと思っても約30年前にデビューしたクルマのため「古いクルマは維持費が大変そう……」と心配の方も多いですよね。そこでこの記事ではS14型シルビアにかかる維持費について解説いたします。 S14型シルビアの特徴 S14型シルビアは爆発的に売れたS13型シルビアの後継モデルです。当時のクルマはボディサイズがどんどん大きくなっていましたが、スポーツカーでは小さいほうが好まれました。S14型シルビアもボディが大型化したために人気が低迷。ガソリンはハイオク限定で維持費がかさんだことも一般市場での人気が伸び悩んだ理由の一つです。 しかし、近年の国産スポーツカーブームによってS14型シルビアに注目が集まっています。当時のクラシカルなデザイン、そして発売当初は不評だった大きなボディサイズも居住性の高さを見いだされ、S14ならではの魅力として車好きの心を掴んでいます。 S14型シルビア維持費の内訳 ここからS14型シルビアの維持費について、5項目に分けて解説します。 燃料代 まずはエンジンタイプ別に燃費を見ていきましょう。 直列4気筒 2.0L NA:10.0~12.0km/リットル直列4気筒 2.0L ターボ:9.2~11.4km/リットル 10.15モードのカタログ燃費で比較しました。実燃費はそれぞれカタログ値より2kmほど低くなる場合が多いといわれています。 それでは実際にいくらかかるのか金額をシミュレーションしていきましょう。人気のあった2.0リットルターボのMTモデルに計算します。 通勤で使用し月間1,000km走行した場合、ガソリンは約105リットル使用(*1)し燃料代は18,094円(*2)かかります。この条件で1年間走行した場合は、217,136円(*2)です。*1 燃費は9.5km/リットルで算出(実燃費)*2 2023年4月4日のハイオクガソリン1リットル当たりの平均価格171.9円で算出 自動車税 2023年4月現在、1.5リットル超~2.0リットル以下(自家用)の自動車税は39,500円/年です。S14型シルビアは最終モデルが1998年に発売されており、車齢が13年を超えます。そのため、自動車税は重課税され45,400円かかります。旧車の場合新車の自動車税と比較すると1年で5,900円も高くなってしまうのです。 任意保険 S14型シルビアの任意保険について大手のネット型保険で見積もりをしました。 <条件>年齢:30歳等級:6E使用目的:通勤・通学運転者:本人限定 <補償内容>対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):3,000万円入院諸費用特約:なし車両保険:あり車両保険(保険金額):20万円免責金額(1回目-2回目以降):5万円~10万円 上記内容でシミュレーションしたところ、総額が約115,000円/年でした。この金額のうち車両保険は約43,000円です。保険料の3割強を占める金額ですが、補償される金額は20万円。一般的に事故の多いスポーツカーは、どうしても車両保険が高額になってしまいます。 車検 S14型シルビアの車検代について見ていきましょう。 <ディーラー車検の場合>自賠責保険:17,650円(24ヶ月)自動車重量税:37,800円(24ヶ月)※初年度登録から18年経過で算出印紙代:2,300円車検料:60,000円 合計:117,750円※車検料は内容、整備工場などにより費用は増減します S14型シルビアは、重量税が1.0トン超~1.5トン以下に区分されます。同区分の一般的な現行モデルの重量税は24,600円ですが、初年度登録から18年以上経過した個体は2段階の重課税により37,800円かかります。また、古いクルマは故障が多く交換部品や整備が必要なことが予想されるため車検代は高額になる可能性があります。 メンテナンス費用 最後にメンテナンス費用を見ていきましょう。S14型シルビアのメンテナンスについては下記の費用がかかります。 ・洗車代・ワイパーゴム交換代・ウォッシャー液交換代・冷却水補充代・エアコンフィルター交換代・ヘッドライト交換代・エンジンオイル交換代・オイルフィルター交換代・ブレーキオイル交換代・エアクリーナー交換代 1年間でこれらの費用が発生します。高く見積もって5万円ほどを見込んでおけば良いでしょう。S14型シルビアのタイヤ交換が発生する場合はスポーツタイヤを購入する必要があるため追加で10万円以上かかるケースもあります。 S14型シルビア年間維持費はいくら? 維持費の内訳を見てきましたが、S14型シルビアの場合、合計でいくらぐらいになるのでしょうか。合計額を見ていきましょう。 <自家用車登録のS14型シルビア年間維持費>燃料代:217,136円自動車税:45,400円任意保険:115,000円車検:58,875円(2年ごとにかかる費用の半分)メンテナンス費:50,000円合計:486,411円 月額では40,000円ほどかかります。通勤で使用しない場合は燃料代と任意保険料を下げられるでしょう。また、ローンで購入するとさらに月々の返済が発生するほか、月極駐車場を契約する場合は別途駐車場代が毎月かかります。 S14型シルビアの維持費が高いと思った時の対処法 古いクルマは、自動車税と重量税の負担が大きいために維持費がかさんでしまいます。また、あちこちの故障や傷みが目立ってきやすく、修理や整備費用が跳ね上がる場合もあるでしょう。S14型シルビアの維持費が高いと思ったら、手放すことを検討してみてはいかがでしょうか。一昔前は10年落ち10万km以上走行したクルマは価値がないと言われていましたが、かつてのスポーツカーの人気が再燃しており、過走行でも高く売却できる可能性があります。 ※2023年4月4日時点のデータです

縁の下の力持ち「エンジンマウント交換」の重要性とは?
読者の皆様は「エンジンマウント」という部品をご存知だろうか? クルマのメンテナンスが好きな方は、なんとなく想像できると思う。 今回、意外と注目されていない部品「エンジンマウント」に注目をしてみたいと思う。 ■エンジンマウントってなに? 「エンジンマウント」とは、エンジンを“車体上に乗せる=マウント”するための部品である。 最近、巷で話題の“マウント”という言葉の意味は、確かに合っている(笑)。 エンジンやミッションは、マウントを介してクルマに固定されている。 部品自体は、ゴムなどのブッシュが内蔵された金属や強化樹脂製のブラケットになる。 取り付け時は、ブラケットが車体側・ブッシュがエンジン側になる。 ブッシュによってエンジンの振動が吸収され、車体側に伝わらない仕組みになっている。 トランスミッションにも同様のマウントが存在し「ミッションマウント」といわれている。 今回「エンジンマウント」と銘打っているが、ミッションマウントも同様と考えていただければと思う。 ■エンジンマウントがダメになったらどうなる? 交換歴がない旧車(20年以上経過)の多くは、すでにくたびれた状態になっている可能性が高いと思われる。 というのも、エンジンマウントは重量物であるエンジンを支えている部品であり、常に重さが加わり続けている状態である。 そのため、走行距離だけでなく、経過年数により劣化して、その免振機能が低下してしまう。 エンジンマウントが劣化したことに気が付くきっかけの多くは「振動」になる。 劣化によりブッシュが硬化してしまい、今まで吸収されていた振動が伝わることになる。 また、長年エンジンやミッションの重さを支えていたことから、ブッシュがつぶれてしまい、位置が下方向に落ちてしまうことがある。 そのため、エンジンやミッションの搭載位置にズレが生じてしまう。 ズレによって、他の部品へ負担がかかることや、スムーズなシフト操作を妨げることにも繋がる。 ■マウント交換は快適性UPに効果テキメン! 筆者の愛車で、劣化に気が付いたきっかけを紹介したいと思う。 1つ目は、AT車でリバースにシフトした際、振動が発生した。 アイドリングや走行をしていても問題となる症状はなかった。 しかし、車庫入れ等でリバースに入れた際、驚くほどの振動が車体を揺らしたのだった。 後退時、エンジンとミッションが普段と逆の方向に捩じれる動きとなる。 劣化したマウントの収まりが悪くなり、振動が発生していた。 交換する際、外した部品の見た目に大きな劣化は見られなかった。 しかし、新旧の部品を並べたところ、古い部品のブッシュ側の固定点位置が下がっていることがわかった。 事実、マウント交換後はエンジン位置が今までよりも高い位置になったのだ! それだけ、マウントは劣化して搭載位置が下がってしまっていたのだった。 2つ目は、MT車でクラッチを繋ぐ際、ジャダーのような振動が発生した。 この振動の原因は、ミッション側のマウントの破断が主な原因であった。 交換時、取り外したマウントは劣化して切れた状態となっていた。 車両は、走行距離10万kmの2001年式 三菱 トッポBJである。 同じく10万km目前の2000年式ダイハツ ミラでも、ミッション側のマウントが破断していた経験がある。 両車ともにMTであり、ミッションマウントへの負荷が大きいのかもしれない。 助手席側のタイヤハウス内、アクセスしやすい場所にあるマウントである。 もし、読者の方で同様の気になる振動がある方は、確認されてみてはいかがだろうか。 ■強化品という選択肢も! エンジンマウントには、強化品も存在している。 封入されたブッシュが標準よりも硬いものと思っていただければ、イメージしやすいと思う。 強化品がラインナップされている目的としては、モータースポーツ用途のためである。 TRDやNISMOといった自動車メーカー系ブランドからもリリースされている。 加減速時、エンジンやミッションは大きく揺れや傾き・捩じれといった動きをする。 街中を普通に走る分には、気にならない程度の動きである。 スポーツ走行をする場合、高負荷がかかり動きも大きくなるが、可能な限り小さくしたい。 強化マウントは、それらを抑える役割を担っており、アクセルレスポンスやシフトフィーリングが向上する。 調べたところ、すでに旧車の域に入っている人気スポーツカーにも設定されている。 車種によっては、純正部品が製造廃止になっていることも、おおいにあり得る。 その場合、強化マウントを流用するといった対応策も選択肢の一つとして可能となる。 強化マウントではあっても、劣化した本来の性能が出せていない標準のマウントと比較して、快適性や操舵性能が良くなることは間違いない。 そしてほんの少し、スポーティになる副産物がついても来るのだ(笑)。 ■まとめ:エンジンマウントは縁の下の力持ち! エンジンマウントは、快適な車内空間を保つ、縁の下の力持ちなのである。 常に支え続けていることで、距離は走っていなくとも劣化してしまう。 気になる振動が出ている場合、マウントの劣化を疑って、早めの交換をオススメしたい。 快適性向上だけでなく、他部品への負担軽減にも繋がり、より長く愛車との時間を過ごせることに繋がるだろう。 [ライター・撮影/お杉]

常に一難去ってまた一難?愛車スバル360のDIYレストアについて
一昨年、自宅から「車庫証明が取れなくもない程度」に離れた場所にガレージを借りて、スバル360のDIYレストアを再開したのは、以前、記事に書いた通りです。 そこで、ふとスバル360のレストアっていつから始めたんだっけ?と思い返してみると・・・。 セリカLBがレストアから戻ってくるタイミングと入れかえだったので、2016年末、気が付くと6年も経っていました。 そう考えると、フルレストアをしたばかりだと思っていたセリカLBも、レストアから6年経過していたことになります。 フルレストアしたことで、これまで見落としていた不具合が洗い出されるように発生してはその対処に追われていたので、あっという間でした。 このあたりの話も、いつか触れることができたらと思っています。 ■ボディは想像以上に腐食していた 当初は各部の浮いてきた錆をサンダーで削り落として、錆止め剤を塗布してサフェーサーを吹けばと思っていたのですが・・・。 フロントフェンダーやフロントエプロンを外すと、左のフロントサブフレームがこの有様。 腐食というより、溶けてなくなっているという状態です。 察しの良い方の中にはシャシーブラックがマスキングしたかのように途切れており、違和感を感じる方もいるかもしれません。 実はこのシャシーブラックの途切れている部分には、FRPが貼ってありました。 そのFRPも加水分解をおこし、もはや部材としての用を成してない状態です。 今でも、腐食部分の補修にFRPを紹介する事例も散見します。 FRPは錆びないことをメリットに挙げる例もありますが、10年~20年スパンで見ると加水分解で腐食と同じ結果です。 それどころか、加水分解でボロボロになった箇所や、はみ出たグラスマットが水を含んでしまい、錆を進行させる原因にもなります。 個人的にはFRPでの補修は好ましくないと考えています。 なにより、この状態で何年も走行し、ときには高速道路も走っていたと思うとゾッとする話です。 昔からスバル360はバッテリートレーの部分がバッテリーの液漏れで腐食しやすいことが知られています。 しかし、近年はさらにバッテリートレーだけでなく真下のサブフレームにも腐食が進行する個体も見受けられます。 心当たりのあるスバル360のオーナーは一度確認し、状態によってはレストアを考えた方がいいかもしれません。 ■厚盛りパテの洗礼 あちこちパテが割れていて覚悟はしていたものの、試しに右フロントフェンダーにグラインダーをあててみたところ、ミリ単位どころかセンチメートル単位でパテが盛ってあったのです。 自分のセリカをレストアした整備工場の社長は「鈑金は基本ハンマリングで成形、パテはハンマーの打痕の傷消しに使うだけ」という「パテを使わない鈑金」をする人です。 とはいっても付け焼刃で真似できる物でもなく、せめて数ミリ単位に抑える方向で頑張っています。 しかし、パテを剝がしていくと、過去に事故でひしゃげたフェンダーを鈑金修理したものということが判明します。 事故による全体のゆがみが酷くヘッドライトベゼルとフェンダーの曲面がまったく合いません。 ホイールアーチのアールもくるっていて、このフェンダーの再生は断念。 結局、ひずみのないフェンダーを探すのに1年ほどかかりました。 ■ボディの腐食の進行は思いのほか重症だった 元々、閉まりの悪い右ドアは諦めて(今までと比べれば)状態のいい中古ドアに交換します。 このあたりから、モノコックだけの状態にしてから腐食部分をすべて直さないとだめだと思うようになり、エンジンミッション・サスペンション・ステアリング・電装系ハーネス、すべて取り外すことにしました。 錆びた部品はサンドブラストで処理できれば一番いいのですが、錆取り剤に漬けおきでもかなり効果があります。 そこで、一晩漬けてワイヤブラシでこすれば、おもしろいように錆が取れました。 錆取りといえば、サンポールやクエン酸も有名ですが、母材への影響や安全性もメーカーが確認している専用の錆取り剤を使うようにしています。 もちろん、このあとは錆止め剤を塗布してシャシーブラックで塗装したのですが、結局最近になって、より強固な二液ウレタン塗料で塗りなおそうかと思っています。 下地を塗装し、塗料店を通じて塗料メーカーに純正カラーコードで調合してもらった二液ウレタン塗料まで用意したところで、どうやって塗装するかという難題にぶつかります。 ソリッド色ならパネル1枚1枚を塗装して研いで修正ということもできます。 しかし、このクルマはシャンパンゴールドのメタリック塗装。 クリアコートまで一発勝負ということにここにきてようやく気づいたのでした。 ゴールド+クリアの2コートを一気に仕上げるには簡易的な塗装ブースでもいいのですが、建屋内で作業する必要が出てきてしまいました。 その後、「ガレージを借りる」という大技にたどりつくまでに3年ほど要することになるのです。 [ライター・撮影/鈴木修一郎]

ロードスターで故障しやすいのはどこ?故障してしまった時の修理費についても解説
ロードスターは現在でも新車販売されている国産の小型スポーツカーとして、人気の高い車です。現行のND型でも登場は2015年で、すでに8年近くが経過しています。そろそろ長期使用による不具合も明らかになってきました。本記事ではロードスターの故障しやすい箇所と故障した際の修理費について解説します。 ロードスターのよくある故障箇所 ロードスターでよく見受けられる故障箇所は、主に以下の5箇所です。ここからは、よくある故障を一つずつ解説します。 エンジン 4代目ND型ロードスターでは、エンジン内部の汚れによる不調があるようです。。ND型ロードスターに搭載されるエンジンは直噴エンジンです。直噴エンジンは、燃焼効率が高い反面、ガソリンの燃焼によって発生するカーボンなどがエンジン内部に堆積しやすいことが欠点といわれています。。また、カーボンは吸気ポートやピストン室内に燃料を噴射するインジェクターなどにも堆積し、燃料の噴霧状態が悪化することによって、エンジン振動が大きくなったり、出力が低下したりするなどの現象が発生します。 3代目NC型ロードスターでは、冷却水に関するトラブルが頻繁に見受けられます。具体的には、電動ファン用のモーターが故障し、エンジンの冷却が正しくできなくなり、エンジンがオーバーヒートするといったケースがあります。 2代目NB型ロードスターでは、燃料ポンプの故障が多いようです。NB型ロードスターの燃料ポンプは寿命が短い傾向があります。この燃料ポンプが故障すると、正常な燃圧が得られなくなり、不具合が起きてしまいます。 エアコン エアコンの故障は、ND型ロードスターで頻繁に見受けられるといいます。 エアコンを構成するパーツの中でもコンプレッサーに異常が生じることは多くありません。しかし、コンプレッサー以外の部品の不具合によって異常が起こり、結果としてコンプレッサーの故障へと繋がっている事例があるようです。 このような故障の場合、コンプレッサーだけの交換では済まないために、修理費が高額になるケースもあります。 オルタネータ 車の発電機であるオルタネータは、エンジンの駆動力によって走行中に発電し、車の走行やライトの点灯、エアコン、オーディオなどが必要とする電力を発生させる重要なパーツの一つです。 そのため、オルタネータが壊れてしまうと発電ができなくなり、走行不能になる場合もあります。また、オルタネータで発電できなくなる前に、エンジンの回転をオルタネータに伝達するプーリー軸のベアリングが壊れることもあります。ベアリングが故障した場合、異音が発生するため、異常を感じたら早めに点検をしましょう。 他にもオルタネータには、スリップリングとブラシという消耗部品があります。これらの部品はいずれ故障やトラブルなどが発生することから消耗部品と考えておくとよいでしょう。 パワーウインドウ ロードスターのパワーウインドウのトラブルは、初代NA型からある不具合の代表例です。 ロードスターのパワーウインドウを動かすモーターやワイヤーなどのパーツは、ドア内部でむき出し状態になっているケースが多く、ドア内部に侵入した水分によって部品が錆びたり劣化したりしやすい環境となっています。そのため、突如パワーウインドウが動かなくなったり、ワイヤーが切れたり、異音が聞こえたりするという事例が多く報告されています。 ソフトトップの雨漏り ソフトトップは、布製の幌です。そのため、鉄板に塗装がされた他のボディパーツに比べれば外的環境に弱い部品といえます。 日差しが強い日中は紫外線に晒され、頻繁に開閉動作をすると擦れることがあるため、劣化は避けられません。 ソフトトップが劣化したり、切れたりすると、雨漏りが発生します。そのため、ソフトトップオープンカーであるロードスターを所有するときは、なるべく直射日光や雨風に晒される環境を避けて保管するとよいでしょう。 また、ソフトトップのオープンカーを楽しみたいのであれば、幌は、消耗品の一部として認識する覚悟も必要かもしれません。 ロードスター修理費の目安 ここまでに紹介した故障の修理費の目安は、以下のとおりです。あくまでも目安であるため、実際に修理が必要になった際には、修理を依頼するディーラーやサービス工場でまず見積もりをしてもらいましょう。 【エンジン】・NC型の電動ファンモーター交換:部品代3万円+工賃3万円=合計6万円低度・NB型の燃料ポンプ交換:部品代で3万円程度 【エアコン】・10万円〜20万円程度(交換部品によって修理費が異なります) 【パワーウインドウ】・1箇所につき2~3万円程度 【ソフトトップの雨漏り】・一般的な相場:約5万円~ ロードスターの維持費が高いと感じたら売却がおすすめ ロードスターの維持費が高いと感じたら、売却を検討するのも一つの方法です。 ロードスターは、世代によってリビルト品や中古部品などのパーツ確保が難しいことがあります。パーツの入手が困難で、修理代が高くなる場合には、売却を検討した方がよいでしょう。 旧車王(リペアマニア)なら故障者でも買取できる もし、故障したロードスターの修理費が高くなってしまい、手放そうと考えた場合、「リペアマニア」への売却がおすすめです。 リペアマニアは、旧車の買取を得意とするカレント自動車が自動車再生事業として運営しており、動かなくなった車も買い取ってもらえる点が大きな特徴です。 一般の自動車買取業者では、故障している車の価値は非常に低くなってしまいます。しかし、自動車再生を事業としているリペアマニアであれば、故障車であっても高く買い取ってもらえるため、故障したロードスターを売却するときにおすすめです。
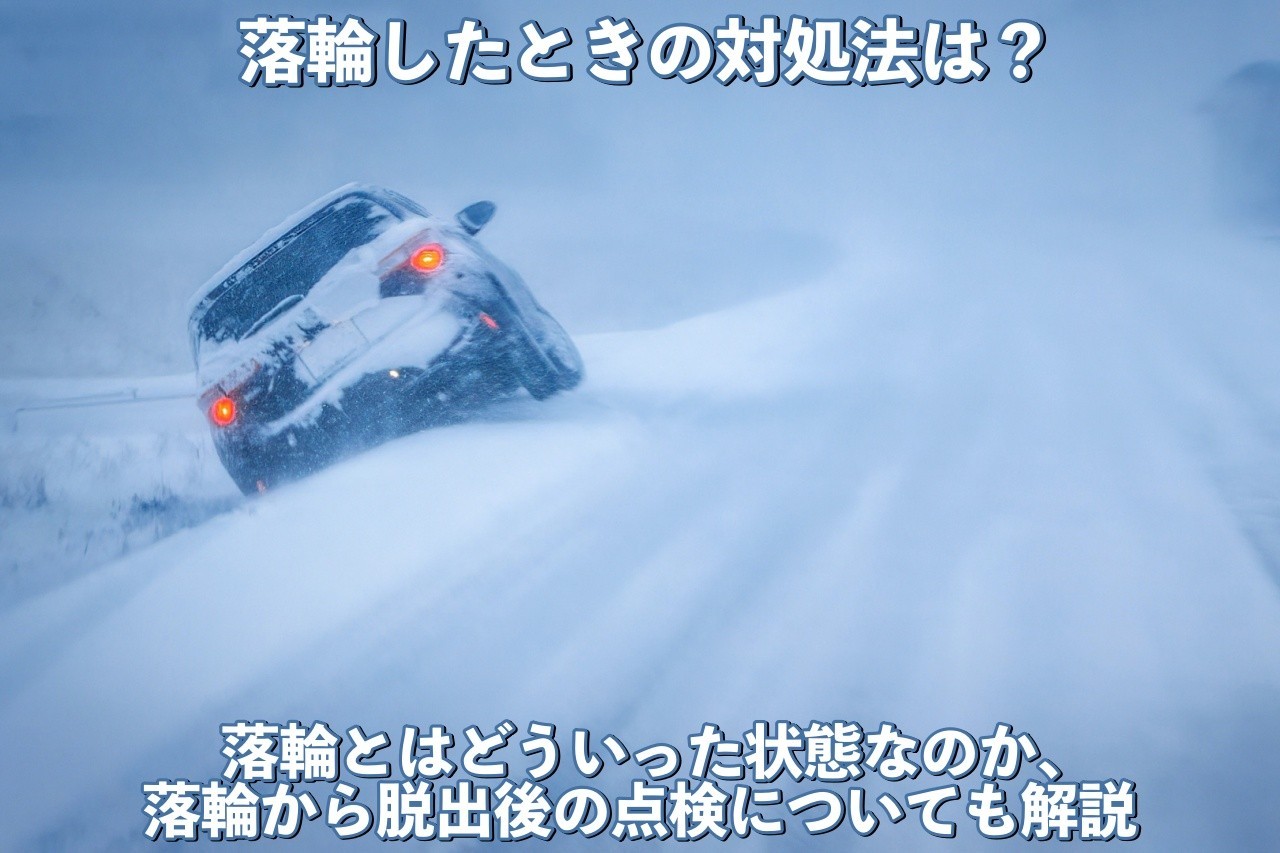
落輪したときの対処法とは?脱出方法や脱出後の点検について解説
落輪とは、クルマのタイヤが道路外に落ちてしまって動けなくなることです。道路の側溝に落ちた場合だけでなく、縁石に乗り上げたり雪や泥でスリップして走行不能な状態も同じ意味として使われます。 落輪したときにどう対処すればよいのか知らない方も多いでしょう。そこで今回は、落輪したときの対処法や、落輪から脱出した後の点検などについて解説します。落輪からの脱出に不安のある方は参考にしてください。 落輪したらまず何をする? 万が一落輪してしまった場合には、まず周囲に危険な状況であることを伝える必要があります。 落輪したら早めにハザードランプをつけて、発煙筒や三角表示板を50mくらい後方に設置しましょう。発煙筒はクルマに搭載されているため、あらかじめ使い方を把握しておくと安心です。三角表示板は備え付けられておらず、カー用品店で販売されています。車載義務はないものの、事故発生時に表示しないと違反とみなされるため注意しましょう 落輪したときの対処法 続いて、落輪したときの対処法について詳しく解説します。 牽引ロープで引っ張ってもらう 雪道やぬかるみにはまってタイヤが空転する場合は、牽引ロープで引っ張ってもらいましょう。車重のあるクルマを牽引するときは、引っ張る側が大きなトルクを発揮できるクルマの方がスムーズに脱出できます。また、牽引ロープを引っかけるフックは着脱式のタイプも増えているため、普段から自分のクルマの牽引フックの場所やタイプを確認しておくとよいでしょう。 複数人で持ち上げる 同乗者や周囲の人たちの助けが借りられる場合は、複数人でクルマを持ち上げて脱出できます。持ち上げる人はケガの予防のために準備運動を行い、備えがあれば軍手などを装着しましょう。持ち上げるときに掛け声をかける人を決めておくとタイミングを合わせやすくなります。 保険会社のロードサービスを利用する 落輪の状況によっては牽引では対処できないこともあるため、ロードサービスを利用しましょう。自動車保険の付帯サービスで利用できることも多く、状況によっては無料で対応してくれます。万一のときにすぐにロードサービスを利用できるよう連絡先を控えておきましょう。 JAFに依頼する 地域や落輪状態によっては保険会社のロードサービスを利用できない可能性があります。JAFに会員登録しておくと広範囲で迅速な対応を受けることができ、簡易な作業であれば費用負担もありません。また、保険契約車ごとの適用である自動車保険のロードサービスに対して、JAFは会員証ひとつでレンタカーやバイクまで対応してくれます。 溝が浅い場合はタイヤの動力で脱出する 溝が浅い場合はタイヤの動力で脱出できます。駆動輪が地面に接していることが条件となるため、すべてのタイヤの接面状況を確認しましょう。雪道や砂面、ぬかるみなどではタイヤが滑りやすくなっているため、アクセルをゆっくりと踏んでタイヤの動力をうまく伝えることが重要です。状況によってはフロアマットや板などを敷くとよいでしょう。 自力で脱出する場合の手順は次のとおりです。 ①安全の確保 後続車の追突を避けるためにハザードランプを点灯させ、三角表示板などの停止表示器材があれば車の後方に設置します。車通りが多い道路では発煙筒などを併用するのもよいでしょう。 ②同乗者の安全確保 同乗者がいる場合は万一に備えてガードレールの外や歩道など、安全な場所に避難してもらいましょう。 ③クルマの状態を確認する 落輪箇所や他のタイヤの接面状態を確認します。溝が深い場合や駆動輪が浮いている場合は、悩まずにロードサービスや周囲の人に助けを求めましょう。 ④脱出する 脱出時に他車への衝突や歩行者への危険がないかしっかりと確認したうえで、ハンドルを脱出方向にきりながらアクセルをゆっくりと踏んで脱出します。また、デフロックが装備されている4WD車の場合は、デフロックをONにしてから脱出を試みると、スムーズに抜け出せ ジャッキで持ち上げる 協力者がいない場合はジャッキを使用して持ち上げましょう。クルマの脱輪箇所をジャッキアップして溝に板などを敷くことで脱出できます。ただし、やわらかい地面でのジャッキアップは危険なため、事前に状態の確認は念入りに行いましょう。 落輪から脱出した後は必ず点検しよう 落輪から脱出した後は安全な場所にクルマを停車させて必ず点検しましょう。側溝に落ちたり縁石に乗り上げた場合はタイヤのパンクや足回りの損傷、エンジン下部からのオイル漏れが発生する可能性があります。また、ホイールアライメントが狂ってしまうとタイヤの偏摩耗や直進安定性が悪くなるといった不具合が生じることもあるため、走行中に違和感を感じたらすぐに点検に出しましょう。

車の横風対策とは?横風が起きやすい場所や対処法も解説
走行中に突然車がふらつき、ハンドルを取られた経験がある方は多いのではないでしょうか。車がふらつく原因の多くは、強い横風を受けたことでしょう。近年は暴風災害時に横風によって転倒した車をニュースで目にする機会も増えました。本記事では強い横風の中で運転する際に気をつけるべき点について、詳しく解説します。 横風が起きることが多い場所 車が横風を受けやすい場所には、トンネルの出口、高層ビルの間、カーブの多い山間部、海沿いや長い橋などがあります。自然に吹いている風が強くなくても、風の流れが局部的に遮られる地形や、建造物がある場所においては、強い横風を受けやすくなります。逆に風を遮るものがなく、強い風を受けやすい広い場所では、自然に吹いている風を、そのまま横風として受けてしまいます。 風速と速度規制・通行止めの関係 車が走行中に横風として受けた風は、同じ風速であっても車の走行速度が速いほうが、一層ふらつきが大きくなります。そのため高速道路など走行速度が速くなる場所には、瞬間風速に応じた速度規制が設けられています。強風による速度規制は、以下のとおりです。 瞬間風速がおおむね10メートル未満の場合 必ずしも最高速度規制は行われませんが、高架部、橋りょう部などにおいては状況によって最高速度規制が行われます。道路の情報案内板には「横風・走行注意」が表示されます。 瞬間風速がおおむね10メートル以上、15メートル未満の場合 中央分離帯のある道路では最高速度は80km/hに規制されます。状況によっては規制は強化され、二輪車、幌付トラック、高積載車等は通行止めの規制を受けることもあります。情報案内板には「強風・速度落とせ」「80キロ規制」などと表示されます。 瞬間風速がおおむね15メートル以上、20メートル未満の場合 中央分離帯のある道路、中央分離帯等がない非分離の道路いずれにおいても、最高速度は50km/hに規制され、二輪車は通行止めになります。状況によっては幌付トラック、高積載車等は通行止めの規制を受けることもあります。情報案内板の表示内容は「強風・速度落とせ」「50キロ規制」などです。 瞬間風速がおおむね20メートル以上の場合 高速道路では通行止めになります。情報案内板には「強風・通行止」「ここを出よ」などと表示されます。 横風にあおられたときの対処法 車の運転中に横風でふらつきを感じた際には、決して慌てずに減速することを心がけましょう。強風が吹いているのであれば、雨が降っていて道路が滑りやすくなっていることも考えられます。急ブレーキにならないよう、まずはアクセルから足を離して、前後の車間距離に気をつけながら、減速しましょう。また急なハンドル操作を避けることも、覚えておいてください。 横風による事故のリスクを抑える対策 横風による車のふらつきが起これば、交通事故に至るリスクが高まります。そこで事故発生のリスクを抑える対策について3つ覚えておきましょう。 ルーフキャリアーは入念に固定する ルーフキャリアを搭載していれば、走行前に十分に固定されているか、入念に確認しましょう。もしも横風によってルーフキャリアがズレてしまうと、車の重心が急激に変化し、車のふらつきは一層大きくなってしまいます。ましてやルーフキャリアが脱落してしまったら、後続車に重大な事故を与える原因になりかねません。 シートベルトを必ず装着する シートベルトの着用は、横風による車のふらつきを抑える対策ではありませんが、万が一車が転倒してしまったり、ガードレールなど道路沿いにある構造物と接触してしまった際など、私たちが受けるダメージを低減してくれます。シートベルトは2008年から全ての座席で着用が義務化されました。けがや障がい、妊娠などの理由がない限り、シートベルトは必ず着用しましょう。また身体の小さな幼児を乗せる際には、チャイルドシートが必要です。 車間距離を十分に空けてゆっくり走る 車が横風を受けてふらつくのは、自分が運転している車だけとは限りません。自車はふらつかなくても、周囲を走行しているトラックや、背の高い車がふらつく可能性があります。強風が吹いている際には、普段よりも車間距離を十分に空けて速度も控えめに、ゆっくり走ることを心がけましょう。 横風の影響を受けやすい車の特徴 横風の影響を受けやすい車の特徴は、背が高いことです。横から同じ力を受けた場合でも、より道路から離れた高い位置で横風の力を受けたほうが、よりふらつきが大きくなります。車のカテゴリーとしては、大型のトレーラーやトラック、乗用車なら1BOXカー、特にハイルーフという普通のボディよりも背を高くした車は、横風に弱いといえるでしょう。 軽自動車で、トールワゴンやハイトワゴンなどと呼ばれる車種も同様です。また車の背は低くてもルーフキャリアを取り付けて荷物を積んでいれば、横風によってふらつく可能性が高いと言えます。また外見から判断することは難しいですが、同じ程度の形をした車であっても、重心が高い車や車重が軽い車のほうが、横風によってふらつきやすい傾向があると考えられます。
