「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
「旧車」の検索結果

日本アルミ弁当箱協会会長の「ちょっと斜めから見た旧車たち」Vol.4
第4回 ~アルミ弁当箱と旧車の意外な関係~ どうも!「日本アルミ弁当箱協会」会長のマツド・デラックスでございます。 今回からは「アルミ弁当箱と旧車の意外な関係」を語っていきたいと思います。 ■アルミ弁当箱全盛期はクルマ社会の全盛期でもあった このタイトル。旧車王の記事としては逆なんでしょうね(編集部注:そのままいきます)。 「クルマ社会の全盛期は、アルミ弁当箱にとっても全盛期」なんでしょう。 しかし、アルミ弁当箱協会の会長としてはあえて逆から行きたいと思います。 魔法使いサリー 「え?」と思う方と「なるほど!」と思う方、両極端に分れる作品がこの「魔法使いサリー」です。 1966年(昭和41年)といえば、自動車産業が活発化し、各メーカーが名車と呼ばれる「大衆車」を世に送り込む世代でもありました。 そんな中放映されていた魔法使いサリーも例外ではなく、自動車産業の影響を受けていたのです。 実はタイトル変更はあのクルマとは無関係? まず、よく話題になるのは「魔法使いサリー」のタイトルです。 この漫画の最初のタイトルは「魔法使いサニー」だったのは有名な話です。 そしてタイトル変更の理由として流れていた都市伝説は「日産が許可をしなかった」でした。 しかし、どうもこれは間違いで、許可されなかったのは他の会社で商品登録名があったからだそうです。 たしか家電メーカーだったはずで、日産も車種名としてその会社に使用許可をもらっていたそうです。 それが日産の大衆車「サニー」だった、というわけです。 現在車種名として残っていないのも、使用許可年数が過ぎたからという説もあるとのことです。 ■クルマの話題が多かったサリーちゃん そんなことが話題になったかならなかったのかは定かではありませんが、「魔法使いサリー」は「クルマ」にまつわる話題が多かったような気がします。 よっちゃんのお父さんの仕事は個人タクシーの運転者だったり「交通戦争(もう死語かもしれません)」を題材に物語があったり・・・。 極めつけのエピソードとして、主人公のサリーちゃんと弟のカブが「ラリー」に参加するという、実にマニアックな展開のエピソードまであったほどです。 そして、このラリーのエピソードで2人が乗るクルマを魔法で選ぶのですが、サリーちゃんは「私と同じ名前のサリーにするわ」といい、カブは対抗して「カブリカ」を選びます。 もちろん、日産の「サニー」VS トヨタの「パブリカ」というわけ訳です。 当時の制作スタッフも粋なことをするものですね。 ・・・といった具合に、アルミ弁当箱に描かれている作品には意外とクルマに関係する作品があるんです。 というわけで、今回の「斜めから見た旧車たち」は「サニー」と「パブリカ」にスポットを当ててみました! まったく脈絡のないコラムではありますが、旧車王ヒストリアだけでなく「マツドデラックスコレクション アルミ弁当箱図鑑」もよろしくお願いいたします。 ●アルミ弁当箱図鑑 厳選50 ーマニア編ー マツドデラックスコレクション (ヴァンタス) | マツド・デラックス https://www.amazon.co.jp/dp/4907061471 ●日本アルミ弁当箱協会会長「アルミ弁当箱図鑑 厳選50 」出版への道https://www.qsha-oh.com/historia/article/matsudo-bangai-1/ またアルミ弁当箱を並べて欲しい等とご要望のある方も是非お声をかけてください。 ●日本アルミ弁当箱協会ホームページhttps://kyokai.fans.ne.jp/arumibenntou/ ●Twitterhttps://twitter.com/keisuke38922 次回はイベントで10月30日に開催される「ISUZUオーナー集会」に参加、展示予定です。 こちらもぜひよろしくお願いいたします! [撮影/ライター・マツド・デラックス(山本圭亮)]

旧車の冬対策はどうすればいい?寒い冬でも旧車を快適にドライブするコツを解説
冬に旧車を運転していて、寒いと感じたことはないでしょうか。旧車の気密性やエアコン性能によっては、寒さを感じる場合があるかもしれません。あまりにも寒いと車を運転したくなくなり、生活にも支障をきたす可能性があります。そこでこの記事では、旧車でも寒さを気にせずに使うためのコツについて詳しく解説します。 旧車は現代の車よりも寒い? 旧車の古さの程度にもよりますが、旧車は現代の車よりも寒い場合があります。車の設計や製造技術が低い時代であれば、ドアの隙間から車内に冷気が入ってきやすいでしょう。パッキンの劣化で気密性が低下していることもあります。 旧車の冬対策の方法 大きな空間を温めようとすると、大きなエネルギーが必要です。そこで冬対策のコツは、温めるところは必要最小限にすること、寒さを感じる肌の部分を集中的に温めることが効果的です。それでは、旧車の冬対策の方法について詳しく見ていきましょう。 温かい衣類を着用する まず暖かい衣類を着用することが基本です。アウターだけでなく最近はユニクロのヒートテックに代表されるような、薄くても保温性の高いアンダーウェアも多く出回るようになりました。これらの多くは吸湿発熱繊維という、人の汗で発熱する素材が使われています。効果的に取り入れましょう。 ヒーターを設置する ヒーターの利用も効果的です。ヒーターには大きく二つのタイプがあります。一つ目は温風タイプ。ダッシュボード等に取り付け、温風を吹き出すことで温めてくれます。二つ目はシートタイプ。人の肌に近い部分を直接温めるので、効率よく温かさを感じることができるでしょう。温風タイプもシートタイプも、電源はシガーソケットを使います。 保温性のあるシートカバーを使う 電気を使わなくても、保温性のあるシートカバーで温かさを感じることができます。シガーソケットの電源が使えない場合には効果的でしょう。 真冬は乗らない 真冬の寒い時期には旧車には乗らない、他の車を使う、または別の移動手段を選択するのも対策の一つと考えましょう。公共交通機関を使う、近距離であれば暖かい服装で自転車を使うと、運動によって身体を温めることもできます。

絶対楽しい旧車ライフ超入門!!その3 旧車を複数所有し使い分けるともっと楽しい
■エピソード1:なんとなく始まった旧車複数所有生活 ボクはバランス至上主義の天秤座生まれ。 当然、義務教育とオプション教育の年数バランスにもこだわり(?)、6-3-3-6(最後の6は、1年の休学と留年を含む)という学生生活を送っている。 その最後の年となった1978年、学生時代最後のクルマとして、ふと目が合ってしまった1964年式のボルボ1800Sを購入したのだ。 当時は旧車という概念がなかったけど、「品5」ナンバーだったし、今なら普通に2年車検だけど、当時は11年以上経過すると1年車検だから明らかに旧い。 でもね、カッコイイんだこれが!! 気に入ってブイブイいわせていたけど、流石に北国のクルマ、冬は良いのだろうが、夏の室内は我慢大会の決勝レベル。 そこで借金して、マイカー初のクーラーを付けてもらうことになった。 いやぁ涼しい! こちらの画像はスウェーデン工場生産になって車名が「P1800」から「1800S」になった直後のモデルだ。 翌年春、卒業して某国産車ディーラーに勤めたのだが、ボルボは車検が近いし、エンジンやミッションのマウント劣化が激しく修理費用がかかる。 そんなとき、車検が1年ほど残ってるけど、いらなくなったから乗ってよ、ってなわけでホンダLN360がやってきた。たしか70年式あたりだから約9年落ち。 今の感覚では、まだまだ旧車というにはほど遠い存在だったけど、当時は、10年も経ったらポンコツのオンパレードという時代だったから、一般的な視線では旧いクルマに見えたはずだ。 まぁ、クルマを購入、維持するために必死になってバイトをしていた若造のボクは、あっという間に複数所有が成立して大喜び。 まるでおぼっちゃまになったような気分を味わったものだ。 こちらの画像はLN360のカタログの一部。 都内を走る分には不満のないパワーで、当時一緒に暮らしていたワンコとのドライブを楽しんだ記憶がある。 ただ第一次複数所有時代は、約半年という短期間のうちに終了した。 初任給の段階ではボルボの修理と車検は難しく売却することになったからだ。 LN360も、通勤用にコロナHT2000EFI-SLを入手した際に手放すことになった。 短い時間だったが、目的に応じてクルマを使い分ける喜びや楽しさを実体験できたことは、とても幸運だったと思う。 ■エピソード2:複数所有は楽しさ倍増、ただ…… その後も、一時的に複数所有することもあったサラリーマン時代だが、2台以上が旧車といえるパターンは皆無だった。 多くの場合、複数所有の基本は、好きなクルマと普段使う実用車って構成だから、旧車が好きで所有するなら、当然2台目は普通に快適な現代のクルマとなる。 その常識的複数所有パターンが一気に崩れたのは、独立2年目となる1989年のこと。 当時愛用していた新車で買った趣味兼実用のホンダCR-X Siに加え、今も所有する69年式フェアレディSRLを手に入れたのだ。 そのキッカケは、新車購入のCR-X Siの走行距離である。 起業し、通勤、営業、取材、そしてストレス解消の峠走りと大活躍してくれたのだから、 走行距離がガンガン伸びるのは当然だけど、2年弱で10万キロも走っていたのだ。 そろそろ買い替えを…と勧めてきた営業マンに、過走行だから査定の減点がナンチャラと言われてショックを受け、複数所有で走行距離の分散が必要と考えたわけだ。 冒頭の画像は69年式フェアレディSRL311。 89年に日本に帰ってきた帰国子女で、国内最初のオーナーがボク。 今も溺愛している最愛の個体だ。 まぁ、ここまでは自然な流れだったけど、その直後、事態は急変。 付き合いのあったアメ車屋さんから79年式ポンティアックファイアーバードトランザムが、自動車趣味の仲間から70年式スバル1300Gスポーツが同時期に転がり込んできたから、大きな変化に対応するため走り回った記憶がある。 さらにその半年後には、73年型1303Sと76年型1200LSと、2台のVWビートルまで加わり、一気にひとりと6台の大家族となってしまったわけだ。 予期せぬ出会いから無計画かつ強引な増車……ある意味ボクらしいできごとだった。 もちろん、好きなクルマがいつでも身近にあるのは幸せだったが、当時はバブル真っ盛りで、年中無休24時間営業の超多忙な毎日。 とても楽しむ余裕なんてない。 そこで、楽しむために乗れないなら仕事に使っちゃえぇ!! と割り切り、取材や納品、外注先との打ち合わせなど、あらゆるシーンで遠慮なく活用し、コンディション維持に努めていた。 突如訪れた大家族生活で、コンディション維持走行同様苦労したのが自動車税だった。 当時の税額だと、トランザム1台だけで16万円コースだったから、とてもキツかった。 駐車場確保も大切な責務。 でも、自分の性格上、クルマがドンドン増えそうな予感がしたので、あらかじめ農業用倉庫を借りていたので救われた。 ただ、置き場があっちこっちになるのはねぇ……。 台風なんかがくると、クルマが心配でじっとしていられなくなってしまう。 多くの旧車に囲まれた生活は喜びも絶大だが、心労が絶えないのも事実と知ったのだ。 ■エピソード3:ナンバーは選ばず、偶然あてがわれたナンバーを楽しむ!? ボクはある時期哲学にハマっていた。 特にC.G.ユングの提唱した理論である「共時性」には強く共感したのだが、それは、思念のエネルギーと偶然の事象に「関連」を感じていたからだ。 身近な例では、電話番号の下4桁やクルマのナンバーがそれ。 初めて就職した会社の配属先の電話番号下4桁が「9771」で、結婚して最初に借りたアパートに付けた電話の番号下4桁が「7197」。 転職して京都に移り、初めて買ったマンションの部屋が「519号」で、そのときの電話番号下4桁が「5195」だからシンクロしてるように思えるでしょ。 最近でも、「3867」のクルマを代えたら「3864」になって、それを代えたら「3877」だから、なんとなく偶然の引き寄せ現象を感じちゃう。 さらに、その時期に買い足した1台が強烈だった。 友人であるショップオーナーは、910型ブルーバードのバンだから、ナンバーは910にするだろ? と提案してきた。 しかしボクは、偶然の一致を予感するから指定はしないで、と頼み、自分のメモの隅に、多分ナンバーは「38〇〇」or「〇〇77」?と書いていた。 そうしたら、そのナンバーが「8677」!! 笑っちゃうでしょ。 ショップオーナーも驚いていましたよ(^^) この連鎖は、それが最後になって、その後GETした2台には継承されなかったけど、思念が偶然を引き寄せたようで興味深い。 だからボクは意図せずに回ってきたナンバーとともに歩み、次のシンクロを楽しみにしているのだ。 ■エピソード4:2シーターシンドローム 複数所有のメリットは、使用目的に応じたラインアップを構築できること。 例えばボクの場合なら、 1.フェアレディ2000、2.車中泊も快適なミニバン、3.仕事機材が積みやすく機動性に優れる小型ステーションワゴン4.フォーマルな席にも似合う、重厚なセダン5.お買い物やチョイ乗りのアシ ・・・ってなラインアップなら実に明快だ。 実は、東京から兵庫に転居した時点では、この理想に近い状態だった。 セダンは真っ赤なアルファロメオ75TSだったからチョイとヤンチャ系だったけど、足りないのは小型ステーションワゴンだけ。 ・・・で、探し始めたのだが、ここに割り込んできたのがポルシェ964だった。 ステーションワゴンとはほど遠いし、よりによってRSR仕様に作り上げた2シーター。 もちろん金額も圧倒的に高かったのだが、つい、買っちまったのである。 その頃、中古で購入後5年強乗ったプレサージュに大きな修理が必要となったので、ホンダのシャトル(もちろん中古)に代替え。 さらに、アルファロメオ75TSとアシに使っていたプレオRMも手放すことになり、ラインアップの再構築をしなくてはならなくなった。 そんなとき、ついうっかりヤフオクで「ポチってしまったの」がボクスターだった。 すでに2台のナンバー付き2シーターがあるだけでなく、2台持っていたレース用のフェアレディSRのうち、ノーマルエンジンクラス用の1台にナンバーを付けるプロジェクトも進行中のできごと。 こうして完成してしまったのが、シャトル+2シーター4台というラインアップだ。 こちらの画像は、2シーターが4台揃っちまった頃のボクの所有車両。 ボクスターの奥は、当時、唯一の普通のクルマとして活躍してくれたシャトル。 そこにミニ1300iが加わったので、少しはまともになったけど、2シーターを主体とする多頭飼いの実用性レベルは、チイとばかり低すぎた。 我ながら、なんともマヌケなクルマ選びをしたものである。 現在は、2台のポルシェを手放し、ナンバーを付けたレース用フェアレディは初期型の240Zに変身している。 2シーターは2台に減って、なんとなく実用性が向上したけど、実はこれも一時的。 そろそろ、現在仕上げ中の2シーターが完成しちゃいそうなので、またまたややこしくなりそうだ。 ■エピソード5:多頭飼いを苦しめる任意保険 クルマを運転する以上、事故の可能性はゼロではない。 だから当然のこととして任意保険に加入し、そのリスクに備えることになる。 でもね、この任意保険のシステムは疑問符のオンパレードだ。 例えば、長年無事故を継続して、任意保険で20等級であるドライバーが、初めて複数所有を敢行し、2台目の任意保険に新規加入するとしよう。 そのとき、2台目の特例として、初年度から1ランクアップで7等級から始まるのだが、ここで最初の疑問符が舞い降りてくる。 運転者が契約者本人限定であれば、2台契約しようが5台契約しようが、保険会社が請け負う事故リスクは1台だけの契約と同じはずだからだ。 過去のデータから、車種や地域によってリスクに差があるにせよ、それは保険の基本料率の話であって、等級に差を付ける正当性が理解できない。 この問題を考えると、2番目の疑問符も浮上してくる。 それは、同一個人が何台契約しようが、運転者が契約者本人限定なら、1回の運転で動く車両は1台だけであり、保険会社が背負うリスクも当然1台分だけ。 でも、それぞれの車両に対し、保険契約をしないとならない。 契約者個人は、例えば5台所有の場合、1回の運転時に背負う事故リスクを5台分負担するということになるし、保険会社は1台分のリスクで5台分の保険料収入を得ることにもなる。 運転者はひとりでも、彼の所有する複数のクルマが動き回るというなら話は別だが、これはユーザーが圧倒的に不利となるやり方ではないだろうか。 もちろん、車両保険に関しては個別契約が必要だが、対人、対物、搭乗者など、基本的な自動車保険契約部分に関しては、車両にかけるのではなく、ドライバーにかけるスタイルにするべきだと感じる。 これは、任意保険だけではなく、自賠責保険に関しても同様で、自動運転車両以外は、車両個々ではなく、ドライバーにかけるべき保険と考える。 車種によるリスク変化をカバーしたいのであれば、ドライバー保険としながら、その個人が所有する車両の申告を義務付け、必要に応じた係数をかければ良い。 また、契約しているドライバーが一時的に他車に乗る場合の短期契約もあるとありがたい。 任意保険のシステムが、もっと自由に多頭飼いができるよう改善されたなら、出会ったクルマをもっと気軽に受け入れられるのになぁ、なんて思う今日この頃。 これって、ボクの単なるワガママかな……? [画像/ボルボ 撮影&ライター/島田和也]

旧車のエンジンがかからない原因は?よくある不具合や対処法についても解説
旧車のエンジンがかからない場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。これまでに旧車のエンジンがかからなかったことがない場合でも、知識として持っておくと万一の際に焦らずに対処できるでしょう。今回は旧車のエンジンがかからない場合の原因や対処法について解説します。旧車を所有している方や購入を検討中の方は参考にしてください。 旧車のエンジンがかからない場合に考えられる原因 旧車のエンジンがかからない場合に考えられる原因はさまざまです。代表的な原因について解説します。 セルモーターの不具合 セルモーターは、エンジンを始動するための重要なパーツです。平均的な寿命は10〜15万km程度で、エンジンの始動やアイドリングストップを過度に繰り返すと寿命が縮まるので注意しましょう。バッテリーが上がっていないのにセルモーターが作動しなければ、セルモーターが原因である可能性が高いといえます。 ヒューズの断線が原因 ヒューズは、電気系統に過度な電流が流れないように断線する仕組みになっています。電装品に限らず、エンジンを始動するためのヒューズが断線しているとエンジンはかかりません。旧車の場合はすぐに手に入らない可能性もあるので、予備のヒューズをストックしておくようにしましょう。 オルタネーターの不具合 オルタネーターとは、発電機の役割を果たしているパーツです。オルタネーターが故障すると、電気が作れずにバッテリーの充電ができなくなります。バッテリーを交換したのにすぐに上がってしまう場合は、オルタネーターが原因の可能性が高いでしょう。平均的な寿命は20〜30万kmのため、中古車であっても走行距離が短ければ関係がないと思うかもしれません。しかし、中古車を購入する時点でオルタネーターが古いものに交換されていることもあるので、購入時にチェックが必要です。 エンジンのかぶり 旧車でもキャブレターを採用しているエンジンは、始動時に「かぶる」という現象が起きることがあります。この「かぶる」という現象は、燃料が必要以上に供給されることでプラグが濡れてしまう状態です。ひどい状態になるとプラグの交換や乾燥が必要となり、エンジンの再始動に大きな労力がかかることになります。電子制御燃料噴射装置式の車でも、アクセルペダルを踏んだままセルモーターを回すと同様のかぶりが起こる可能性があるので注意しましょう。 エンジン自体の故障 エンジンは耐久性の高いパーツです。ただし、オイルの交換や燃焼による減少対策を怠るとエンジンに大きな負荷がかかり故障します。エンジンオイルは潤滑、冷却、密閉、洗浄、防錆という5つの役割を果たしているので、最悪の場合はエンジン自体の交換が必要になるケースもあると考えましょう。 電圧不足が原因 電圧不足でもエンジンがかからない場合があります。いわゆる電圧降下(ドロップ)という現象で、電気を送る線の不具合で電圧が末端になるに従って低くなりエンジントラブルが生じることです。他にもヒューズが錆びていたり、バッテリーやオルタネーターの寿命や不調が原因となることもあるので、定期的な電圧チェックは欠かさないようにしましょう。 社外パーツが原因 旧車のパーツは確保が難しい場合が多く、不具合が生じた際に適応する社外パーツに取り換えられていることがあります。しかし、適合するとはいっても純正や推奨パーツとは異なるものを代替えとしているケースもあり、突然の不具合に見舞われてエンジンがかからなくなることもあるので注意が必要です。 旧車のエンジンがかからない場合の対処法 続いて、旧車のエンジンがかからない場合の対処法について解説します。 セルモーターの不具合 セルモーターに不具合が起きている場合は交換が必要です。新品のセルモーターへ交換すると3~5万円程度の費用がかかります。旧車はすぐにセルモーターを確保できないこともあるので、始動音に違和感を感じたらすぐに業者へ相談するとよいでしょう。 ヒューズの断線 断線したヒューズを自力で元に戻すことは難しいため、通常は交換が必要です。ヒューズの断線に早く気づけるように、サビがないかなどのチェックをこまめに行いましょう。カー用品店などに在庫のない品番もあるので、普段からストックしておき車に積んでおくことをおすすめします。 オルタネーターの不具合 オルタネーターの不具合は交換修理が必要となります。一般的な中古車店で購入した旧車の場合は、純正のオルタネーターかどうかの見分けもつかないので信頼できる専門店で購入する方が安心といえます。交換費用は5~10万円程度かかり、部品がなければ調達できるまでエンジンをかけることはできません。 エンジンのかぶり キャブレター式の場合はチョークの調整に失敗したり、チョークレバーの戻し忘れが原因のことが大半といえます。特に寒い日は始動時にチョーク調整に細心の注意を払う必要があるので、マニュアル通りの始動を心がけるようにしましょう。旧車はマニュアルが備わっていないことも多く、専門店で購入する場合は納車時に説明してもらえるのでしっかりと理解しておく必要があります。 エンジン自体の故障 エンジンの故障については、経年劣化するパーツの定期的な交換や日常的な点検をしっかりと行うことで回避できるケースも多いでしょう。特に重要なのがオイルやラジエターの水が正常に循環するかどうかなので、汚れやレベルゲージ、ラバーホース類の破れがないかなどに注意しましょう。 中古車で購入する場合、専門店でレストアされてエンジンの分解洗浄が行われている車はひとまず安心できるといえるでしょう。しかし、一般的な中古車販売店で現状渡しの車を購入した場合は、旧車に詳しい修理工場で細部まで点検してもらうことをおすすめします。エンジンの交換となると数十万~数百万円の費用負担が発生し、乗せ換え用のエンジンがなければ廃車することになるかもしれません。 電圧不足が原因の場合の対処法 電圧不足でエンジンがかからないケースが旧車では非常に多いといえます。まず、日常的な予防策として過度に電装品を取り付けないようにし、電圧のチェックをこまめに行うようにしましょう。電圧チェックについては市販されているオルタネーターチェッカーやクランプメーター、車内で電圧を確認できるシガーソケット用やバッテリーに直接接続できる電圧計もあるので導入を検討されてみてはいかがでしょうか。 電圧不足によりエンジンがかからない場合の対処法は、原因を究明して必要に応じてパーツ交換することです。リレー回路や配線に問題がある場合は、専門店に修理依頼して交換してもらうようにしましょう。テスターで原因箇所がみつかっても代替パーツを要することもあるので専門家に任せる方が無難といえます。 社外パーツが原因 社外パーツが原因でエンジンがかからない場合も、多くはパーツを交換することで不具合が解消します。ただし、納車後の不要なトラブルや走行時のリスクを考えると、やはり専門店で車を購入してアフターケアをお願いした方がいいでしょう。専門店によっては車に使われている社外パーツの箇所や特性を理解しており、交換用パーツもストックしているケースがあるので万一の際も安心です。 旧車のエンジンがかからなくなる場合は買い換えるべき? 旧車のエンジンがかからなくなった場合でも、比較的簡単な処置で直るケースがあります。重要なのは「エンジンがかからなくなったのか原因を知ること」「どの程度の費用負担が必要なのかを確認すること」「再発しないように直せるのか確認すること」の3つです。 修理費用や維持費の面で買い換えを検討することもあるかと思います。しかし、旧車のエンジンがかからなくなるというのは年式を考えれば当然のことでもあり、原因や解決策を理解した上で総合的に判断するのがいいでしょう。まずは専門店に相談することをおすすめします。

旧車にドリンクホルダーを設置する方法は?設置する際の注意点も解説
ドリンクホルダーは、今や車に標準装備されている便利なツールです。そんなドリンクホルダーは社外パーツとして1980年頃から世に出始め、標準装備されたのは1990年代になってからでした。そんなドリンクホルダーは旧車でも設置できるのでしょうか。今回は旧車にドリンクホルダーを設置する方法と注意点について解説していきます。 旧車にドリンクホルダーを設置する方法 ドリンクホルダーの種類は様々です。エアコンダクトやシフトレバーなどに取り付けるタイプがありますが、旧車には年代によって取付けが困難な車も存在します。具体的な取り付け方法について解説します。 DIYで設置する DIYとは、日曜大工のように自分自身で作ったり修繕することを意味します。ドリンクホルダーは市販のものを流用して、所有している旧車の任意の箇所に取付けすることです。ネオクラシックカーと呼ばれる年代の車であれば、エアコンダクトやダッシュボード上に市販の社外品を設置するのは比較的容易といえるでしょう。 それ以前の年代に生産された旧車は設置箇所に乏しくDIYでの設置が必須となります。観光バス用のドリンクホルダーを内装にビス止めするか、ドアガラスの隙間にステーを差し入れて固定することが多いです。 カスタムショップに依頼する 大切にしている愛車に穴を空けたくないという方は、カスタムショップに依頼すると良いでしょう。世界的に旧車フリークの中では「レストモッド」と呼ばれる手法がトレンド化しています。レストモッドとは「レストア」と「モディファイ」を掛け合わせた造語で、性能や使い勝手が良くなるように現代的な仕様に変えることです。 内装の一部もしくは全部をカスタムして、ドリンクホルダーを追加設置することで内装の刷新と利便性の向上やオリジナリティの付与ができます。レストモッドを手がけるファクトリーも数多く誕生していますので検討してみてはいかがでしょうか。 旧車にドリンクホルダーを設置する際の注意点 続いて、旧車にドリンクホルダーを設置する際の注意点について解説します。 手足の動きの邪魔にならない箇所に設置する 旧車にドリンクホルダーを設置できる箇所はそれほど多くありません。ドアの内側やセンターコンソールボックス横などに設置するのが主流です。ただし、運転中のクラッチやステアリング操作の妨げにならない場所を選ばなければなりません。また、運転中に邪魔にならないよう、仮止めなどを行い手足の動きに支障が出ないようにしましょう。 必要な容量を確保する ドリンクホルダーは、対応する容量によってサイズが異なります。どのサイズのドリンクを入れるかを想定して必要な容量を選びましょう。また、ペットボトルを入れる時は高さも必要なため、内装や手足に干渉したり隙間が足りずに入らないということのないように位置を決めてください。 自家用車に取り付け可能なドリンクホルダーか確認する 自家用車のどの位置に取り付けるかを考えたうえで、対応できるドリンクホルダーであるのか確認しましょう。ダッシュボード上やコンソールボックスに両面テープで貼り付けるのか、穴を空けてビス止めをするかによっても対応するドリンクホルダーは異なります。 ネオクラシックカーなどのエアコンダクトに取付けが可能な車種でも、ルーバーの形状によって対応の可否はあるので注意が必要です。また、車種専用のドリンクホルダーは、対応車種の内装形状に合わせたものとなるのでそれ以外の車には使用できません。

神奈川県で急増した盗難。R32GT-Rや80スープラなど旧車15台が被害
旧車の盗難は相変わらず多いのだが、特に今年6月以降、目立って増えているのが神奈川県だ。 ■2022年6月以降、神奈川県内で盗難被害が急増 自動車盗難情報局(jidoushatounan.com)に登録されたものや、TwitterなどのSNSで盗難が拡散されているものをピックアップしてみた。 ※盗難に関する内容は登録時点での情報です 神奈川県においては2021年の1年間で4台(うち1台は発見)の旧車が盗まれているが、2022年は6月半ばまではゼロ。 しかしその後、急増しており6月16日から9月11日まで報告されているだけで15台(未遂1台含む)!異常な数字である。 スカイラインGT-R(10台)と80スープラ(3台)の盗難が目立っている。 ■2022年6月〜9月にかけて神奈川県内で盗難された国産車 車種やボディカラー、盗まれた日、時間帯、場所、クルマのナンバーや特徴、そしてどのような盗難対策をしていたのか?などをお伝えしておく。 ●6月16日(0時~6時15分) ・車種:平成2年式 スカイラインGT-R NISMO(ガンメタ)・場所:神奈川県 横浜市 綱島駅付近の駐車場(自宅人近い月ぎめ駐車場)・ナンバー:横浜 330 や 2632・盗難対策:ハンドルロックとタイヤロック装着。月極駐車場のフェンスと繋いでいたチェーンロック。車カバー。*車部品の散乱は無し。タイヤロック破壊。車カバーを剥がされていた。右リアから出ている牽引フックに取り付けていたチェーンロックを外されていた。隣接している工場から延長コードを使用して電源を取り、エンジンを始動させたと思われる。 ●6月24日(5時~18時頃) ・車種:BCNR33 スカイラインGT-R(白)・場所:・場所:横須賀市スカイマンション下の駐車場・ナンバー:横浜 302 ひ 8681・盗難対策:ハンドルロックバー使用*マフラーの近くに溶けたあとがあり。HKSのスーパーターボマフラー。ホイールはボルクの17インチのアルミ金色。塗装はクリアが剥げていてまだらになっています ●6月26日(時間は不明) ・車種:日産スカイライン BNR32GT-R(スパークシルバー)・場所:神奈川県 横浜市泉区下飯田付近の駐車場・ナンバー:横浜 33 ら 4219・盗難対策:なし*純正16インチ ボンネット塗装ハゲあり フロントバンパー右ライト下擦り傷あり*ADVAN FREVA装着 GT-Rエンブレムは盗まれて接着部分のみ残っている ●7月17日11時半~18日3時 ・車種:平成9年式 マツダRX-7(ホワイト系)・場所:神奈川県 横浜市戸塚区 契約していた月ぎめ駐車場・ナンバー:横浜 303 る 7005*現場にはガラスの破片などはなし。フロントとサイドにC-WESTのエアロがついており、リアはノーマルでGTウィングがついているRX-7となります。フロントのエアロ右寄りの場所が割れ始めてきております。給油口には「全財産 inside」のステッカーが貼ってあります。 ●8月10日7時10分~17時8分 ・車種:日産スカイライン BNR32 GT-R(ブラック)・場所:神奈川県 藤沢市遠藤 勤務先駐車場 勤務先社屋から2~300M離れた社員専用駐車場内です。お昼頃、不審な車が駐車場から出て行く所が目撃されています。・ナンバー:相模 33 の 6426・盗難対策:対策なし。施錠のみ*エンジンはN1用に換装。外観はニスモ仕様。リアにカーボン製の旧ロゴのニスモマークのエンブレム。HKS関西のロールバー装着。リアウィンドウにカロッェリアのテレビアンテナあり。NISMO(ベルディな)マフラー。オーリンズの車高調サスです。右側のリアホイールアーチ後方下側に錆による穴あり。ドアノブにニスモマークのついた保護パットが付けられています。後輪のみN1用穴無しディスクを装着 ●8月13日20時頃~8月14日9時50分頃 ・車種:日産スカイラインGT-R(ブラック)・場所:神奈川県 海老名市中新田 自宅駐車場・ナンバー:相模 301 た 9420・盗難対策:ハンドルロック使用*R33GT-R純正のホイール、ニスモバンパー、柿本Rのマフラー、ARCのインタークーラー付き。車の部品の散乱はなし。 ●8月16日19時~17日5時頃 ・車種:80スープラ(グレー)・場所:横浜市緑区マンション駐車場機械式上段・ナンバー:横浜 35 に 1360・盗難対策:なし*色はグレー系ですがカタログ記載はグレイッシュグリーンマイカメタリックとなっていますフロントバンパー右わきにかすれ傷あり。運転席側ドアミラーそばに『猫バンバン』のマグネットステッカー貼っています。(ただし経年劣化で真っ白に)新車購入から20年以上乗っています。人生の半分以上はこの車と一緒に過ごしてきました再塗装していないのでボンネットは一部剥げている部分ありますフロントガラス(助手席側)に傷あり。特にカスタムしていないので特徴はノーマル仕様です ●8月16日朝 ・車種:80スープラ(白)・場所:横浜市緑区・ナンバー:横浜331す8320・盗難対策:バイパーセキュリティとラフィックスを付けていたがバイパーは1年前から不調で、ラフィックスもハンドルを外していなかった。 ●9月1日 ・車種:トヨタ スープラ(赤)・場所:川崎市宮前区野川自宅前の月ぎめ駐車場・ナンバー:川崎301 す 7717・盗難対策:タイヤロック前後輪に使用 ●9月3日19時~9月6日16時 ・車種:平成14年式 レガシィB4(青)・場所:神奈川県 厚木市三田・ナンバー:春日井 500 そ 86・盗難対策:なし*アパート前露天駐車場に駐車、数日間運転しなかった間に盗まれました ●9月8日未明から朝 ・車種:日産 スカイラインGT-R(ブラック系)・場所:横浜市金沢区 集合住宅敷地内の駐車場・ナンバー:横浜 33 ぬ 9482・盗難対策:タイヤにチェーンロックを掛けていた ■旧車およびネオクラシックオーナーは早急に「本気で盗まれないための対策」を! わずか3か月弱で未遂1台含む15台が盗難されているが、気になるのは『盗難対策:なし』が目立っていることだ。 またタイヤロックやハンドルロックなどを装備していても、実際はほんの数分で切断される(時間稼ぎにはなると思われるが)。 盗む方が悪いのは当然だが、盗まれやすい旧車のオーナーは、一刻も早く「本気で盗まれないための対策」をする状況にあることは間違いない。 特にスカイラインやスープラ、RX-7など人気の旧車スポーツカーにはお金がかかっても(20-30万円前後)、誤報ゼロのカーセキュリティを装着することをお勧めしたい。 たしかに痛い出費だと思うが、必要経費と割り切り、決断するときだと思う。 取り急ぎ何かやっておきたい、という場合はアップル社のエアタグなどを応急的に取り付けておくのもよいだろう。 神奈川県が急増している理由は・盗難多発の千葉、茨城、埼玉、愛知、三重の5県で導入されている『ヤード条例』が施行されておらず、解体ヤードに関する規制がとても緩い。・これまで旧車盗難がほとんどなく、盗難対策をせず簡単に盗める旧車が豊富 等が考えられる。スカイライン、80スープラのオーナーは特に注意してほしい。 ■9月12日夜に「国産スポーツカー窃盗未遂で男二人逮捕 神奈川県」の報道 [9月12日追記]なお、この原稿を書き終わった後、9月12日夜に「国産スポーツカー窃盗未遂で男二人逮捕 神奈川県」のニュースが流れた。 報道によると暴力団関係者と無職の男2名は6月以降、スープラやスカイラインなど合計20台(被害総額は1億円超)を盗んだとのことである。 自動車窃盗における検挙率は盗難の多い関東地方の場合、平均して3割前後。 旧車はさらに低いが、よく逮捕されたものだ。 [車両写真:自動車盗難情報局(jidoushatounan.com)から引用、画像/Adobe Stock、ライター・自動車生活ジャーナリスト加藤久美子]
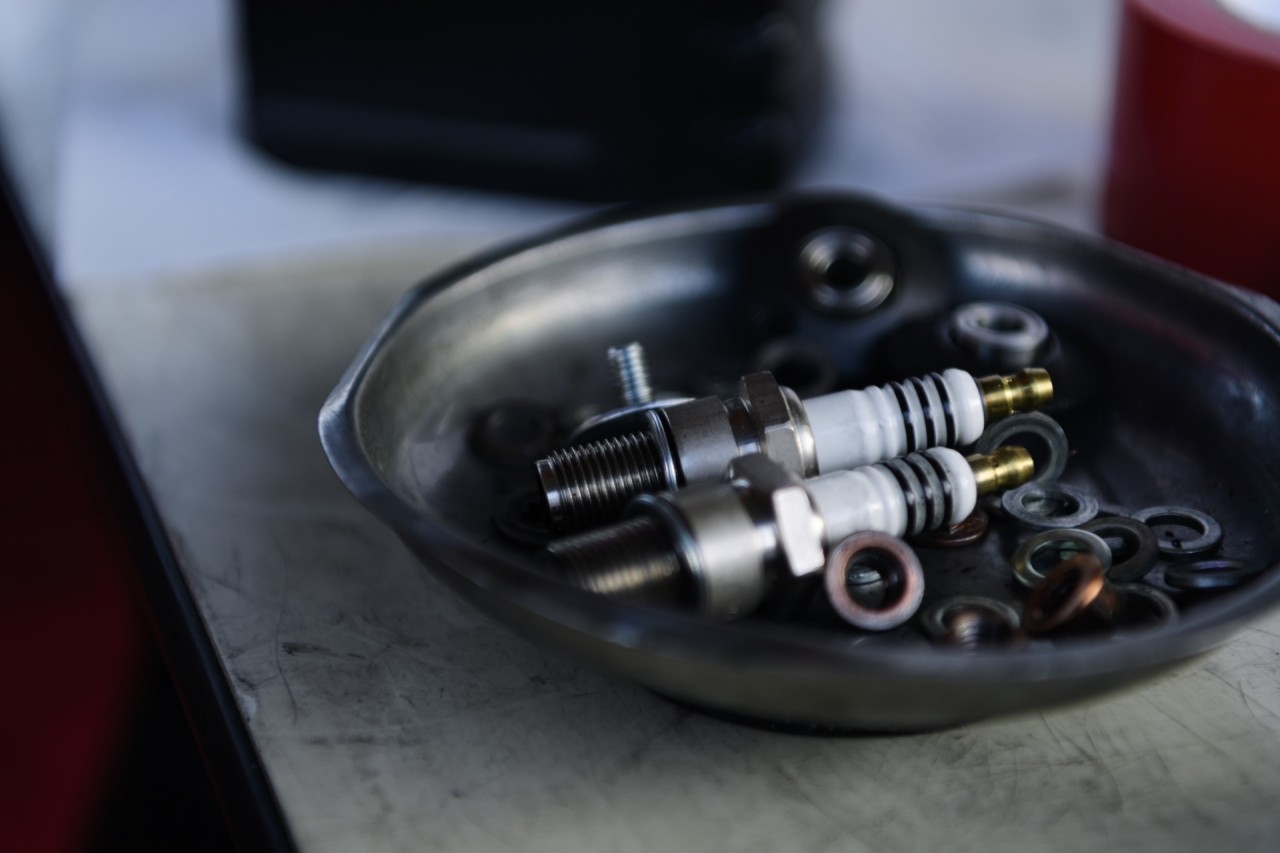
旧車パーツはどうやって入手する?入手困難な理由やそれぞれの特徴を紹介
クルマには交換が必要なパーツがあります。走行によって摩耗したり、樹脂やゴム製のパーツは、熱や紫外線を受けて劣化します。しかし、パーツの供給は生産終了からおよそ10年といわれているため、いずれ新品の入手ができなくなります。 特に“旧車”と呼ばれている古いクルマだと、パーツを入手するのがより難しいといわれています。 そこでこの記事では、旧車のパーツが入手困難な理由とパーツの入手方法について詳しく紹介します。 旧車のパーツが入手困難な理由 1台のクルマには、約3万個のパーツが使われているといわれています。中には他の車種との共用品もあれば、逆に外観が同じ車でも、製造年月日で変更されているパーツもあります。これら全てのパーツを、自動車メーカーや自動車パーツ製造会社が、いつまでも保有し続けることはできません。また、日本には自動車メーカーに保管期間を定める法律はなく、自動車会社ごとに判断されています。 一般的に、クルマの生産終了から10年程度であれば、ほとんどのパーツの入手が可能といわれています。逆に生産終了から10年以上経過すると、自動車メーカーからパーツを入手できなくなることもあります。 “旧車”という言葉に明確な定義はないものの、生産終了から10年以上が経過している車種を指すことが多いです。パーツの生産年数を踏まえて考えると、ほとんどの旧車の新品パーツはすでに入手できない状況にあります。一方で、発売から何十年も経過した旧車だと、さまざまな箇所に故障がみられ、パーツの交換に迫られる場合が少なくありません。そのため、旧車オーナーにとって、パーツの入手方法は維持するための大きな課題の1つだといえます。 旧車パーツの入手方法 自動車メーカーの在庫が無くても、旧車のパーツを入手する方法があります。 ここからは、旧車のパーツを入手する方法とその特徴を紹介します。 ①ネットオークションで競り落とす まずは手っ取り早く、ネットオークションで探してみましょう。オークションは、入札によって価格が競り上がるため、希少価値の高いパーツや人気の高いアフターパーツなどは高額になりがちです。逆に需要が小さければ、格安で入手できる場合もあります。 ネットオークションは、欲しいパーツが出品されているとは限りませんので、定期的にチェックするとよいでしょう。 ②フリマアプリで購入する フリマアプリは、入札によって価格が競り上がる部分を除けば、基本的にネットオークションと同じです。そのため、常に欲しいパーツが見つかる訳ではありません。しかし、フリマ市場は拡大傾向にあるため、パーツ入手の最も有効な手段になるかもしれません。 ③SNSで売り手を探す SNSを活用して欲しいパーツの売り手を探すこともできるでしょう。あなたの情報が売り手に伝わりやすくなるよう、#(ハッシュタグ)に車種、メーカー名や部品名を付けましょう。直接売り手に届かなくとも、同じ車の愛好家があなたの情報を拡散してくれるかもしれません。 ④部品取り車を購入してパーツを取る 部品取りができるクルマを、丸ごと購入する方法です。車種やクルマの状態によっては高額になることもありますが、走行できない状態で長く放置されていたり、下位グレードで価値が低かったりするクルマであれば、比較的安価に入手できることがあります。ただし、購入したクルマの保管場所を確保する必要があるため、他の方法よりもハードルは高いといえるでしょう。 ⑤流用可能なパーツを購入する 車種が違っていても共通して使われているパーツもあります。エンジンやトランスミッションなどは形式が同じであれば、違う車種であっても流用が可能です。旧車パーツを探す際には同一車種に限定せず、共通して使われていそうな車種についても調べてみましょう。 ⑥アフターパーツを使う 純正部品が手に入らなくなってしまってもアフターパーツなら手に入るというケースは多々あります。具体的には、サスペンション、マフラー、フロントフェンダー、カーボンボンネット、シート、ステアリングなどです。旧車をカスタイズするユーザーも多いため、有効な手段といえるでしょう。 【最新アフターパーツ情報】純正形状の外板パーツもある 一部の旧車の純正形状の外板パーツを販売しているアフターパーツメーカーもあります。一般的なアフターパーツと異なり限りなく純正に近い形状のため、旧車オーナーにとっては大変心強い存在でしょう。形状だけではなく、素材も純正と同じスチールを使用していることが多いようです。 ⑧メーカーの復刻パーツを使う 現在、トヨタ、日産、ホンダ、マツダから一部の旧車の復刻パーツが発売されています。車種は限られますが、各メーカーで復刻パーツ生産を今後も推進していくことが予想されます。生産終了した純正パーツを入手できる絶好の機会のため、自分の探しているパーツが対象に含まれているかどうかをこまめにチェックするとよいでしょう。 各メーカーの復刻パーツ情報は下記サイトで確認できます。 トヨタ/GR HERITAGE PARTS日産/NISMO Heritage Partsホンダ/BEATparts ※ビートのみマツダ/CLASSIC MAZDA ※NAロードスター、FC/FD RX-7のみ まとめ 旧車のパーツが入手困難な理由とパーツの入手方法について紹介しました。 旧車のなかでも、発売から半世紀近くが経過する1970〜1980年代の古いクルマは、さまざまな箇所に錆や腐食が発生するため、維持し続けるにはパーツ交換が必須です。 ネットオークションやフリマアプリで手軽に取引できるようになったり、自動車メーカーの復刻パーツがはじまったりするなど、旧車のパーツを入手する方法がどんどん増えています。さまざまな方法を駆使すれば、より長く旧車に乗り続けることができるでしょう。

日本アルミ弁当箱協会会長の「ちょっと斜めから見た旧車たち」Vol.3
■第3回 ~アルミ弁当箱協会のこれから~ どうも!「日本アルミ弁当箱協会」会長のマツド・デラックスでございます。 「旧車王」に連載3回目となりました今回は、「アルミ弁当箱協会のこれから」を熱く語らせていただきます! ■コレクターはアーティストにはなれないと気づく 今年の「ノスタルジック2DAYS」や「アメイジング商店街」そして有楽町マルイでの「のなかみのると仲間たち」に参加させていただき、改めて認識したことがありました。 それは「コレクター」は「アーティスト」にはなれないということです。 人によっては当たり前のことかもしれませんね。 「何を今さら?」と思われても不思議ではないかもしれません。 私はとこかで勘違いをしていたところがあったと思っています。 「他人のやっていないことをやるのだから・・・・的な考え」がそう思わせたのかもしれません。 しかし、本物の「アーティスト」の方たちに囲まれたときに、ちっぽけなプライドがすっ飛びました。 ■コレクターを極めようと決めた日 コレクターを極めるために、ただひたすら「アルミ弁当箱」を集める・・・。 それでは「日本アルミ弁当箱協会」などという団体を作っても意味がないのです。 そこには、旧車の不人気車を愛するような愛情と、「その子たち」をどうやって後世に伝えるかということも使命のひとつだと思っています。 アルミ弁当箱から伝わる世相や歴史観について「アルミ弁当箱コレクターだから発信できること」がたくさんあると思っています。 「日本アルミ弁当箱協会」を通して、斜めからの角度で独特の方法で伝えることが「コレクターの極み」ではないかと再認識しました。 ■昭和の伝道師に俺はなる! 「旧車王」が自動車文化を通して「昭和」を伝えていくよう、これからの「日本アルミ弁当箱協会」はアルミ弁当箱を通し「昭和」の文化や世相を伝えていきたいという想いがあります。 いつの日か「アルミ弁当箱ミュージアム」を作り、これまではスポットライトが当たることなく消えて行くものから新たな力を生み出し、皆さまに少しでもお役に立つような「昭和の伝道師になりうるコレクター」になりたいと思います! ■今回の斜めから見た旧車「パルサーエクサ(1982年)」 さてまたまたやってきましたこのコーナーは、本当に無理矢理アルミ弁当箱からの「斜め」から見た旧車コーナーです。 今回は「パルサーエクサ」です。 ではなぜ今回「パルサーエクサ」なのか? それにはあるアルミ弁当箱が関係しています。そのアルミ弁当箱とは?1977年に放映された「ジャッカー電撃隊」です! こちらに描かれている「スペードマシーン」。 もう旧車王の読者の皆様にはベース車両が何かおわかりでしょう。 そうです!秀逸のデザインで未だに根強い人気を持っている「フィアットX1-9」です。 また個人的な話になってしまいますが、私も「1300」と「1500」の2台所有したことがあります(無類のタルガ好きです)。 特撮車両になっても、ほとんど手を加えることがなかった斬新なデザインがたまりませんでした。 それから5年後「パルサーエクサ」が発売となります。 そのときに私は「ジャパニーズX1-9」といった佇まいにときめき、日産のディーラーにカタログをもらいに行ったことを覚えております。 ジャッカー電撃隊のスペードマシーンから「パルサーエクサ」を紹介するという暴挙と妄想をお許しください。 それほどこの「エクサ」は当時の日本車としてはぶっ飛んだ1台だったので、アルミ弁当箱とコラボさせて頂きました! こんな感じで「ゆる~く」また旧車を紹介していきますのでよろしくお願いいたします。 そしてここでお知らせを・・・・・。 私のコレクター本「アルミ弁当箱図鑑 マニアック編」が9月1日からアマゾンにて予約開始となりました。発売は9月17日です。 オールカラーの100ページに様々なジャンルのアルミ弁当箱を詰め込んでおります。是非、読んで頂ければありがたいです!よろしくお願いいたします。 ◎アルミ弁当箱図鑑 厳選50 ーマニア編ー マツドデラックスコレクション (ヴァンタス) 単行本 – 2022/9/17https://www.amazon.co.jp/dp/4907061471/ [撮影/ライター・マツド・デラックス(山本圭亮)]

失敗しない旧車選びはショップ選びにあり!状態のいい旧車を見つける方法
価格の高騰もあり、いま旧車に注目が集まっています。しかし、あまり知識のないかたが、経年劣化のすすんだ旧車を、他の中古車と同じ感覚で購入するのは危険です。今回は、旧車購入の要となる信頼のおけるショップの見つけ方から、状態のいい旧車の見極め方まで詳しくご紹介します。 妥協はNG!ショップ選びが初めの一歩 どれだけ万全に整備されていても、発売から数十年が経過する旧車にはトラブルがつきものです。目に見える場所の劣化だけでなく、エンジン内部やメーターなどの電気系までトラブルの原因となる箇所は多岐に渡ります。 購入時の整備はもちろん、購入後のアフターサービスまで信頼のおけるショップを選ぶことが、長く乗れる旧車を手に入れる重要なポイントです。 ショップの経験と整備体制を事前に確認 旧車を購入する際は、購入先となる中古車ショップの経験や整備体制を事前に確認しておきましょう。とくに旧車に対する知識や経験は重要で、購入時に問題がなくても、乗り始めたらすぐに故障することもありえます。 ただし、購入する側は素人なのでショップの実力を判断するのは至難の業。最低限、誠実で信頼のおけるショップを選びましょう。数十年前のクルマなのに、とくにマイナスポイントを挙げることなく「すべて問題ありません」と言い切ってしまうショップは避けたほうが無難です。 また、整備に必要な部品の供給体制も事前に確認しておきたいポイント。旧車の部品はすでに絶版となっていることもあるので、現状の在庫保有や供給体制について話しておくことも大切です。 ショップの扱っている中古車ラインナップから判断 信頼のおけるショップかどうかは、営業年数と取り扱っている中古車ラインナップである程度判断できます。営業年数がそれなりにあり、購入予定の中古車と同年代のクルマを多く取り扱っているショップがベストです。 また、ファンの多い旧車であればその車種を専門に扱っているショップもあります。そのようなショップは、取り扱い台数が多く、当然のことながら経験が豊富です。加えて、特定車種に特化したショップであれば、整備用の部品も多く確保していることも多いので、アフターフォローにも期待できます。 旧車だからこそ可能な限り細かくチェックする 中古車、しかも旧車となると各部が新車同様に万全の状態ということはまずありません。しかし、しっかりと整備されていて良好な状態を保っているクルマであれば長く乗り続けることができます。旧車購入前には、エンジンや足回りなど可能な限り細かくチェックし、正確に状態を把握することが大切です。 必ず購入前にエンジンを始動する 旧車を購入する際は、必ず事前にエンジンをかけて状態を確認しましょう。エンジンはごまかしがきかないパーツのひとつで、クルマの状態を判断する大きな材料になります。 まずは、始動性。スムーズに始動するか、可能ならエンジンがかかった後1度切って再度確認しましょう。状態が良ければ何度始動してもスムーズに始動します。次に確認するのがアイドリングの状態です。旧車のエンジンは、暖気が完了しないと安定しないものもあるのである程度時間をかけて確認しましょう。 最後に確認するのが吹け上がりと異音です。軽くアクセルを吹かしてスムーズに吹け上がるか、異音はないかを確認します。また、マフラーからの排気も同時に確認しましょう。白煙や黒煙があがっている場合は、納得いくまで説明を求めましょう。 万が一エンジンがかけられない場合は理由を説明してもらい、納得がいかなければ避けた方が無難です。どちらにしても、購入前までにはエンジンの動作確認を必ずおこないましょう。 試乗をさせてもらえればベスト 購入を最終決定する前に、可能なら試乗をすることをおすすめします。シフトの入り具合、足回りのガタつき、ステアリングラックの不具合などは試乗をしないとわかりません。 とくに長い間動かしていなかったクルマの場合は、動かすことで不具合が出てくることもあります。試乗をする際は、段差を乗り越えた際の音やボディのきしみ、ステアリングを切った際の抵抗感など神経を研ぎ澄ませて細かくチェックすることが大切です。 「古いクルマなのでこんなものです」と言われても、気になる部分は納得いくまで説明をしてもらいましょう。また、できるだけ多く試乗をすればクルマの違和感に気がつきやすくなります。 部位によっては修復不可!?内外装のチェックポイント どれだけ高い技術力をもったショップでも、修復が難しいのがボディの腐食と内装パーツの経年劣化です。場所や程度によっては、修復費用が高額になるばかりか、そもそも修復不能な場合もあるのでしっかりと目視で確認しておきましょう。 腐食箇所をくまなくチェック 旧車を購入する際にもっとも懸念されるのが、ボディやシャシーの腐食です。ボディの外観だけではなく、エンジンルームの細部や車内、トランクルームのカーペットの下など可能な限り目視で確認しましょう。 万が一大幅な腐食の修復箇所を見つけた場合は、他の箇所にも腐食がある場合もあるので、経緯や修復方法などを細かく販売店に確認しましょう。 内装はオリジナル部品がないこともある 内装を見る際に、最低限確認しておきたいのがメーターパネルや各種スイッチです。とくにメーターや各種警告灯の動作はしっかりと確認しておかないと車検に通りません。車種によっては、すでに交換部品を製造していない場合もあるので修復が困難な場合もあります。 また、そのほかの内装は走行性能に直接影響がないので軽視されがちですが、旧車を購入する場合は注意が必要です。内装に使われているプラスチックや布は経年劣化しやすいので、ちょっとした塗装のはがれやシートの破れでも、使いはじめると劣化が一気にすすむこともあります。 少しでも気になる部分は、修復の可否や金額を購入前に必ず確認しておきましょう。 まとめ いかに精巧で頑丈に作られていても、クルマが工業製品である以上経年劣化には抗えません。しかし、劣化していることを前提に万全な整備をすることで、旧車でも安心して乗ることはできます。 アクセルを踏み込んだときの吹け上がりや心地よい振動やキビキビとしたハンドリング、個性的なボディスタイル。多くの旧車はクルマ本来の魅力を追求した設計思想のものが多く、現代のクルマにはない魅力あふれる車種がたくさんあります。 ぜひ信頼のおけるショップを見つけて、旧車ライフを楽しんでください。

旧車を遺すべく、現状の問題や課題を中心にお伝えします!:小村英樹
■名前:小村英樹(オムラヒデキ) ■職業/肩書き フェアレディZ Z32専門店 代表取締役 Z32一筋で二十数年になります。これからも他車種はやりません。実は、前職はコンピュータープログラマー/システムエンジニアでした。 ■現在の愛車 フェアレディZ32 最終型ZX・2by2・TバールーフZ32を5台乗り継いできた生粋のZ32好きです。 ■ご自身の性格をひと言で表現すると? 自分で言うのもなんですが、真面目で几帳面タイプです。人見知りで、営業マンタイプはありません。 ■好きなクルマは? 基本的にスポーツカーが好きですが、やっぱりフェアレディZ32が一番です。今でも世界に通用する究極のスポーツカーだと思っています。 ■憧れのクルマは? もっと綺麗で程度の良いフェアレディZ32最終型です(笑)。やはり、これに勝るクルマはありません。 ■旧車ヒストリアでどんな記事を書いてみたいですか? 旧車ブームの裏に潜んでいる問題や課題をお伝えできればと思っています。 この10年間で今の旧車達が遺るか危惧しています。今のままではダメです。 旧車オーナー様・オーナー予備軍の方に、ぜひ読んで頂きたいです。 ■その他なんでも・・・ 趣味は仕事で、年中無休で働いていますが、最近は写真撮影にハマっています。Instagramのフォロワー様1万人を目指し、毎日Z32の写真をアップしています。ストーリーには自然や景色など、季節を感じる写真をアップしています。音楽を聴きながらドライブしている時が、至福の時間です。 ■HP/SNS/YouTube等 ・ホームページhttp://www.Z32-Zone.com/ ・Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Fairlady-Z32-Proshop-Zone/286263454768481 ・Instagramhttps://www.instagram.com/Z32_Zone.omura/ ・YouTubehttps://www.youtube.com/user/ZoneZ32 [ライター・撮影/小村英樹(Zone代表)]
