「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
「旧車」の検索結果

ニュージーランドは旧車にも優しい!驚きの自動車税と車検制度とは
オークランド在住のtomatoです。 以前お伝えした通り、公共交通機関が貧弱なニュージーランドではクルマの保有率はほぼ1人1台と高く、スマートフォンと同様にクルマは生活必需品といっても過言ではありません。 ●懐かしい日本車と再会できる国「ニュージーランド」現地レポート https://www.qsha-oh.com/historia/article/tomato-new-zealand-report1/ では、ニュージーランドでクルマを所有する際は、一体どんな車検や税金制度があり、どれくらいの費用が掛かるのでしょうか。 筆者の愛車「マツダ・ロードスター(ND型)」が2023年9月にちょうど更新タイミングを迎えたので、この機会にレポートします。 果たすべき義務は2つ ニュージーランドの公道を走行するためには、下記の2つの認可を取得または更新する必要があります。 ・ヴィークル ライセンス (Vehicle Licence) https://www.nzta.govt.nz/vehicles/licensing-rego/ ・ウォレント オブ フィットネス(Warrant Of Fitness) https://www.nzta.govt.nz/vehicles/warrants-and-certificates/warrant-of-fitness/ Vehicle Licence (Rego) これは公道の走行許可で、一般的には「Rego」(Registrationの短縮形で、「リジョー」と発音 )と呼ばれています。 とはいうものの、結局のところは税金を徴収する仕組みと考えられ、日本の「自動車税」に相当するかと思います。 オンライン(または窓口)で費用を支払うことで、上記のような小型のレーベル(カード)が郵送されてきます。 それをフロントガラスの助手席側に掲示することで、プロセスは完了です。 日付形式は日本式やアメリカ式などとは異なる馴染みの薄いイギリス式で、この実例は2024年5月9日ではなく9月5日まで有効という意味になります。 ちなみに、このレーベルを見るだけで年式や車種などの基本的な車輌情報が得られるので、クルマのミーティングなどで会話のキッカケに非常に重宝しています。 そして気になるその費用はというと、筆者のロードスターはもっとも一般的な「ぺトロール(ガソリン)乗用車」カテゴリーに属していることから、最長となる12か月分の費用は(事務手数料が安価なオンライン申請で)$103.68でした。 なお、2023年10月からは価格改定により$106.15と若干の値上がりとなって、11月執筆現在の為替レート(89円/ニュージーランドドル)で換算するとおよそ9,400円。 ここで「あれ?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 そうです。驚くことに「車輌重量」や「エンジン排気量」などは、金額にまったく影響しないのです。 さらに驚くことに、ニュージーランドには日本の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に相当するものも存在しないのです。 といっても、不安になる必要はありません。その代わりとしてACC(Accident Compensation Corporation)という仕組みがあり、なんとニュージーランドへの渡航者も含めて、自動車事故に限らずさまざまな事故での損害を補償してくれます。 したがって、この国では自動車保険といえば、「対人/対物保険」ではなく「対物保険」となります。 ただし、付保すること自体は義務ではないので、ここでは割愛します。 Warrant Of Fitness (WoF) これは日本でいう車検(自動車検査登録制度)にあたり、一般的には「WoF」と省略して表現することが多く、犬の鳴き声のように「ウォフ」と呼ばれています。 認可されている整備会社ごとに料金が異なるので一律ではありませんが、一般的には$50~$75(日本円で4,400~6,700円)ほど。 検査に合格すると、上記のような、小型のレーベル(カード)をフロントガラスに貼りつけてWoFが完了となります。 この実例では、2024年9月まで有効という意味。 ただし、これは月末まで有効という意味ではなく、裏面にある日付が実際の有効期限になるので注意が必要です。 興味深いことにWoFは日本の車検とは少し方針が異なり、車輌の根本的な安全性のチェックが主体となっているようです。 例えば、エンジンオイルの交換はおろか、その状態を確認することもないのが特徴です。 <検査項目>・タイヤの状態(溝の深さ含む)・ブレーキの動作・車体の構造点検(特定の場所のサビは許されない)・ライト・ガラスの安全性・ワイパー、ウォッシャー・ドアの動作・シートベルト(痛んでいないか。正しく、バックルが動作するか)・エアバック・スピードメーター・ステアリング、サスペンション・排気システム(漏れていないか、うるさくないか)・燃料システム(漏れてないか) (ニュージーランドで初めて登録される)新車に関しては、初回のWoFを受ければ、3年間有効となります。 それ以外の車輌に関しては、大量の中古車を輸入するユニークな国だけに、有効となる期間はニュージーランドを含めた世界のいずれかの国で、「車輌が初めて登録された年月日」で決まる仕組み(下表)です。 要は新車でなければ一般的には1年間有効。 ただし、古いクルマは、「リスクが高いのだから、有効期間は6ヵ月だけですよ」となっているのです。 これは走行安全の観点からも理にかなっていると思えます。 なお、WoFで不合格となっても、28日以内に対象箇所を直し、同じ整備工場に持って行けば、ありがたいことに再検査の費用はかかりません。 まるで軽自動車並みのコスパ? 驚くことに、一般的な「ガソリン乗用車」であれば、義務はこれだけ! 仮に筆者の愛車が旧車、1990年式の初代ロードスター(NA型)であったとしましょう。 その場合WoFは年に2回更新する必要がありますが、それでもRegoとWoF合わせた年間総額は、(消耗品を除いて)2.5万円程度で済んでしまう計算です。 調べたところ日本国内でクルマを維持する場合、地方の「生活の足」として優遇されている軽自動車ですら自動車税と車検代(年換算)の合計は4.5万円程度となるようですから、ニュージーランドはクルマ好き/旧車好きにとても優しい国といえるのではないでしょうか。 今でもたくさんの懐かしいクルマ達が現役で走っているのにもうなずけますね。 編集後記 今回の更新を迎えるにあたり、ここオークランドにて輸入中古車を扱われている「マツダ・ホームグロウン」さんに、エンジンオイル交換といった車輌整備からWoFまでのフルソリューションを行なっていただきました。 実は同社を運営するのは日本国内の正規マツダディーラー「広島マツダ」さん。 実際に作業を担当するメカニックはマツダ車を熟知しているだけでなく日本人なのです。 ただし、WoFに関しては同社は認可を保有していないため、オークランドで20年以上にも渡り自動車整備工場を営んでいる同じく日系の「クリア・モータース」さんがWoF検査作業のみ請け負う形態となっていました。 なお、「クリア・モータース」さんには、今回の記事内容の監修をしていただきました。 この場をお借りして、お礼を申し上げます。 ありがとうございました。 取材協力 「マツダ・ホームグロウン」さんhttps://www.maho.co.nz/ 「クリア・モータース」さんhttps://clearmotors.co.nz/ [撮影・ライター / tomato 監修 / クリア・モータースさん]

旧車ユーザーは三重苦に悩まされる?! 苦労を減らすためのポイントも解説
「人とは違う車に乗れる」「現在の車にはないスタイリング」など多くの魅力が詰まった旧車。しかし、旧車を保有するには、現行車にはない特有の苦労もあります。旧車に乗る際は、魅力だけではなくリスクも十分検討することが重要です。 そこで、オーナーを悩ませる旧車所有の苦労を紹介します。少しでも苦労をなくすためのポイントも紹介しているため、これから旧車を購入予定の方はぜひ参考にしてみてください。 旧車乗りが必ず直面する三重苦 旧車オーナーが直面する問題は、税金を含めた維持費用の高騰です。一方で、そもそもパーツが入手できないという、お金では解決できない問題もあります。 まずは旧車の所有により直面する、3つの問題点を詳しくみていきましょう。 税金が高い 旧車に乗るうえでオーナーの直接的な負担になるのが、毎年かかる自動車税と車検ごとの自動車重量税です。自動車税は、新車登録から13年が経過すると15%程度(ガソリン車の場合)上昇します。自動車重量税に関しては13年経過のあと、さらに18年経過でも加算されるため注意が必要です。 また、明確に旧車に乗ろうと思っていない方でも、13年経過時点での重課は車の購入時に意識しておく必要があります。日本の自動車の平均保有期間は7年というデータもあり、購入時点で6年が経過していれば、普通に車を保有しているだけでも13年に達してしまうためです。 故障リスクが高い 旧車最大の問題は、故障リスクが高い点です。自動車の実際の耐用年数は一概にはいえないものの、目安として法定耐用年数を参考にすると、普通車でも6年とされています。新車登録から10年どころか20年以上が経過する旧車であれば、ゴムや革製パーツの劣化、ポンプやコンプレッサーといった稼動部の故障リスクは避けられません。 旧車に乗る際は日常的に小まめなメンテナンスを行い、故障箇所をできるだけ早く見つけることが重要です。また、一ヶ所を修理すると他の部品に負荷がかかり、連鎖的に故障するケースも少なくありません。旧車を所有する場合は、小さな違和感にも常に気を配るようにしましょう。 パーツが入手しにくくなる 旧車が故障した場合、パーツが入手しにくい点にも気をつけましょう。税金の高くなる13〜18年程度であれば、国産メーカーなら入手可能です。しかし、ゴルフ 5を始めとした欧州車などでは部品の廃盤も始まっている車種もあります。 ただし、国産メーカーでも生産終了から10年を目安としているほか、ディーラーオプションなどは車輌の生産終了とともにパーツの生産も打ち切られるケースもあるため注意が必要です。 故障の発生しやすくなる旧車だけに、パーツの入手性は事前に確認しておきましょう。 旧車に乗るなら特に注意したいポイント 旧車を保有する以上、三重苦を完全になくすことはできません。しかし、いくつかのポイントに注意すれば、苦労を軽減できます。せっかく入手した旧車をできるだけ長く維持するために、ぜひ参考にしてください。 旧車を維持するうえで気をつけたいポイントを3つ紹介します。 夏や冬といった温度変化の激しい季節 旧車で故障が発生しやすいのは、真夏や真冬といった温度変化の激しい季節です。特に真夏は、温暖化の進行によって新車販売時には想定していなかった気温になる日も少なくありません。 具体的に注意したいポイントは、温度変化に弱いゴムや革製のパーツの劣化です。例えば、2008年式のプジョー308SWでは、酷暑の影響でシフトノブが突然ポロポロと崩れ落ちたといった事例もあります。 また、ボディ塗装の劣化も、旧車を保有していると避けられない問題です。塗装は紫外線の影響で、時間経過とともに徐々に劣化していきます。特に夏場は紫外線が強いうえ、雨上がりの水滴がレンズの役目をして、太陽光線がボディを焼いてしまうこともあるようです。屋根付きのガレージや車全体を覆うカバー、日除けの装備など、できるだけ温度変化を抑えられる工夫をして保管しましょう。 さらに、酷暑による影響は劣化しやすいパーツだけではありません。エンジンの冷却系やエアコンのコンプレッサーなど、熱を逃がすための機器類に過剰に負荷がかかる恐れもあります。特にエアコンは、夏を迎える前に点検とメンテナンスを実施し、突然の故障に見舞われないよう注意しましょう。 比較的新しくても油断しない 旧車というと、極端に古いクルマをイメージしがちです。しかし、FD2型シビックタイプR 、Z33型フェアレディZ 、GRB型やGVB型インプレッサWRX STI、NC型ロードスター、ポルシェ911(Type99)など、現代的なイメージの強いクルマも製造から10年以上経過する旧車の域に入っています。 今は目立った劣化がなくても、ちょっとしたきっかけで故障に発展する恐れもあるため注意が必要です。日常的に点検をすることで、大きな故障への発展を防げる場合もあります。できるだけ軽微なうちに故障箇所に対応して、愛車をより長く健全な状態を保ちましょう。 重要なパーツは予備を保有しておく 旧車を保有する場合は、重要パーツの予備を準備しておくことをおすすめします。生産終了から一定の年数が経過するとパーツの生産が打ち切られるケースもあるほか、仮に生産されていても供給自体が絞られる可能性が高いためです。 例えば、1996年式のトヨタ AE111型カローラレビンのリアハブベアリングは、メーカーによる供給は続いているものの受注生産のため納品まで数ヶ月かかります。万が一故障した場合は、数ヶ月間クルマを動かせません。 旧車には「持病」と呼ばれる、特有の故障しやすい箇所が判明している車種もあります。修理する可能性の高い部品は、入手可能なタイミングで予備を用意しておきましょう。 三重苦があってもやはり旧車は魅力的 現代では考えられないスタイリングや設計思想など、旧車には多くの魅力があります。避けられない三重苦があってもなお旧車は人気を集める存在です。また、しっかりとメンテナンスされた旧車であれば、車種によっては資産としての価値も生まれます。 一方で、旧車の売買をする際は、一般的な中古車業者での取引はおすすめしません。購入時は当然、専門業者によるメンテナンスや車輌状態の説明が必要不可欠です。一方、売却時には、やむを得ない経年劣化も含めて、正しく査定してもらうことが重要になります。一般的な中古車店では、古いというだけで減額されるかもしれません。三重苦に耐えて維持してきた旧車なだけに、売却の際は正確な査定をしてもらえる専門業者に相談してください。

旧車にガラスコーティングしても問題ないのか?メリット・デメリットを解説
買った当初はピカピカで綺麗だった車も、年月が経つと色褪せたり、輝きを失ったり、塗装が剥げて、古く見えてしまいます。年月が経過した車を再び綺麗な状態に戻すためには「コーティング」が効果的です。しかしコーティングといってもさまざまな種類があり、どれを選べばいいのか迷う方もいるでしょう。 ボディの保護という面でも、見た目の美しさという面でも、特におすすめしたいのはガラスコーティングです。 そこで今回は、旧車にガラスコーティングをしても問題ないのかという点について詳しく解説します。あわせて、ガラスコーティングのメリットとデメリット、市販のコーティング剤の効果と注意点について紹介します。 車にガラスコーティングをしても問題ないのか? 一般的に、旧車にガラスコーティングをしても問題はありません。見た目を美しくしたり、傷や汚れなどから車本体を保護する目的で、ガラスコーティングはおすすめです。 実際に使用する前に、まずはガラスコーティングのメリットとデメリットについて詳しく確認しておきましょう。 ガラスコーティングのメリット ガラスコーティングをするメリットとしては、次の点が挙げられます。 ・傷や汚れから車体を保護できる・汚れがついても落としやすくなる・色あせや傷みを防げる・見た目が美しくなる・他のコーティングよりも効果が長く続く 車体にガラスコーティングをすると、見た目がピカピカになって美しくなるだけでなく、ホコリや小石、紫外線などから車体や塗装面を守り、長期間にわたって綺麗な状態を保てます。また、汚れがつきにくくなるため洗車時間も短縮できるでしょう。 車のコーティングには、ガラス系の他に、油脂や樹脂などを用いたものもありますが、ガラスコーティングが最も耐久期間が長いといわれています。ガラスコーティングの持続期間は、およそ3~5年程度です。ただし、車の保管場所の環境や使用状況によって、コーティングの持続期間は変わるため、おおよその目安として考えておくとよいでしょう。 ガラスコーティングのデメリット ガラスコーティングは自分で施工するのが難しいタイプもあり、専門店に持ち込んで施工を依頼しなければならない場合があります。そのため、一時的に車が使えない期間が発生したり、費用が高いことがデメリットです。専門店などに依頼した時の相場は、業者やガラスコーティングの種類によって異なりますが、およそ5~8万円程度が目安といわれています。 また、ガラスコーティングは比較的効果が長続きしますが、定期的なメンテナンスが必要です。コーティングのメンテナンスにも費用がかかることも合わせて覚えておきましょう。 施工費用を抑えたいなら市販のコーティング剤も検討しよう 専門店やネット通販などでは、自分で施工できるガラスコーティング剤が販売されています。コーティング剤の価格は、数千円程度であるため、専門店に依頼するより費用を抑えられるでしょう。また、スプレータイプのものなら、吹き付けて専用クロスで拭くだけなため、自分で簡単に施工できます。 自分でコーティングを施工する場合は、コーティング剤を吹き付ける前にボディの汚れをしっかり落としておく必要があります。ボディに汚れが残っていると、コーティングの効果が長続きせず、見た目も美しくありません。 市販のコーティング剤の耐久期間は、専門店で施工してもらうコーティングに比べて短めです。コーティングの持続期間は、コーティングの種類や車の保管環境などによって異なりますが、およそ数ヶ月~1年ほどといわれています。 コーティングの費用を抑えたい方は、市販のコーティング剤も検討してみるとよいでしょう。

見た目より中身を優先!? こんな人に旧車を乗ってほしい!
私自身、Z32専門店を営む店主ですが、いつの間にか疑いようのない「旧車」であることを日々実感しています。 年々、個体数が減っていく現状を目の当たりにし、絶滅の危機に直面している日を案ずる日々です。 これから先「一台でも多くZ32を後世に遺すためには?」を、皆さんと一緒に真剣に考えなければなりません。 いきついた答えは、その一台を大事に守ってくれるオーナー様が必要だということです。 「こんな人に乗ってほしい!」という要望をまとめてみました。 これから旧車に乗りたい方へのメッセージでもあります。 愛車を守り、一生乗り続ける覚悟がある人 オーナー様が、愛車を守り、一生乗り続ける覚悟が必要です。 そのクルマは縁あって出会ったわけですが、貴方のお陰で幸せなはずです。 一蓮托生の思いがあれば、貴方の気持ちに愛車が応えてくれます。 維持費がかかることを理解している人 愛車を維持していくために、お金がかかることに対する理解が必要です。 自動車税・ガソリン代・車検代はもちろん、修理やメンテナンス代も確実にかかります。 お金を惜しみなくかけてあげれば、愛車も喜んでくれます。 見た目より中身を優先し、メンテナンスしながら乗る人 見た目より中身(機関系)を優先し、メンテナンスしながら乗ることが必要です。 いくら見た目を良くしても、調子が悪ければ、安心して楽しく乗れません。 しっかりメンテナンスしてあげれば、愛車がいつまでも活き活きと長生きしてくれます。 改造メインではなく、ノーマル重視で乗る人 改造メインではなく、ノーマル重視で乗ることが必要です。 改造してクルマが良くなることはありません。 やはりノーマルが一番格好良いのです。 ノーマルで綺麗に乗ってあげれば、愛車も喜んでくれます。 万が一の場合、中途半端な状態で手放さない人 万が一の場合、中途半端な状態で手放さないことが必要です。 中途半端な状態の車からは愛着が感じられず、次の方へ受け継ぐのが難しいのです。 次の方も大事に乗ってくれれば、愛車も安心するはずです。 オーナー自身が健康な人 愛車を守るためには、オーナー自身が健康であることが必要です。 病気がちでは、愛車に手をかけることも、乗ってあげることもできません。 オーナー自身も健康であり続ければ、愛車を一生守ることができます。 まとめ 旧車に乗るのは、ペットを飼うのと同じです。 ただ可愛いだけでペットを飼うのはダメですよね? 住みやすい場を提供し、毎日栄養のある良い物を食べさせ、定期的に健診・散歩・シャンプーをします。 日々、健康管理をし、清潔にして、安らげる環境を見直す必要があります。 気が抜けません。 時間とお金を惜しみなく使い、愛を与え続けます。 それが可愛がるということです。 そうすることで、ペットも、この人が飼い主で良かった、この人のお蔭で幸せだと感じるはずです。 それができない人は、ペットを飼ってはいけません。 ペットが不幸になるからです。 飼い主は、ペットのためにモチベーションを維持し、健康で、一生添い遂げることができる覚悟が必要なのです。 [ライター・画像 / 小村英樹]

日本アルミ弁当箱協会会長の「ちょっと斜めから見た旧車たち」Vol.14
旧車王をご覧の皆様! いつもこの「邪道」なコラムをお読みいただき、ありがとうございます。 今回は幻(?)の旧車について、アルミ弁当箱を通してお話をさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 第14回 ~今回の斜めから見た旧車~ 今回の話は前回ほどいい加減な話ではありません(気になる方は前回の私のコラムを)。 日本アルミ弁当箱協会会長の「ちょっと斜めから見た旧車たち」Vol.13https://www.qsha-oh.com/historia/article/matsudo-vol13/ 「ここに描かれているクルマは何なのか?第二弾!」なんです。 ただこちらはなんとなく正体がわかっているような気もするのですが・・・。 アルミ弁当箱の世界ではよくある話で、「わざとぼやけて描くことは少なくないこと」とお話させていただきました。 もちろん大人の事情でございます。 しかし、アルミ弁当箱に描く方も、あちらこちらに「ヒント」を残しています。 そのヒントを見つけ、自分たちで「解釈」していくのがアルミ弁当箱の楽しみの1つであります。 これは実存したくるまなのか? アルミ弁当箱の写真をよく見ていただきたい。 一見するとこの図柄のクルマはいい加減に描かれ、ベース車輌がないようにも思えます。 実際私も勝手にそう思っていました。 しかし、この図柄には大きなヒントとなるものが描かれているのです。 そのひとつが、ドライバーが子供であるということです。 そしてもう一つのヒントは、何気に描かれている「標識」です。 この2つが今回の「クルマ」の正体に迫る大きなヒントになるのです。 ■昭和の子供達なら実は運転したことのあるクルマ? まず運転しているのが小さな子供ということが気になりました。 私は当初、マツダの「R360」を可愛くオープンカーにしてイラストにしたのかと勝手に思っていたのですが、どうも「子供」に意味があると考えると、「コニー」の「グッピー」をベースとして昭和40年頃に神奈川県の「こどもの国」で活躍していた、「ダットサン・ベイビー」を思い出しました。 当然、子供たちが運転する「ゴーカート」のようなクルマでしたが、あえてその姿を描いた貴重なアルミ弁当箱なのでは?(実際のゴムのバンパーは描かれてないが・・・)、と考えたのです。 そこでもうひとつの気になること「標識」です。 この頃は「交通戦争」時代。 子供達に交通ルールを覚えてもらうためのひとつとしても、「こどもの国」で啓蒙活動をすべくこのクルマが活躍していてもおかしくありません。 ですからあえて「止まれ」の標識を一緒に描いたのではないでしょうか? ということで、この赤いお弁当箱の可愛い謎のくるまは「ダットサン・ベイビー」ではないか、という見解となりました! まだまだアルミ弁当箱に描かれているクルマは謎が多いのですよ! それではまた次回をお楽しみに! ■お知らせ そしてここでお知らせを・・・・・。 私のコレクター本「アルミ弁当箱図鑑 マニアック編」がアマゾンにて絶賛発売中です。オールカラーの100ページに様々なジャンルのアルミ弁当箱を詰め込んでおります。是非、読んで頂ければありがたいです!よろしくお願いいたします。 ●アルミ弁当箱図鑑 厳選50 ーマニア編ー マツドデラックスコレクション(ヴァンタス)https://www.amazon.co.jp/dp/4907061471 そしてなんと!この私に映画出演のオファーがありました!「路恋人」監督の「ぜんぶ朝のせいだ!」にちょこっと出演させていただきます。9/24には「アメイジング 映画部2」にも出店予定でトークショーも?!詳細が決まりましたらまたご報告させてください! ●映画『ぜんぶ朝のせいだ』オフィシャルTwitterhttps://twitter.com/morningall2023 ●映画『ぜんぶ朝のせいだ』特報https://www.youtube.com/watch?v=vg0LHPEM6Ss 10月1日には久々の関西遠征!大阪ロフトプラスワンウエストにて「ファンタスティックヴィレッジ」でトークショーをさせていただきます。12時から16時で開催いたします!お近くの方は是非!前売り券、絶賛発売中です! ●『第4回ファンタスティック・ヴィレッジ』 – LOFT PROJECT SCHEDULEhttps://www.loft-prj.co.jp/schedule/west/260209 [画像 / Dreamstime 撮影/ライター マツド・デラックス(山本圭亮)]

教えて旧車オーナーさん!今"N15 パルサー VZ-R"を買ったワケ
2023年現在、100年に一度の転換期といわれている。 自動運転が開発され、新型車には電気自動車も多くなってきた。 そんな環境のなか、旧車と呼ばれる年代のクルマを、新たな愛車として選ぶ方も多くいる。 なぜ新たな愛車として迎え入れたのか? 新たにオーナーとなられた方にお話を伺った。 ■根っからの日産フリークなファミリー 今回、お話を伺ったのは、親子で旧車を愛車としているご家族だ。 お父さまは日産スカイラインGT-R(R32型)を所有しつつ、最近日産パルサー VZ-R(N15型)を通勤メインのクルマとして購入したのだとか。 長男である息子さんは、お父さまと同じ型のスカイライン GT-Rを所有されている。 今回お話を伺うことはできなかったが、次男の息子さんは、日産フェアレディZ(Z33型)にお乗りとのことだ。 おわかりの通り、大の日産フリークなご家族なのだ(笑)。 今回、パルサーVZ-Rを購入されたお父さまの内容となる。 今所有されているクルマについて伺った。 「R32スカイラインGT-Rは2008年頃、知人が手放す車両を購入しました。それまで、DR30 スカイラインRSターボに乗っていたのですが、やはりGT-Rには一度は乗っておきたいという思いを持っていたため、意を決して乗り換えました」 やはり、多くのクルマ好きが一度は憧れる、GT-R。 日産フリークであり、憧れを持っていた方にとって、そんな縁談の話は願ったり叶ったりに違いないだろう。 最近購入された、パルサーについて伺った。 「パルサーは半年ほど前、中古車店で購入しました。通勤で使っていたK12マーチからの買い替えになります」 なぜ、今まで乗られていたマーチより古い、パルサーに乗り換えられたのか? 「パルサーVZ-Rも、いつか乗りたいと思っていました。今回の購入時には、VZ-Rしか考えていませんでした」 そこまでの熱い思いを持たれているには理由があるはず。 さらに詳しく伺ってみた。 「昔、耐久レースに日産のワークスとしてVZ-Rが出てました。その時にびっくりするほど速かったんです。」 筆者も、当時VZ-Rがレースに出ていたのは知っていた。 しかし、残念ながらまだ幼かった筆者は、実際にレースシーンを見る機会がなかった。 レースでの活躍を、生で見た感想も聞くことができた。 「そのレースでは、当時の愛車と同じDR30のRSターボも出走していたのですが、VZ-Rが立ち上がりの加速で離れていっちゃうんですよ。テンロク(1.6L)なのに。それが衝撃でしたね」 「まだ幼かった、息子二人も観戦していたのですが『お父さんのクルマを抜いてった!』と驚いていましたよ!」 幼い息子さんにとっても、父親が乗っている身近な存在である同型のスカイラインが抜かれてしまったことは、記憶に残っているそうだ。 「特に次男がカルチャーショックだったようでして、のちに免許を取って最初に買ったクルマがVZ-Rでした(笑)」 現在、Z33にお乗りの息子さん。 幼心に受けた衝撃がきっかけとなったのか、最初の愛車として3ドアのパルサーVZ-Rを選び、腕を磨いていたそうだ。 VZ-R購入時、他に候補のクルマはあったのか? 「なかったですね。VZ-Rだけでした。最近のスポーツモデルの中古車も同価格帯でありましたが、候補には入っていませんでした」 なぜ、指名買いだったのか? 「この年代(90年代)のクルマって、個性があるじゃないですか。そこに惹かれてました。この頃って、各社ライバルメーカーのクルマに勝ってやろう!とかラリーで優勝してやろう!とか、攻めの姿勢だったのが良いですよね。VZ-RにもN1という仕様もありましたし」 ■心がけているのは予防整備 ここからは、購入後のエピソードについて。 すでにR32 スカイラインGT-Rもお持ちなので、経験は豊富だ。 今までの経験を踏まえ、納車後におこなった整備があるとのこと。 「GT-Rでも同じことを心掛けているのですが、出先で不動にならないよう、予防整備をしています。今回、納車後にオルタネータや点火系などの交換をしました。燃料系はまだなのですが、ここもやっておけば心配は減りますね」 予防整備としては、かなり手厚い部類と思う。 中古車である為、今までの扱われ方が分からないことは多い。 “無事に帰宅する”これは事故に限ったことではなく、忘れがちではあるが整備についても、重要なことと思う。 マイナーな不具合に見舞われたこともあるそうだ。 「タコメーターが動かなくなってしまう症状が出てしまいました。メーター交換をしようと思ったものの、VZ-R専用メーターはすでに製造廃止。標準グレードの物はまだ手に入ったので、メーター修理専門のお店に修理を依頼しました。新しいメーターから故障した部品を移植して、専用メーターを直してもらいました」 「他にも調べると在庫が残り1個の物が多く、気になるところは交換しました」 その行動力と決断に恐れ入ってしまう。 90年代車は多くの「グレード専用部品」がある。 その部品自体の新品はなくとも、流用や移植で修理が可能であり、専門店もあることには驚いた。 ■カスタムも長期の目で見た安心感を 次にこだわりの部分について伺った。 「本当は3ドアが欲しかったのですが、タマ数も減っており、値段も息子が購入したときの1.5倍になっていました。そのなかで見つけたのが今の愛車です」 パルサーVZ-Rにはボディ形状は3タイプある。 4ドアセダン、3ドアハッチバック、5ドアハッチバック。 程度と金額から5ドアハッチバックを購入されたとのことだが、最初拝見した時に違和感があった。 「5ドアはRVブームもあって、フロントバンパーがRVっぽいデザインになっています。それが、ちょっと好みと合わなかったため、3ドアVZ-Rのバンパーに交換しました」 話を伺って、違和感の理由がわかったのだった。 VZ-Rが新車で販売されていたころ、世間はRVブームであった。 そのため、パルサーの5ドアにはRVテイストを与えていた。 そのデザインのまま、VZ-R専用エンジンを載せて販売していたのだ。 他にも、リアのスポイラーをオーテックバージョンの物に変更されている。 交換する際、標準装備のスポイラーと取付穴の位置が合わなかった。 バックゲートを別途中古で購入、穴を開け直してから交換されたそうだ。 従来の穴を埋めることによる、トラブルを避ける為のこだわりが表れていた。 また、マフラーも購入時は社外の物が装着されていたが、純正採用の実績があるフジツボ製に交換されたとのこと。 ■ぜひ、そのクルマのことを理解して乗って欲しい! これから、90年代のクルマに乗ろうと思っている方へ、何かアドバイスがあるか伺ってみた。 「せっかく乗るなら、そのクルマのことを理解して、少しでもいいので勉強して乗ってもらいたいですね。もし、ネームバリューだけで乗りたいと思っているのでしたら、良い結果とならないことが多いので、やめた方がよいと思います」 90年代のクルマは、まだまだ現役で走っている個体も多く、街中でも目にするだろう。 映画やアニメなどでフューチャーされることや、過去の映像作品も動画サイトで目にするだろう。 そこでクルマの名前を知り、同じクルマに乗りたい!と思う人は多くいる。 いつまでも現役で、人気で居続けることは嬉しいことだ。 ただ、そのクルマのことを理解せずに乗った時、旧いが故に現代の感覚と違うことはもちろん、トラブルも発生する。 理想と違うことが起きた時、大きく落胆するだろう。 しかし、ほんの少しでも、そのクルマについて知る努力をしたことで、感じ方は変わってくる。 「せっかく憧れのクルマを愛車としたのに、残念な思い出となってもらいたくない」 そんな思いのこもった言葉だった。 ■ 総括 メーカー同士、意地の張り合いに熱くなっていた時代 今回お話を伺ってわかった、現代にあえて旧車を選ぶ理由。 そこには、デビュー当時の活躍を目の当たりにしてきた方ならではの理由があった。 各メーカーのスポーツモデルには、明確な意識をしているライバルがいた。 そのクルマたちは、ワークスとして戦うレースに留まらず、そのクルマを選んだオーナー同士もお互いを意識し合い、サーキットなどで性能をぶつけ合っていたのだ。 ユーザーも含め、ライバルに秀でるよう切磋琢磨していた時代を見てきたオーナーならではの、熱さを感じるための選択であったと知ることができた取材となった。 [撮影&ライター・お杉]

旧車に多いターボエンジンってなに? なんとなく理解している車用語を詳しく解説
ハイパワー化を追い求めていた時代に生み出されたクルマ、現在では旧車と呼ばれる車種に搭載されていることの多い「ターボ」。エンジンの高出力化にターボが有効とわかっていても、詳しい仕組みまでは知らないという人も少なくありません。 そこで今回は、ターボの仕組みを基本から特性まで詳しく紹介します。 排気量以上のパワーを生み出すターボ ターボの正式名称は「ターボチャージャー」で、日本語では「過給機」と呼ばれています。「チャージ」するのは、燃料の燃焼に欠かせない空気です。 同じ排気量のエンジンでも、ターボの装着によってより高いパワーを発揮できます。なぜターボでパワーアップができるのか、エンジンの基本的な仕組みとともにみていきましょう。 エンジンパワーは爆発力で変わる ターボの説明をする前に、まずはエンジンがパワーを得る仕組みを簡単に解説します。一般的なガソリンエンジンは、シリンダーに取り込んだ空気と気体化した燃料を混ぜた混合気に点火し、爆発した際に発生するエネルギーを取り出すという仕組みです。 つまり、爆発力を高めれば、それだけエンジンパワーが上がります。燃料を増やせば爆発力を上げられると単純に考えがちですが、燃焼(爆発)させるには燃料に見合った量の酸素も必要です。空気(酸素)の量が変わらなければ、残念ながら燃料を増やしても爆発力は向上しません。 そこで、エンジンに送り込む空気量を増やすために、ターボチャージャーが開発されました。ターボによって空気を圧縮しエンジンに送り込む空気量を増加させ、混合気の爆発力を高めます。 ターボは排気ガスを利用して空気を圧縮 ターボは空気を圧縮して、より多くの酸素をエンジンに送り込む装置です。空気は圧縮すると密度が高まり、同じ体積でも量を増やせます。さらに、ターボで空気を圧縮する際は、排気ガスの圧力を使用するため、別のエネルギーを必要としません。本来、ただ排出するだけであった排気ガスのエネルギーを再利用するため、効率的にパワーアップできる点もターボの特徴です。 大まかな仕組みは、排気管の途中に「タービン」と呼ばれる風車を取り付け、排気ガスの圧力で風車を回し、吸気菅側にあるコンプレッサーを回して空気を圧縮します。 ターボには実は欠点もある 排気量以上のエンジンパワーを引き出せるターボですが、残念ながら万能ではありません。圧縮された空気の温度上昇と、「ターボラグ」と呼ばれる空気を圧縮できるエネルギーが得られないタイミングが存在します。ターボの欠点と補うための装置を紹介します。 ターボの効率を最大化するインタークーラー 空気は、圧縮されると温度が上昇する性質があります。温度が高い空気をエンジンに送り込むと、ノッキングが発生しやすくなりパワーや燃費面で不利です。また、気体は温度が上昇すると密度が下がる性質もあるため、十分なパワーを発揮できません。そこで、圧縮して温度が上がった空気を冷やす装置として、インタークーラーが開発されました。 インタークーラーは、ラジエーターと同じ仕組みです。圧縮して温度が上昇した空気をインタークーラーに送り込み、フィンで放熱して温度を下げます。 ただし、国産ターボ車が登場した1979年当時はインタークーラーを装備していないクルマも多く、パワー競争が激化した1980年代に入ってから各メーカーがこぞって採用しました。 ターボラグのないスーパーチャージャー ターボは、排気ガスの圧力でタービンを回して空気を圧縮します。つまり、排気ガス圧力の低い低回転域では、空気を圧縮する力を十分に得られません。タービンが回って空気を圧縮できるまでの時間差を「ターボラグ」といい、この間には十分なパワーを発揮できないため、ターボの弱点だといえます。 ターボと同じく空気を圧縮する「スーパーチャージャー」は、この弱点を克服しました。空気の圧縮にエンジン自体の回転を利用する仕組みのため、低回転域から効率よく空気を圧縮できます。しかし、エンジンパワーの一部を空気の圧縮に利用するため、少なからずパワーロスが発生する点がデメリットです。特に高回転域では、スーパーチャージャー自体が足かせになってしまい、あまりパワーが伸びません。 ターボ車は部品点数が多いので中古車の場合はしっかりと確認 ターボは、ハイパワー化の一途をたどっていた1980年代以降、多くのクルマに搭載されました。特にスポーツカーなど、現在でも中古車として人気の高い車種に数多く搭載されています。また、タービンやインタークーラーの交換といったチューニングで、簡単にパワーアップをできるのもターボ車が人気の理由です。 ただし、自然吸気エンジンに比べてターボ車は部品点数が多いうえ、過給によってエンジンに大きな負担をかけるため中古車を購入する際は状態をしっかりと確認しましょう。 また、ターボ車を売却する際は、ターボ関連の部品を正しく査定してくれる専門業者に依頼しましょう。一般的に中古車として価値が高いのは、純正で状態の良い個体です。しかし、旧車の場合は状態の悪くなった純正パーツを交換している場合も多いでしょう。旧車の取り扱いに慣れていない業者だと、純正ではないという理由だけで査定額を下げられるかもしれません。流通量の少ない旧車であっても、車輌状態を正しく評価できる業者に持ち込むことが重要です。

学生だからってあきらめるのはまだ早い!工夫次第では夢じゃないこだわりの旧車ライフ
近年、20~30代の若者の間でネオクラシックカーと呼ばれる旧車ブームが巻き起こっており、非常に注目を集めている。 都内で大学生をしている筆者のまわりでも、ゴルフやボルボに代表される王道車種はもちろん、そのほかにも個性的なネオクラシックカーがほしいという声がちらほらと聞こえるようになってきた。 クルマが好きな筆者としては、同世代の友人たちがどんな要因であれ自動車に興味を持ってくれるのは本当に嬉しいことである。 ▲近年絶大な人気を得ているゴルフ2 ▲同じく人気を集めているボルボ240 しかし我々20代の学生にとって、クルマというのはとてもハードルが高い買い物、ましてや旧い車なんてなおさらのこと。 しかも自動車というものは買っただけでは済まず、維持費がかかるし、旧車なら修理費もかかったりもする。 そういった点で、皆あこがれてはいるけれど、なかなか手が出ないというのが現状である。 そんな“旧車に乗りたいけれど、ハードルが高くてあきらめかけている同世代のオーナー予備軍の方々”へ。 ごく一般家庭で育った文系大学生の筆者が、“どのようにして旧車ライフを送れているかのコツと工夫”を参考になるかはさておき、お伝えしておこうと思う。 ■旧車は維持費が高い、燃費が悪いというイメージについて 僕のまわりの大人や友人、いろいろな人から“超”頻繁に聞くフレーズとして“旧車は壊れる、旧車は金がかかる、燃費が悪い”がある。 これは確かに間違っていないが、正しいとも言い難い。 旧車のなかでも大小さまざま千差万別であり、これを真に受けて旧車をあきらめてしまうのは非常にもったいないと思う。 ■旧車と付き合っていくうえでネックになる維持費や修理費を節約するには 旧車がその魅力にもかかわらず敬遠される要因でもあるランニングコスト。 これは工夫次第で抑えることができるのだ。 もちろん税金や保険は節約できないので、頑張って捻出する以外に選択肢はないのだが、ここでは車検や整備費などの抑え方について解説していく。 ポイント1 ~ユーザー車検~ 車検というと、整備工場に依頼して取得してもらうのが一般的である。 しかし旧車の場合、車検を取得には現行の自動車とは少し異なる技術が必要であり、整備費が高くついてしまうのだ。 それを自分でおこなうことによって、大幅に費用を節約することができる。 もちろん車両によって注意点などが異なったりもするわけだが、近年ではユーザー車検に挑む人も増えている。 さらにネットにも多くの情報が公開されているので、それらを参考にすると良いだろう。 ポイント2 ~こまめな点検、整備を自分で~ 旧車は壊れやすいといわれるが、理由としてはさまざまな部品が年数を経て劣化していることがあげられる。 それらの部品は大抵大事になる前に予兆があり、それに気が付いて事前に交換や修理、調整をしてやることで解決できる。 ほったらかしにしないで日頃からこまめに車の様子を観察して注油するなど、メンテナンスしてクルマとコミュニケーションを取ることが大切だ。 これらのことを続けていれば、オーナーにしかわからないクルマの声のようなものが聞き取れるようになっていき、これが旧車と付き合っていくことの醍醐味だったりもする。 ポイント3 ~修理を自力で行う方法~ 旧車は壊れやすいといわれるが、それゆえに構造がシンプルで簡単に修理できる傾向がある。 メジャーな車種や一部輸入車などは、未だにメーカーから新品の部品が生産されていたり、そうでなくてもヤフオクやイーベイなどを駆使すれば、素人でも簡単に部品が入手できるケースが多い。 一定数人気のある車種だと修理の解説をしている動画やサイトなどもあるので、筆者のような完全な素人でもネット時代の恩恵である程度の修理はできてしまうのだ。 手をかければかけるほど愛着が湧くので、なるべく自分で修理するというのもオススメである。 ■筆者がオススメするクルマの条件 比較的維持しやすいクルマの条件を解説する ・排気量が小さめ 税金やガソリン代を抑えるためというのもあるが、排気量はクルマ自体の大きさや重さ、パワーに直結する指標であるので、排気量が少なければタイヤにかかる負担も小さくなりやすい。 ▲排気量ごとの税金 ・1960~1970年代に設計されたクルマ この年代に設計されたクルマは、それ以降のクルマに比べてはるかにシンプルな構造になっていて、電気的に車を制御するシステムなどもない。 つまりDIYで修理をするにも比較的イージーであり、不便な部分は多いけれど運転するのにもコツが要るため、ドライバーを育ててくれる利点もある。 ▲シンプルで手の入りやすい旧車のエンジンルーム ・自分が心から惚れ込んでしまったクルマ 旧車というのは現行の自動車に比べてやはり手間がかかるし、苦労する部分もあるので情熱がないとなかなか厳しい。 なので苦労や手間もすべて吹き飛んでしまうくらい大好きなクルマを選ぶことが肝心だ(もちろん妥協のないクルマ選びというのは口でいう100倍以上難しいのだけれど…)。 ■さいごに筆者より クルマが欲しいと思ったなら、旧車やクルマ全般によく言われる噂やイメージなどを鵜呑みにせず、ネットなり本なりで細かくいろいろと調べてみることを薦めます。 ハードルが高いとはいえ情熱があれば案外どうにでもなったりするものです。 諦めなければいつかきっと手に入るはず。 これを読んでいる旧車にあこがれているみなさまが、ステキなカーライフを送れることを心より祈ります。 [ライター・画像 / 小河昭太]
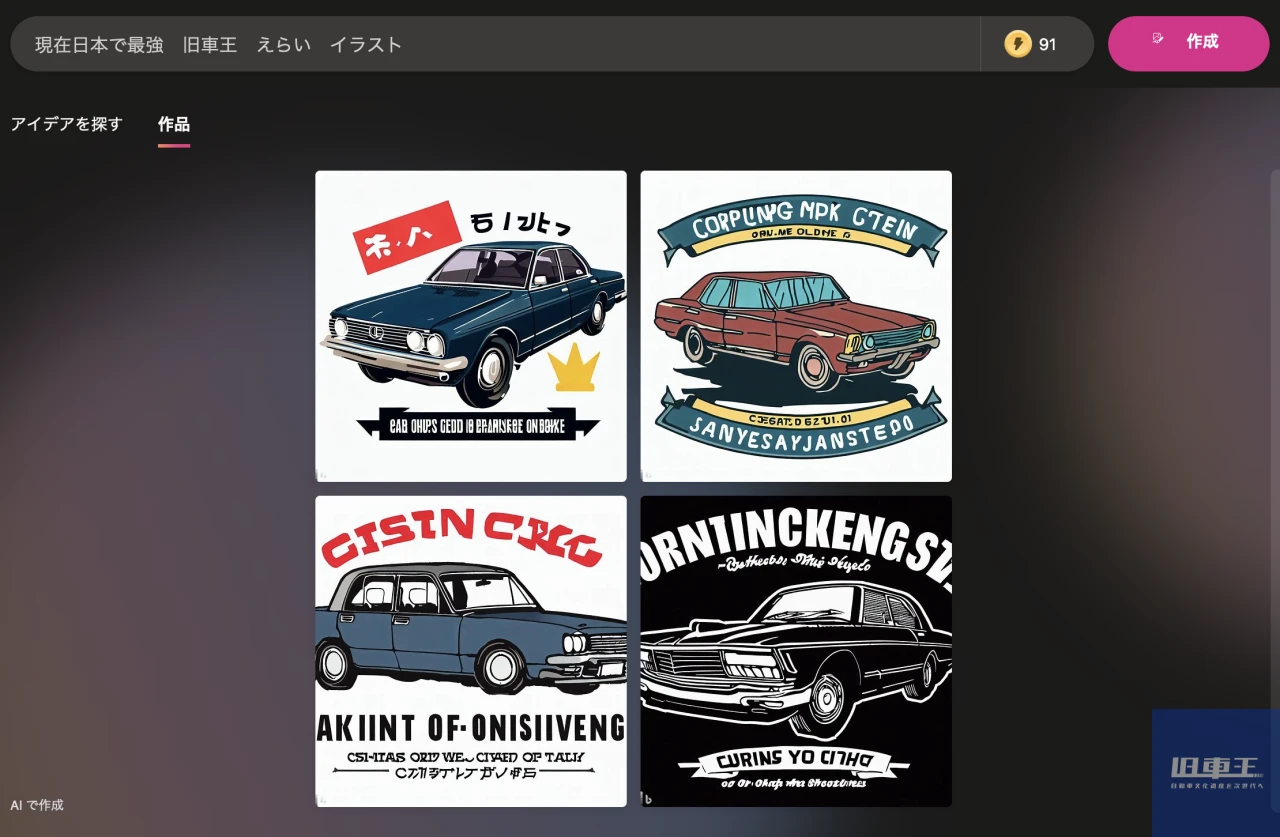
「AI」が描くオレたちの旧車!
さて、ワタクシまつばらは「イラストレーター」としての肩書きも持っております。 webの挿絵とか本の表紙とか説明図とか、線画が多いのですがこんなの描いているんですよ、実は。 さて、そんなイラストレーターとしての立場でお話しすると、昨今様々なメディアでウワサの「AI」。 すなわち「Artificial Intelligence」の略ですが、昭和時代なら鉄腕アトムに搭載されている「人工頭脳」とか、まあ、そんなイメージがありますよね。 その「AI」くん、ご存知の方もいるかとは思いますが、最近イラスト業界では話題持ちきりなのは、写真ライクな美少女画像とか、かっこいいヒーローのポーズとか、AIが描くそのハイクオリティな出来栄えに、多くの人が「近い将来イラストレーターの仕事なくなっちゃうんじゃないか」とか「この出来ならモデル撮影のカメラマンも不要になるかも」とか、色々ウワサが絶えません。 まあ、その辺の考察は別の機会にイロイロ考えるということで、今回は旧車王らしく、そしてプロのイラストレーターとして、AIが生成する「オレたちの旧車」を考えてみようというのが今回のネタ。 いやあ、AIくん、なかなか面白いですぜ、ということではじまりはじまりー。 まずは手始めに、AIくんに何か描いてもらいましょう。 今回登場するのは、Microsoftのブラウザ「Bing」に搭載されているAI「DALL-E」という画像生成AIくんと、SeaArt というAIコミュニティで使えるイラスト生成「img2img」というAIくんです。 現在のAIにはそれぞれ特徴があって、画像を生成するためのキーワード「プロンプト」=ワレワレは「呪文」とか呼んでますが(笑)、同じ「呪文」を唱えても、生成される結果は大幅に違うというように、すでに「AIの個性」というものが芽生え始めている感じがします。 まあ、そんな前振りはともかく、早速AIくんに「描いて」もらいましょう、オレたちの旧車! まずは「DALL-E」くんの描く旧車! 呪文は「縄文時代のスポーツカー、日本、古代、縄文人」って、旧すぎ?(笑) おおっ! なんかそれらしいイメージというか、チキチキマシンに出てくる「001 岩石オープン」みたいなイメージだけど、まあ、縄文人ならこんなスポーツカー、アリだよね!という感じでいいっすね。 さて、全く同じ呪文を「img2img」くんにお願いして、縄文人のスポーツカーを・・・・・ って、おい!サイドカー?・・・・昭和時代じゃないかコレ?って感じで、同じプロンプト=呪文唱えてももこんなに違う。 確かに運転手は縄文人っぽいけれど。 さて、さらに時代は進み、時は飛鳥時代。 聖徳太子のスポーツカーをAIくんたちに描いてもらいましょう。 デザインは遣隋使でお馴染みの小野妹子くんです! 「DALL-E」くんはなんとなくそれっぽい感じに仕上がってますね・・・。 キャラデザインがそれとなく中華風。 これ見るとエンジンは付いてなさそうなので、足漕ぎかも。 足漕ぎだったらカッコいいすね、コレ。 で、次は「img2img」くん・・・うを!オモシロすぎ!なんだよコレ(笑)。 まるで祇園祭か岸和田のだんじりじゃないっすか。 やはりエンジンどこに付いてるんだか・・・、あ、飛鳥時代だからエンジンなんてないのか。 まあ、いくら旧車王でも縄文や飛鳥時代は旧すぎなので、もっと近いところで、大正時代はいかがでしょう? あ、コレはかなりいい線行ってますね、AIくんも。 近い過去ならあまり忘れてないようで。 こんなありそうでなさそうなグラフィックが、AIくんが最も得意とするところなんでしょう。 呪文は「大正時代 実用車 日本製 自動車 東京 モダン」です。 さて、それではもう少し現実的に。 AIくんもがんばって画像を生成してくれていますぞ。 作画は「DALL-E」くん。 呪文は「スズキ フロンテクーペ 70年代 スーパーカーみたい かっこいい」です。 過日鬼籍に入られたデザイナーで、世の中に直線なんてものはないと豪語されていたシド・ミードさんが、もしシトロエン2CVをデザインしていたならば・・・、という想定で、こんな呪文を唱えてみました。 こちらも作画は「DALL-E」くん。 「シド・ミード デザイン 2CV シトロエン」です。 うむー、どちらも納得できるかどうか?と言えば「そうかもね・・・」という感じになっちゃうのですが、それでもなんとなく「ソレっぽい」仕上がりになっているのは、さすがAI(笑)。 フロンテクーペはかっこいいなあ。 今度はシンプルに、呪文を「シトロエン 2CV」として、「img2img」くんに描いてもらいましょう・・・・って、なんとなくビートル混ざってる感が(笑)。 ドアの枚数とか構造の描写に、かなり悩んでいる様子が見えますね。 まあ、それとなく特徴を捉えていたりして、誰が見ても「2CV」というところはキッチリ押さえているようです。 というように、現状でのAIくんは、かなり無茶な要求にも真摯に、クソ真面目に応えてくれます。 そもそも、普段ワレワレが使っているコンピュータも「人間が指示したり要求したこと」以外はできませんよね。 言われたことを忠実に実行する。それが彼らの行動です。 なので、AIくんが「描いて」くれたイラスト的なものや写真的なモノも、プロンプト=呪文をできるだけ忠実に再現してくれたものだと思うのです。 それはネット上に溢れる情報=「ビッグデータ」から、必要なものを取り出して組み合わせたモノなので、ワレワレ人間が思いもよらないような、すなわち「意志」や「感情」を省いたデータの組み合わせが可能、というのがAIくんの強みでもあり、弱みなのかな、という気がします。 ともあれ、絵描きとしては、AIくんはなかなか面白い遊び相手だなと思っておりますので、これからもイロイロ一緒に遊んでみようと計略中であります。 いや、こいつ面白いっすよ(笑)。 最後に「現在日本で最強 旧車王 えらい イラスト」という呪文を唱えてみましょう。 応えてくれるのは「DALL-E」くんです。 どうですか?最強? ありそうでなさそうな、ちょっと素敵なデザインではありますね。 [画像 / OpenAI「DALL-E」, Stable Diffusion「img2img」・ライター/まつばらあつし]

先入観から誤解しやすい、旧車へのボディーコーティングについて語る
▲筆者の所有する空冷ビートル。ソリッドカラーとはいえクリアー層を有するが、比較的高年式の車輌とはいえ塗装の質は現代車に比べ明らかに劣る 新車・中古車に関わらず、クルマを購入する際に、必ずといってよいほどボディーコーティングの施工を勧められることはないだろうか? クルマの見積書に記載があれば、これから自身のモノとなる愛車のために、いわれるがまま施工される方も多いことであろう。 もはやボディーコーティングといえば、車輌購入時のオプションメニューとして、代表的な選択肢の一つといっても過言ではないはずだ。 さて、ここまでは一般的な現代のクルマでの話であるが、これが旧車へのボディーコーティングとなったら一体いかがなものであろうか? 今回はボディーコーティング施工の業務経験から、旧車へのボディーコーティング施工について、私クマダの主観とはなるが、初心者のためにできるだけ簡単に意見を述べてみたいと思う。 ▲現代のクルマでは、購入と共に当たり前のように施工されるボディーコーティング そもそもボディーコーティングとは何か? ボディーコーティングとは、その名のとおり、自動車のボディーなど外装に施工する保護処理の一つである。 業務用の特殊なコーティング剤を塗布してボディーの塗装面全般を保護し、耐久性を向上させるためにおこなわれる。 使用されるコーティング剤については、黎明期はワックスに類似する程度のものから、フッ素(テフロンとも呼ばれる)やシリコーンを用いたポリマーコーティング剤が主であったが、おおよそ10数年ほど前から、(ガラスの組成に近いシロキサンやポリシラザンを原料とする)二酸化ケイ素を用いたガラス系コーティング剤が主流となった。 今回の記事は、現代において主流となったガラス系コーティングの施工を前提として、話を進めていきたいと思う。 ▲昨今では近所のガソリンスタンドでも施工できるほど、身近になったボディーコーティングではあるが・・・ ボディーコーティングを施工するメリットとは? それでは、旧車にボディーコーティングを施工するメリットとデメリットについて語っていきたい。 まず、現代車に施工する場合と同様の一般的なメリットをあげれば、以下のとおりだ。 【塗装の保護】厚く硬いコーティング膜により塗装面を傷やスクラッチなどのダメージを緩和し、傷そのものをつきづらくする。 【光沢に優れる】ガラスの組成に似た成分を持つことから光沢に優れる。ハイグレードなコーティング剤を施工すれば、その膜厚によりクリアー層がさらに厚くなった様に見える製品も存在する。 【汚れが定着しづらくなる】コーティング被膜上に汚れが定着しづらくなる。ピッチ・タールなど、特に油性の汚れがこびり付くことが少なくなる。また、長期間放置したものはNGだが、水アカも通常の洗車でかなり落としやすくなる。 【長寿命である】ガラス系コーティングは無機質のため、酸化しないことが特徴だ。 旧来のポリマーコーティングについて全てがそうとはいえないが、ロウや石油系溶剤などの有機物からなるワックスについては、熱を受けたり時間の経過により、ゆくゆくは保護膜そのものが酸化し、汚れとともに塗装にこびりついて劣化してしまう場合もある。 無機質であるガラス系コーティングは熱や紫外線に強く、酸性雨からもボディーを保護する効果が高い。 これは有機物からなるワックスやポリマーコーティングとの最大の違いである。 一般的に寿命は3~5年といわれるが、筆者の経験上、メンテナンス次第だが寿命はそれ以上ともいえる。 【旧車に施工するメリットは?】旧車に施工するメリットは、とくに青空駐車にてクルマを保管するオーナーにとって、紫外線や酸性雨からボディーの塗装を保護できることが最大のメリットとなるはずだ。 それ以上に、現代車のように厚いクリアー層を持たない旧車については、膜厚のあるコーティングを施工することによって、ボディーに光沢を与えることができる場合もある。 また、油性の汚れがこびり付きづらくなる防汚性能にもメリットがある。 キャブレター車など、リアバンパーのマフラー周りに排気ガスによる黒いススがつくことが無かろうか? こういった汚れが通常の洗車で落としやすくなるのだ。 逆にボディーコーティングを施工することによるデメリットは? それでは、逆にデメリットを述べよう。 今日においては、ボディーコーティングを施工するうえで、選択肢はほぼガラス系コーティング一択となるであろう。 考えられるデメリットは以下のとおりだ。 【施工費用が高額である】価格が高い。誰しもがそう感じるはずだ。情報化の進んだ今日では、ボディーコーティングに用いるプロ用の薬剤もインターネットショッピングで手に入れることができる。薬剤そのものの価格は、施工する金額の数分の一となり、けっして高価ではない。 それでは、なぜプロに施工を依頼すると高額なのか? 答えは簡単だ。施工にとても時間がかかり、とにかく重労働だからである。 その理由を次の項で述べる。 ▲旧車ではありませんが、筆者はこんなYouTube動画をつくっております。https://youtu.be/SK1gWpUxyIk ボディーコーティング剤への過度な期待は禁物 ところで、実際にボディーコーティングの施工をプロに依頼する際の検討材料といえば、よほどのマニアでない限り、なんとなく使用するコーティング剤のブランドや、ネームバリューから想像される仕様や性能に興味が向きがちではなかろうか? 私クマダは、この部分に注意喚起をしたい。 あくまでもボディーコーティングの施工において、作業の主役はコーティング剤そのものを塗布する工程ではなく、その施工時間の大半を費やす、施工者自身による下地作りの工程なのだ。 では、ボディーコーティング施工において主役となる、下地作りとは何か? 簡単にいえば、それはボディーの汚れ落としと塗装面の研磨だ。 ボディーに付着した長年の汚れ、鉄粉やピッチ・タールをトラップ粘土で除去することから始まり、ボディーについた傷やスクラッチを、ポリッシャーを用いて入念にコンパウンド掛けをして削り落とす。 使用過程のクルマにおいては、通常の洗車では手の届かない部分の汚れ、一例を述べれば、モールとボディーのすき間やエンブレムの周りなどにこびりついた長年の水アカなどを、スケール除去剤のような個人で取り扱うにはリスクのある「プロ仕様」の特殊な薬剤をもちいて入念に落とす。 実は、ボディーコーティングを施工することでクルマが輝くのではなく、むしろこの下地作りの作業でクルマが輝くといっても過言ではない。 ではなぜ、ボディーコーティングを施工するために、そこまでの作業が必要なのか? それは、ガラス系コーティングの被膜はとても強固なため、簡単にやり直しができないからである。 ガラス系コーティングはシンナーで簡単に落とせるような代物ではない。 下地となる塗装面に傷や汚れが残ったまま施工してしまうと、そのままその傷や汚れを強固にコーティングしてしまうのだ。 新車と違い、使用過程におけるクルマを磨くことは、面倒なことこの上ない。 さらにコーティング剤を塗布する場合にも、塗布する場所の温度や湿度など、施工環境への配慮が必要である。 また施工後も、決められた時間、ボディーを水に濡らさないようにして、しっかり乾燥させなければならない。 とにかく、全般的にとても気を遣う作業なのだ。 だからボディーコーティングの施工は高額となるのである。 どこかで聞いたような言葉で述べれば、「コーティング剤の性能の違いが、コーティングの仕上がりの決定的な差ではない」のだ。 むしろ、施工者の技術や経験で仕上がりに大きな差がでるといって過言ではないであろう。 コーティング剤のネームバリューに惑わされてはいけない。 お金を費やすべきものは、施工者自身の腕と情熱なのだ。 ▲旧車ではありませんが、筆者はこんなYouTube動画をつくっております(その2)https://youtu.be/mLqZ6kl4BWc 悩ましい旧車へのボディーコーティング 旧車にボディーコーティングを施工する場合は、さらにいくつか注意するべき点がある。 ここまでの記事を読めば、勘の良い読者の方は気づかれたことであろう。 ボディーコーティングの下地作りをする際におこなう、電動ポリッシャーによるコンパウンド掛けはボディーの塗装面を磨くので、当然のことではあるが少なからずボディーの塗装を薄くしてしまう。 もとより旧車の塗装といえば、経年により少なからずダメージがあることが前提ではある。 しかしながら、事故などの補修による再塗装部分やキレイにレストアされた車輌など、プロフェッショナルであっても、その塗膜がどのような下地の上に乗っているものか予想がつかない場合が多い。 こういった部分に安易に手を入れると、下地作りの作業途中で、思いもよらない原因で塗装面を傷めてしまう場合もあるのだ。 旧車のボディーコーティングについては、施工を断られることもあると耳にしたことがある。 当然のことであろう。 旧車の塗装に手を入れるには、それなりの経験が必要だ。 ボディーコーティング施工者の誰もが旧車を相手にできるわけではないのだ。 レストアされた車輌であればまだしも、貴重なオリジナルペイントの車輌に手を入れる場合は特に慎重に作業せねばならない。 それこそ取り返しのつかない事態になりかねないからだ。 ならば、旧車のボディーコーティングはどこに依頼すれば良いのか? ボディーコーティング施工は洗車の延長線上、すなわちカーディティーリング業界に属する。 旧車への施工を唱っている施工業者であればなんら問題ないが、身の回りに見つからなければ、鈑金塗装の、それも旧車が得意なプロフェッショナルの門を叩くと良い。 ワックスは塗料を弾くため、塗装時のトラブルの素となるためか、洗車業界と鈑金業界は水と油といわれることもある。 しかし、常にボディーペイントの下地と塗膜に向き合っている彼らからは「佳い(よい)」アドバイスをいただけるはずだ。 ▲業務上、今日までガラス系コーティングを施工する時間はいくらでもあったが、今日までワックス仕上げで維持している。メキシコ産ビートルとはいえ、すでに25年が経過したオリジナルペイント塗装はいたるところでクリアー層の剥がれが始まっている まとめ レストアされたクルマはどれも美しい。 しかし、自身の幼少期、これらのクルマが新車であった頃、はたして、これほど艶やかに輝いていただろうか・・・?ふと思うことがある。 旧車といえば、ある時代より旧いクルマの場合、ソリッドカラーのクルマなど、クリアー層を持たない塗装が多く存在する。 筆者もいわばアラフォーのおっさんとなり、昨今の旧車ブームではネオクラシックと呼ばれる1970年代後半から1980年代のクルマが自身の刷り込みのクルマであるのだが・・・。 そういえばこのクルマ、新車の頃はもう少し落ち着いた輝きだったような・・・。 特にここ数年、旧いクルマを眺めていると、このように感じることが多い。 極端にいえば「不自然」に感じるのだ。 レストアされ、新車時以上に高品質な塗装で、エンジンルームのスミからスミまで美しく厚い塗膜でオールペイントされたクルマ。 こういったクルマには、躊躇せずボディーコーティングを施せばよいことであろう。 しかし、オリジナルペイントが残るクルマはどうだろうか? 当時はまだ高額だったシュアラスターのカルナバで仕上げたクルマは、まだ幼かった筆者の目でも違いを感じたものだ。 ここからは余談であるが、ここまでボディーコーティングについて語っておきながら、特にオリジナルが随所に残る旧車風情が漂う佳き時代のクルマに対し、安直にガラス系コーティングをおススメして良いものかと感じているのが筆者の正直な感想だ。 青空駐車かつ日常使いの旧車オーナーにとって、ボディーコーティングは強くおススメできるものではあるが、決して必須であるとはいえない。 有機物ゆえに、ボディーの水アカの原因になりかねない旧来のカーワックスであっても、その自然な艶と肌ざわりに根強い人気があり、週末の洗車とワックス掛けがルーチンワークとなっているベテランオーナーは数多い。 長い期間隅々までキレイに磨かれ、良好な状態を保たれた旧車のボディーの細部に残る、どうしてもオーナーが落としきれないちょっとした水アカに、むしろそのオーナーの愛着の深さを感じてしまうことがあるのだ。 あばたもえくぼ。 結局は、自身のいちばんやりたい方法でクルマを仕上げるのが、究極の旧車メンテナンスではなかろうか。 閑話休題。 旧車においては、最新が最良と言えないことが多いのだ。 ボディーコーティング然り。 ボディーコーティングはあくまでも、クルマ維持の選択肢の一つに過ぎない。 ※私クマダはYouTubeでポンコツ再生動画を公開しております。ぜひ動画もご覧になってください。チャンネル登録お待ちしております。https://www.youtube.com/@BEARMANs [ライター・クマダトシロー / 画像・クマダトシロー, AdobeStock]
